あしたが変わるトリセツショー『脳・血管いきいき!超シンプル「血圧」ケア術』
血圧と聞くと「年をとったら上がるもの」と思っていませんか?実は、上が130mmHgを超えるだけで、脳卒中や認知症のリスクが急上昇することが最新研究で分かってきました。今回の『あしたが変わるトリセツショー』では、誰でもすぐに始められる「血圧ケアの新常識」が紹介されました。この記事では、放送内容をもとに、血圧を下げるシンプルな生活術をまとめます。
【あしたが変わるトリセツショー】スパイスで減塩&味変革命!練りスパ・スパイ酒の作り方まとめ|2025年7月31日放送
能勢町が実証!「毎日測る」だけで血圧が下がる

大阪府能勢町では、地域ぐるみで住民が毎日血圧を測定し、記録するプロジェクトが行われています。リーダーを務めるのは大阪大学大学院の神出計教授。この取り組みは、単なる健康管理ではなく、「自分の体と毎日向き合う」ことを目的に始まりました。
参加者は自宅で血圧を測り、専用の用紙やアプリに数値を記録します。その結果、1000人以上のデータを2年間追跡したところ、上の血圧と下の血圧が平均3mmHgずつ下がるという変化が見られました。わずか3という数字ですが、医学的には脳卒中や心疾患のリスクを大幅に減らす効果があるといわれています。
さらに注目すべきは、町全体で起きた変化です。能勢町では、後期高齢者の医療費が減少し、要介護認定者の割合も低下しました。これにより、医療と介護の両面で地域の負担が軽くなり、住民の生活の質が向上したと報告されています。
この成果の背景には、「セルフモニタリング効果」があります。自分で血圧を測り、日々の変化を目で確かめることで、自然と塩分を控えたり、運動を増やしたりといった行動改善が起こるのです。能勢町では、町民同士が励まし合いながら記録を続ける“地域の連帯感”も生まれました。
今ではこの取り組みが全国から注目され、厚生労働省や医療研究機関も能勢町のモデルを参考にしています。血圧を「医者に任せるもの」から「自分で守るもの」へ――能勢町の挑戦は、健康長寿の新しい形を示しています。
血圧130のラインを意識する

自治医科大学附属病院の田中亮太教授によると、脳出血で救急搬送された患者の多くが高血圧を抱えていたことが明らかになりました。特に50歳未満の比較的若い世代では、そのうち約8割が治療を受けていなかったといいます。血圧の高さを自覚していながら放置していたケースもありましたが、多くは「自分はまだ大丈夫」と思い込んでいた人たちでした。こうした“自覚のない高血圧”こそが、命を突然奪う大きな要因になっているのです。
脳出血や脳梗塞などの発症は、血管が長年の高圧にさらされて弱くなることが原因です。高血圧は痛みも症状もほとんどなく進行するため、発見が遅れがちです。田中教授は「症状がないから安心ではなく、測らないことが危険」と警鐘を鳴らしています。
さらに、帝京大学の大久保孝義教授の研究チームは、日本全国10の研究データ、約7万人分を解析しました。その結果、血圧が130〜139mmHgの人は、120mmHg未満の人に比べて死亡リスクが明確に高いことが確認されました。これまで「正常高値」とされてきた範囲でも、すでに心血管疾患の危険が増しているというのです。
この発見は、血圧管理の常識を大きく変えるものであり、医療現場では「130の壁」が新たな基準として注目されています。日本高血圧学会も、早めの生活改善や測定習慣の定着を推奨しています。つまり、血圧を“下げる”よりも、“130を超えさせない”という考え方が、これからの健康づくりの基本になりつつあります。
若い世代の生活習慣の乱れやストレス、塩分の多い食生活が、知らないうちに血圧を押し上げています。毎日少しの意識を変えることが、脳と血管を守る最善の一歩です。
朝が勝負!血圧を測るタイミングの新常識

番組で紹介された最新の研究によると、血圧を測る最も効果的なタイミングは「朝」であることが分かっています。朝の血圧は、その人の1日の中で最も高くなりやすく、脳卒中や心筋梗塞などのリスクを最も反映する重要な指標とされています。特に、病院の健康診断などでは正常値だった人が、家庭で測ると高い数値を示すことがあり、これを「仮面高血圧」と呼びます。さらに、朝だけ血圧が上がるタイプの「早朝高血圧」も多く見つかっており、自覚がないまま危険な状態に陥るケースも少なくありません。
理想的な測定タイミングは、起床後1時間以内が基本です。まずトイレを済ませてから、そして朝食をとる前に測ることが推奨されています。なぜなら、排尿や食事によって一時的に血圧が変動するため、安定した状態で測定することが大切だからです。また、測定前には2〜3分間静かに座って落ち着くことで、より正確な数値が得られます。
このように毎朝同じ条件で血圧を測ることで、体の小さな変化にも気づきやすくなります。例えば、数日続けて高めの値が出た場合は、塩分の摂りすぎや睡眠不足、ストレスなど生活の乱れを振り返るきっかけになります。これが「セルフチェックの第一歩」であり、重症化を防ぐ最も確実な方法です。
研究では、朝の血圧が高い人ほど脳卒中の発症率が高いことも確認されています。日本人は特に朝の時間帯に発症リスクが集中する傾向があり、日本高血圧学会も朝の測定を強く推奨しています。血圧計を枕元に置いておくなど、測る環境を整えることで習慣化しやすくなります。
たった1日1回、朝の数十秒で得られるデータが、将来の健康を守る大切なサインになります。毎朝の測定は、病気を防ぐだけでなく、自分の体を知るための“日課”として続ける価値があります。
カリウムを味方に!「カリ活カード」で楽しく減塩
塩分を控えるだけでは、血圧を安定させることはできません。体の中でナトリウムとバランスを取る働きをするカリウムをしっかり摂ることが大切です。カリウムには、余分な塩分(ナトリウム)を尿として体外に排出する作用があり、結果的に血圧を自然に下げる効果が期待できます。
番組で紹介された『カリ活カード』(監修:京都府立大学大学院・奥田奈賀子教授)は、このカリウムの摂取を「見える化」するために作られた画期的なツールです。カードには食材ごとのカリウム量が記されており、1日4枚以上のカードを食事に取り入れることを目標としています。カードを組み合わせることで、自分がどれくらいカリウムを摂れているかがひと目で分かる仕組みです。
番組で紹介された例では、次のような組み合わせが取り上げられました。
| 食材 | 量 | カリウム量 |
|---|---|---|
| ほうれんそう(生) | 40g | 300mg |
| にんじん(生) | 100g | 300mg |
| ブロッコリー(生) | 70g | 300mg |
| トマト(生) | 140g | 300mg |
これらを合わせて食べることで、1日あたり+1200mgのカリウムを無理なく摂取できます。特別な食材を用意しなくても、身近な野菜をバランスよく選ぶことで、自然と塩分を減らし、血圧の安定につながります。
さらに、カリウムは加熱しても壊れにくい栄養素で、スープや煮物などの汁ごと食べる料理に向いています。バナナやキウイ、アボカドなどの果物にも豊富に含まれており、朝食や間食に取り入れるのも効果的です。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、成人男性で1日2500mg、女性で2000mgのカリウム摂取が推奨されています。普段の食事に少しずつ“カリ活”を取り入れることで、血圧の上昇を防ぎ、心臓や腎臓の健康を守ることができます。
カリウムを意識することは、ただの栄養管理ではなく、体の中のバランスを整える習慣。毎日の食卓が、そのまま健康づくりの第一歩になります。
NHKオリジナル「血圧対策エクササイズ」も注目

番組の後半では、血圧を自然に下げる効果が期待できる「トリセツ流エクササイズ」が紹介されました。監修を務めたのは福岡大学病院の医療チームで、誰でも自宅で簡単に続けられる内容です。運動が苦手な人でも無理なく取り組めるように設計されており、朝や夜のすきま時間にできる点が特徴です。
最初の動きは「その場ジョギング」。時間はおよそ50秒です。足を大きく上げる必要はなく、ゆっくりと足踏みをするように行います。腕を軽く振りながら呼吸を整えることで、下半身の血流が改善し、心臓から全身への血の巡りがスムーズになります。特に朝行うと、寝ている間に下がった体温が上がり、血管の動きが活発になる効果もあります。
続いて紹介されたのが「ストレッチ運動」です。ふくらはぎ、そしてもも裏(ハムストリングス)を左右交互に5秒ずつ、2回繰り返すだけのシンプルな動きです。壁や椅子につかまりながら行うと安定しやすく、安全に実践できます。このストレッチは、下半身にたまりやすい血液を上半身へ戻し、動脈の柔軟性を保つのに役立ちます。
運動時間はわずか2~3分ですが、続けることで末梢血管の拡張が促され、血圧が自然に下がりやすくなります。激しい運動ではないため、年齢を問わず誰でも始められるのが大きな魅力です。
研究によると、軽い有酸素運動を毎日短時間でも続けることで、自律神経のバランスが整い、血圧が安定する傾向があることが分かっています。トリセツ流エクササイズはその理論をもとに作られており、「体を整える=血管を整える」という考え方が基本にあります。
体を動かすことは、薬に頼らずに血圧をコントロールする第一歩です。大切なのは、頑張りすぎず、“心地よい疲れ”を感じる程度で毎日続けること。短い時間でも、日々の積み重ねが確かな変化をもたらします。
血圧管理の主役は「自分」
今回の『あしたが変わるトリセツショー』が伝えた最大のメッセージは、血圧ケアは誰にでも「自分でできる」ことばかりだということです。薬や特別な治療だけが頼りではなく、日常の中でできる小さな習慣の積み重ねこそが、脳や血管、そして心臓を守る鍵になります。
例えば、大阪府の能勢町のように、毎日血圧を測り記録するだけでも確実に変化が生まれます。数値を見える形にすることで、自分の体のリズムがわかり、無理なく生活を整えられるようになります。これが「セルフモニタリング」の力です。
食事面では、カリウムを意識した食生活が紹介されました。カリウムを多く含む野菜や果物を毎日少しずつ取り入れることで、塩分のとりすぎを自然に抑え、血管への負担を軽減できます。『カリ活カード』のように楽しみながら続けられる工夫も、健康を長く守るポイントになります。
また、血圧を測るタイミングも重要です。朝の測定を習慣にすることで、「仮面高血圧」や「早朝高血圧」といった隠れたリスクを早期に発見できます。1日たった数分の測定が、重大な病気を未然に防ぐきっかけになります。
さらに、軽い運動も欠かせません。番組で紹介されたトリセツ流エクササイズのように、その場ジョギングやストレッチなどを毎日2〜3分続けるだけで、全身の血流が良くなり、血圧が安定しやすくなります。
こうした行動はどれも難しいものではなく、今日からすぐに始められることばかりです。血圧を測る、食事を見直す、体を動かす――この3つの積み重ねが、「自分で自分の健康を守る」ための基本です。
やがてそれが習慣になったとき、脳や血管、心臓の健康が長く保たれ、心も体もいきいきとした日々を送ることができるでしょう。
まとめ
・血圧は「130」が新たな健康の分かれ目
・朝の測定で隠れ高血圧を早期発見
・カリウムを意識して減塩の効果をアップ
・「測る」「食べる」「動く」で血圧は自然に下がる
・日々の記録が、最高の健康習慣になる
今からでも遅くありません。今日の「測定1回」が、10年後の自分を守ります。
出典:NHK総合『あしたが変わるトリセツショー 脳・血管いきいき!超シンプル「血圧」ケア術』(2025年10月9日放送)
https://www.nhk.jp/p/torisetsu-show/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

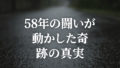
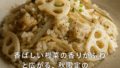
コメント