嗅ぐだけで健康革命!?「鼻」の力を守る全力対策
普段の生活で「味が薄い」「香りを感じにくい」と思ったことはありませんか?それ、実は嗅覚の衰えが始まっているサインかもしれません。嗅覚は単に匂いを楽しむだけの機能ではなく、運動能力や寿命、さらには肥満予防にまで関わることが最新の研究で分かってきました。この記事では、2025年9月11日にNHKで放送された「あしたが変わるトリセツショー」の内容をもとに、嗅覚の持つ驚きのパワーと、健康を守るための最新ケア術を紹介します。
においが運動パフォーマンスを上げる?
高知健康科学大学の研究によると、私たちが普段の生活で当たり前のように感じているしょうゆのにおいには、驚くべき効果があることが分かりました。なんと、その香りを嗅ぐだけで筋肉の動きが活発になり、運動能力が向上することが実験で確認されたのです。
実際の実験では、においを嗅いだ人たちの階段を上るスピードが速くなったり、ジャンプ力が高まるなど、目に見える変化が起こりました。香りという一見「感覚的なもの」が、体の具体的な動作にまで影響を及ぼしているのは驚きです。
研究者によると、この仕組みはにおいが脳を直接刺激することで、体を効率的に動かす神経回路が活性化されるためと考えられています。つまり、においは脳と体をつなぐスイッチのような役割を果たしており、ただ嗅ぐだけでパフォーマンスを引き出す可能性があるのです。
この結果は、スポーツやトレーニングの場面だけでなく、日常生活の動作――たとえば通勤で階段を上るときや、散歩の歩幅を広げるとき――にも影響する可能性があります。私たちが「におい」を意識的に生活に取り入れることで、自然に体を動かしやすくなり、健康維持や体力アップのサポートにつながるかもしれません。
普段なにげなく使っている調味料の香りに、こんなにも大きな力が隠されていたというのは驚きですね。
においで脂肪が燃える!?驚きのダイエット効果
富山大学の恒枝さんが行った実験では、意外な発見がありました。研究対象となったのは空腹状態のマウス。このマウスにエサを与えるのではなく、ただエサのにおいを嗅がせたところ、体の中に蓄えられていた体脂肪が燃焼されることが確認されたのです。
仕組みはこうです。においを感じ取った脳が「これから食事が始まる」と判断し、体はあらかじめエネルギーを準備しようとします。その結果、まずは体に蓄えられた脂肪エネルギーを先に使おうとする反応が起きるのです。においが単なる感覚の刺激にとどまらず、体の代謝活動にまで影響していることが示された点が大きなポイントです。
人間への応用はまだこれからの研究課題ですが、こうした結果は「食べ物の香りをしっかりと感じること」が、私たちの代謝を高める可能性を持っていることを示唆しています。普段の食事の香りを意識的に楽しむことが、健康づくりや体重管理の新しいヒントになるかもしれません。
嗅覚の衰えが命に関わる
アメリカで行われた17万人規模の大規模研究では、においを感じる力を失った人は、正常に嗅覚が保たれている人と比べて、死亡リスクが3倍以上高いことが明らかになりました。これは単なる統計上の偶然ではなく、がん・心不全・糖尿病・脳卒中といった命に関わる病気の多くで、嗅覚の低下が強く関連していることが示されたのです。
さらに、金沢医科大学の三輪さんは「嗅覚が衰えると食べ物の香りを感じられず、食欲が落ちてしまう。その結果、必要な栄養が不足し、体力の低下へとつながる」と指摘しています。嗅覚の衰えは本人が気づかないうちに進むことも多く、生活の質を大きく下げるリスクがあるのです。
つまり、においを感じる力は単なる感覚ではなく、私たちの健康寿命を大きく左右するカギです。日常生活の中で香りを楽しみ、嗅覚を守ることは、長く元気に生きるために欠かせない習慣といえるでしょう。
嗅覚を奪う病気の正体
嗅覚を損なう代表的な原因のひとつが、耳鼻科でも多く報告されている慢性副鼻くう炎です。特にその中の「好酸球性副鼻くう炎」は進行が早く、比較的早い段階からにおいを感じにくくなる傾向があります。さらに重症化しやすいため、放置すると症状が長引き、日常生活に大きな影響を及ぼすことも少なくありません。
もうひとつの大きな原因が感冒後嗅覚障害です。これは風邪やインフルエンザ、さらには新型コロナウイルス感染症の後に起こるもので、においが分からなくなった状態が長く続くケースがあります。中には回復まで数年単位を要する人もいるほどで、自然に治るだろうと放置してしまうのは危険です。
このように嗅覚障害は生活の質を下げるだけでなく、健康そのものにも悪影響を与えかねません。だからこそ、症状が長引くときは早めの受診と適切な治療が、嗅覚を守るための大切なカギとなるのです。
1日2分!鼻を鍛えるセルフケア
ドイツで2009年に提唱された「嗅覚刺激療法」は、専門の医療機関だけでなく、家庭でも取り入れやすいシンプルなトレーニング法として世界的に注目されています。
やり方はとても分かりやすく、レモン・ユーカリ・クローブ・バラといった4種類の香りを用意し、1日2回、それぞれ15秒間ずつ「これは何のにおいか」を意識しながら嗅ぐという方法です。香りをただ感じるのではなく、「今は柑橘系の香りだな」「これはスパイス系の香りだ」と意識することがポイントで、これによって嗅覚神経が刺激され、においを感じる機能回復を助けるとされています。
また、この療法は海外だけでなく日本でも応用が進められており、日常的に親しまれている緑茶や柑橘類、味噌などの香りを使った研究が行われています。私たちにとってなじみのある香りを用いることで、より継続しやすく、生活に取り入れやすいトレーニング法として広がりつつあります。
特別な器具や大きな負担がなくても続けられる点が大きな魅力で、嗅覚を守るセルフケアの新しい習慣として期待されています。
今日からできる鼻の健康習慣
- 食事の際はしっかり香りを感じる
食べ物をおいしく味わうためには、味覚だけでなく香りも大切です。炊きたてのご飯の甘い香り、味噌汁のだしの香り、焼き魚や煮物から立ちのぼる香ばしさ。これらを意識して感じ取ることで、食欲がわき、満足感も高まります。普段の食事を「ただ食べる」のではなく「香りを楽しみながら食べる」と心がけることが、嗅覚を鍛える第一歩になります。季節ごとの花や自然の匂いに意識を向ける
春の桜や草木の香り、夏の青々とした木々や土のにおい、秋の落ち葉や果物の香り、冬の冷たい空気や焚き火の香りなど、四季折々の自然は豊かな香りを届けてくれます。散歩のときに少し立ち止まって深呼吸をし、その季節ならではの匂いを感じることで、気分がリフレッシュされ、心身のバランスも整います。風邪や副鼻くう炎を軽視せず、症状が長引いたら早めに耳鼻科へ
「においがわかりにくい」「鼻づまりが長引く」といった症状を放っておくと、嗅覚が戻りにくくなることがあります。特に副鼻くう炎やアレルギー性鼻炎は嗅覚障害の大きな原因になるため注意が必要です。早期に耳鼻科を受診して適切な治療を受けることが、嗅覚を守るための重要なポイントです。香りのトレーニングを生活に取り入れる
毎日の生活の中でも嗅覚トレーニングは可能です。コーヒーや紅茶を飲むときに香りを楽しむ、アロマや入浴剤の香りを感じる、調理の際にスパイスや調味料の香りを意識するなど、ちょっとした工夫で嗅覚を刺激できます。こうした習慣は嗅覚神経を元気にし、においを感じる力を長く保つことにつながります。嗅覚は使わなければ衰える感覚です。スマホやパソコンに集中しすぎて目や耳ばかりを使っていると、においを感じる時間はどんどん減ってしまいます。だからこそ意識的に「香りを楽しむ時間」を生活の中に取り入れることが、健康寿命を延ばす近道になります。日常に香りを取り戻すことは、心と体を豊かにする大切な習慣なのです。
まとめ
この記事のポイントは以下の通りです。
-
においは運動能力や脂肪燃焼に影響する
-
嗅覚の低下は死亡リスクを3倍に高める
-
慢性副鼻くう炎や感染症後に注意が必要
-
1日2分の嗅覚トレーニングが有効
においを守ることは命を守ること。 日常生活に香りを取り入れ、嗅覚を意識する習慣を始めてみませんか?
さらに詳しい情報やセルフチェックシートはNHKの公式サイトでも公開されています。興味のある方はぜひチェックしてみてください。
👉 NHK あしたが変わるトリセツショー 番組ページ
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

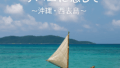
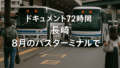
コメント