「あの人に会いたい」久里洋二
あなたが子どもの頃、テレビの前で夢中になって見た『ひょっこりひょうたん島』や『みんなのうた』。その軽快な歌やユーモラスな動きが今でも耳に残っている、という人は少なくないでしょう。その映像世界を形づくった人物のひとりが、アニメーション作家の久里洋二さんです。2025年9月20日に放送されたNHK「映像ファイル あの人に会いたい」では、彼の生涯と作品が丁寧に振り返られました。この記事では、その内容をより詳しく掘り下げ、久里洋二さんが残した軌跡を改めて見直します。
NHK【首都圏情報ネタドリ!】戦後80年「火垂るの墓」を見つめ直す理由とは?高畑勲の空襲体験とドロップ缶の記憶(2025年8月22日)
久里洋二とはどんな人?
まず押さえておきたいのは、久里洋二さんが「日本アニメーションの表現を新しい領域へと広げた人」であることです。
彼はもともと漫画の世界から出発しました。漫画家の横山泰三に師事し、絵の基礎や表現力を学びます。そして、自費出版という形で世に出した『久里洋二漫画集』が高く評価され、文藝春秋漫画賞を受賞。これは彼にとって大きな転機であり、創作活動の幅を広げるきっかけになりました。番組では、この賞をきっかけに彼が「映像」という新しい表現に挑戦していく姿勢が語られていました。
実験的アニメーションの幕開け
1960年、久里洋二さんはアニメーション制作に乗り出します。当時はまだ日本のアニメーションが「商業的」「娯楽的」な色合いを強く持っていた時代でした。そんな中で発表された『人間動物園』は、見る人に強烈な印象を与えました。社会への風刺を込め、独特な動きや音のリズムを取り入れたこの作品は、国内外で11の賞を受賞し、一躍注目を集めます。
番組では、単なる娯楽ではなく「実験的な表現の場」としてアニメーションを位置づけた久里さんの姿勢が紹介されました。彼にとってアニメは、現実を切り取り、ユーモアとアイロニーを交えながら表現する手段だったのです。
『ひょっこりひょうたん島』とNHK作品への貢献
久里洋二さんの名前を広く知らしめたのが、NHKとの仕事です。特に有名なのは、『ひょっこりひょうたん島』のオープニング映像。シンプルでありながらもインパクトのある動きは、子どもたちの心をつかみ、番組を象徴する存在となりました。
また『クラリネットこわしちゃった』などの『みんなのうた』作品も手掛け、子どもから大人まで幅広い層がアニメーションを通じて音楽を楽しめるようにしました。さらに『われわれは宇宙人だ!』のように少し不思議でユーモラスな作品も制作し、日常生活の中で視聴者に想像の世界を届け続けました。
文化番組と映像表現の多様化
番組では、久里さんが関わったNHKの文化番組も多く紹介されました。
「NHKニュース おはよう日本」や「くらしのジャーナル」などでの映像表現は、情報番組であっても印象的なビジュアルを加える役割を果たしていました。日常的に目にするニュースや解説に、彼の手によるアニメーションが加わることで、堅いテーマでもどこか柔らかく親しみやすい空気が生まれていたのです。
また、彼の活動は町永俊雄や黒田信哉といった制作スタッフとの協力のもと進められ、多彩な作品がNHKから発信されました。これらのコラボレーションが、日本のテレビ文化を支えてきたことも番組内で強調されていました。
創作への姿勢と生涯の信念
「アニメーションは死ぬまで作りたいね」
これは久里洋二さんが残した、最も心に響く言葉のひとつです。番組のラストで紹介されたこの言葉からは、彼にとってアニメが単なる仕事ではなく「生きることそのもの」であったことが伝わります。
晩年になっても創作意欲は衰えず、久里実験漫画工房などの活動を通じて若い世代との交流も続けていました。新しい技術が生まれても、自分なりの方法でアニメに向き合い続けた久里さんの姿勢は、多くのクリエイターにとって道しるべとなっています。
まとめ
今回の放送で描かれた久里洋二さんの軌跡から、次のようなポイントが浮かび上がります。
-
漫画とアニメを自在に行き来しながら、新しい表現を切り拓いた先駆者だったこと
-
『人間動物園』や『ひょっこりひょうたん島』、『みんなのうた』など、多彩な作品で幅広い世代に影響を与えたこと
-
「死ぬまで作りたい」と語るほど、一生涯を創作に捧げ続けたこと
久里洋二さんの作品は、単なる過去の映像ではなく、今なお私たちの記憶と感性に働きかけ続けています。アニメーションの奥深さを再発見できる今回の放送は、多くの人に「創作の力」を改めて感じさせてくれるものでした。
――
ソース: NHK 映像ファイル あの人に会いたい
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

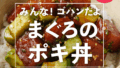

コメント