さよなら銭湯。松戸に刻まれた“60年のぬくもり”を見送る夜
仕事のあと、汗を流しに立ち寄る場所。湯けむりの向こうから聞こえてくる笑い声、脱衣所の番台に座るおばあちゃんの穏やかな顔――そんな光景が、誰の心にも一度は刻まれているのではないでしょうか。かつて日本中にあった銭湯は、地域の人々をつなぐ“心のよりどころ”でした。けれど、令和のいま、その数は激減しています。昭和43年には全国に1万7999軒あった銭湯が、令和6年にはわずか1653軒。半世紀で90%以上が姿を消しました。
千葉県松戸市にある松戸ヘルスランドも、その一軒。2025年10月9日、『ひむバス!』の放送では、この銭湯の“最後の営業日”に密着しました。創業から60年、地域の人々に愛されてきた湯屋が幕を下ろす瞬間――その夜、松戸の街は静かな感謝と別れの涙に包まれました。
松戸ヘルスランド、60年の歴史と“家族のような場所”
松戸ヘルスランドの創業は昭和40年。初代店主は高橋由利子さんの祖母でした。当時の松戸は、東京への通勤圏として住宅地が急速に広がり、銭湯は地域コミュニティの中心にありました。地下からくみ上げた天然の地下水を沸かした湯はやわらかく、肌あたりがよいと評判。タイル張りの浴場には富士山の絵が描かれ、脱衣所には木のベンチ。訪れる人の顔は、皆どこかリラックスしていました。
高橋さんはその銭湯を三代目として引き継ぎ、地域の高齢者や子どもたちが安心して通える場所を守ってきました。特に冬場は冷えた体を温めに来る常連が絶えず、毎日顔を合わせるうちに自然とあいさつが生まれる――まさに「地域の家族」が集う場所でした。
しかし、2024年春に異変が起こります。浴場の配管が老朽化し、漏水が発生。修理には数百万円の費用がかかることがわかり、高橋さんは苦渋の決断を下します。「お客さんの笑顔を見送るために、最後の日をきちんと迎えたい」――その思いが、今回の『ひむバス!』への依頼につながりました。
“最後の送迎”に込めた感謝の気持ち
番組では、日村勇紀と宮崎あずさが千葉・松戸市を訪れ、常連客をひむバスで銭湯へ送り届けました。1駅離れた自宅から毎日通っていた大川洋治さんは、52年間通い続けた超常連。彼にとって銭湯は“もう一つの家”であり、仲間と過ごす憩いの場でした。「湯に入れば、嫌なことも忘れられる」と笑うその表情には、時代を超えて銭湯が人々を癒やしてきた力がにじんでいました。
また、小栗さんファミリーも登場。夫婦と5歳の一歩希(いぶき)くんは、ここ5〜6年ずっと松戸ヘルスランドに通い続けてきました。子どもの成長を見守るように、お客さんたちが声をかけてくれる。「背、伸びたね」「小学校どこ行くの?」そんなやりとりが、地域の優しい時間をつくっていました。銭湯があることで、世代を超えた“見守り”の文化が自然と生まれていたのです。
最後の夜、412人が湯に集う
閉店当日、朝から店の前には長い行列ができました。「もう一度入りたい」「最後にありがとうを言いたい」と、常連も初めての人も入り混じって、開店と同時に浴場は満員。タオル片手に笑い合う人、浴槽の縁に腰かけて昔話をする人、別れを惜しみながらも笑顔を見せる人。
この日、訪れた入浴客は過去最多の412人。高橋さんは休む間もなく番台に立ち、常連一人ひとりに感謝の言葉を伝えました。「今日で最後なのが信じられないね」「おばちゃん、ありがとう」――そんな声があふれ、店内には笑いと涙が混じる不思議なあたたかさが広がっていました。
夜10時半、「本日の営業は終了いたしました」の札が掲げられると、外にはまだ多くの人が残っていました。閉まる扉の前で、最後の記念撮影をする家族、名残惜しそうに煙突を見上げる常連たち。湯気のように、時代の記憶が空へと溶けていく――そんな一夜でした。
銭湯が消えるということ。それは、地域の声が小さくなるということ
全国の銭湯が減っている背景には、燃料費の高騰や設備の老朽化、人手不足といった経営的な課題があります。けれど、それ以上に深刻なのは「人が集まる場所」が失われていることです。
かつて銭湯は、家庭に風呂がなかった時代の“生活インフラ”であると同時に、地域の情報交換の場でもありました。仕事帰りの会社員がニュースを語り、主婦たちがレシピを交換し、子どもたちが湯上がりのコーヒー牛乳を分け合う。そんな日常の中で、人と人との“関係資本”が育まれてきました。
松戸市立博物館にも、昭和の松戸を象徴する銭湯文化の写真や資料が展示されています。松戸ヘルスランドは、まさにその時代を生きた“最後の記録”でもありました。
それでも、人の心に残る“湯のぬくもり”
閉店翌朝、松戸ヘルスランドの入り口には花束と「長い間ありがとうございました」と書かれた手紙が置かれていました。夜の灯が消えた店先に残るのは、人々の記憶です。湯の温度は下がっても、そこに通った人々の心の中では、まだ“あの湯気”が立ち上っています。
近年、全国では銭湯の跡地を活用した地域再生の動きも増えています。古い浴場をカフェやギャラリーに改装したり、子ども食堂や地域サロンとして再生する事例もあります。松戸でも、こうした“地域の拠点づくり”に関心を持つ若者たちが動き始めています。銭湯の閉店は、終わりではなく“次の地域文化”への入口かもしれません。
まとめ:地域の灯を未来につなぐために
この記事のポイントは以下の3つです。
・昭和40年創業、松戸ヘルスランドが配管故障をきっかけに閉店。60年にわたって地域をつないだ“湯屋文化”が幕を閉じた。
・『ひむバス!』で日村勇紀と宮崎あずさが常連客を送迎し、最終日の感動を共有。大川洋治さん、小栗さんファミリーら常連の姿が印象的だった。
・銭湯は地域のつながりを育む場所であり、閉店は“地域の声の喪失”を意味する。だが、人の記憶と文化は新しい形で受け継がれていく。
昭和の湯気が消えても、そのぬくもりは人々の中に残り続けます。松戸の街角を歩くと、どこかにまだ石けんの香りが漂っているような気がする――銭湯がくれたのは、ただの温かいお湯ではなく、“人の心の温度”だったのです。
出典:NHK総合『ひむバス!』(2025年10月9日放送)
https://www.nhk.jp/p/ts/KWJJ77RLV6/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

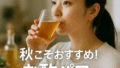
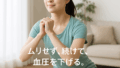
コメント