メジャーリーガーの種の秘密・寿司屋の湯飲みの真相・タイムカプセルの歴史
2025年4月18日放送のNHK総合『チコちゃんに叱られる!』では、誰もが一度は疑問に思ったことのある3つのテーマが紹介されました。「メジャーリーガーがひまわりの種を食べる理由」「おすし屋さんの湯飲みが大きい理由」「タイムカプセルを埋めるようになった理由」です。番組で明かされた答えや専門家の解説をもとに、さらに詳しく解説します。
メジャーリーガーがひまわりの種を食べる理由は「究極の暇つぶしアイテムだから」

番組では冒頭の出題として「メジャーリーガーがひまわりの種を食べるのはなぜ?」という問いが投げかけられました。その答えは意外にも、「究極の暇つぶしアイテムだから」。つまり、野球という競技の性質に深く関係しているということです。
・野球は他のスポーツに比べてプレーしていない時間が圧倒的に長い競技です。攻守の切り替え、イニングの間、打席を待つ間など、選手たちはベンチで多くの時間を過ごすことになります。その中で、口を動かして殻を割るという単調な動作がリズムを生み出し、精神を安定させる効果をもたらしています。
・ひまわりの種を食べることは、ただの癖ではなく、集中力を維持するための行動とも言えます。実際、日本のプロ野球でもガムを噛む選手が多く見られますが、それと同じように、ひまわりの種も「ベンチワーク」の一部として定着しています。
・解説を担当した早稲田大学・川島浩平教授は、野球選手にとっての“暇つぶし”が、同時に“パフォーマンス管理”にもなっていることを指摘しました。何もしない時間をどう使うかは、選手としての過ごし方に直結します。その点でひまわりの種は、まさに機能的なアイテムなのです。
・番組では、大谷翔平選手やミゲル・カブレラ選手がベンチでひまわりの種を食べている実際の様子が紹介され、今やメジャーリーガーにとっては欠かせない存在になっていることが強調されていました。とくに大谷選手は試合前のルーティンの一つとして、種を食べる姿が多く目撃されています。
・さらに、ひまわりの種はたばこやスナックの代替品としても健康的。ビタミンやミネラルも豊富で、単なる間食以上の価値があることも見逃せません。塩分や味の種類も多く、自分の好みに合わせて選べるため、ベンチの中で共有されているケースも多いそうです。
このように、メジャーリーガーがひまわりの種を食べる背景には、スポーツとしての戦略的な側面と、人間的な習慣の融合が見てとれます。ただの「食べる」行動ではなく、試合を乗り切るための「仕組み」になっているのです。
おすし屋さんの湯飲みが大きい理由は「おかわりをさせないため」

今回の放送で紹介されたテーマのひとつ、「おすし屋さんの湯飲みが大きいのはなぜ?」という疑問に対し、チコちゃんが出した答えは「お茶のおかわりをさせないため」でした。一見サービスの一環のように見える大きな湯飲みに、実は職人たちの知恵と工夫が隠されていたのです。
・この理由について解説したのは、清水すしミュージアムの名誉館長・日比野光敏さんです。湯飲みのルーツは、1820年代の江戸時代に屋台で提供されていた寿司文化にあるといいます。当時の寿司は現在よりもかなり大きく、1貫が今の3倍ほどのサイズ。ネタには脂がしっかりとのっており、次のネタに移る前に口の中をリセットする必要がありました。
・そのために活躍するのが、カテキンを豊富に含んだ熱いお茶です。脂をすっきりと洗い流し、次のネタの味をきちんと楽しむために、寿司とお茶はセットとして定着していきました。
・しかし、湯飲みが小さいと、すぐにお茶が冷めてしまい、さらにおかわりの回数が増えて店側の手間が増えることになります。そこで工夫されたのが、分厚くて大きな湯飲みです。これなら熱を逃がしにくく、1回の提供で多くのお茶を楽しめるため、職人の手を煩わせることなく済みます。
・また、ぬるくなったお茶を何杯も飲まれると、満腹になって寿司の注文量が減るという問題もあったそうです。湯飲みを大きくすることで、温かい状態を長持ちさせ、一杯で満足してもらえるようにする。これも寿司職人の仕事の効率と味へのこだわりを守るための知恵です。
・さらに番組では、東京・門前仲町の寿司屋が紹介され、湯飲みに描かれた寿司ネタの名前や魚の漢字が映し出されました。これは、客が寿司を待つ間の会話のきっかけや学びの要素としても機能しており、湯飲みが“道具”以上の役割を果たしていることが伝えられました。
このように、大きな湯飲みには「おかわりさせない」というシンプルな目的だけでなく、寿司文化を支える多くの理由と工夫が詰まっていたのです。今後お寿司屋さんに行ったときには、湯飲みの重みと熱さを感じながら、その意味を味わってみると、より深く日本の食文化を楽しめるはずです。
タイムカプセルを埋めるようになった理由

番組の最後に取り上げられたテーマは、「タイムカプセルを埋めるようになった理由」でした。私たちにとっては学校行事などで馴染みのあるタイムカプセルですが、そのはじまりには驚きの歴史がありました。番組では、未来の人に向けて“いま”を伝える手段として、どのように誕生し、広まっていったのかが紹介されました。
・そもそもの出発点は、1939年のニューヨーク万博。アメリカのウェスティングハウス社が、5000年後に開けることを目的として、1つのカプセルを地中深くに埋めたのが、現代的なタイムカプセルの原点です。中に収められていたのは、新聞、電化製品の部品、衣類、化粧品など、当時の暮らしを象徴する品々。このカプセルは、人類の文明を未来に伝える“文化のメッセージボトル”とも言えるものでした。
・この挑戦的な取り組みが世界中で注目され、日本でも影響を受けた形で、1970年の大阪万博で話題のプロジェクトが実現します。それが、松下電器(現パナソニック)と毎日新聞が共同で手がけた「タイム・カプセルEXPO’70」です。大阪城公園に埋められた2つのカプセルのうち、1つは西暦6970年に開けられる予定。もう1つは、100年ごとに開封・記録更新を繰り返していく設計です。中には、当時の生活用品から最先端の技術資料、文化を象徴するものまで2098点が収納されています。
・番組では、この大阪万博の記録映像や、実際のカプセルの外観、埋設の様子が紹介されました。未来の人がカプセルを開けたときに「これが1970年の人々の暮らしだったのか」と思えるよう、保存性や耐久性にも徹底した設計が施されていたことが分かります。
・この一連の出来事をきっかけに、タイムカプセルは学校の卒業式や地域行事の定番になりました。卒業生が未来の自分に向けて手紙を書いたり、クラスの集合写真やその年の新聞、好きな物の記録を残したりすることで、成長や時代の移り変わりを実感する手段になっています。
・また、番組では、過去に埋められたタイムカプセルが開封された様子も紹介され、思い出がよみがえる瞬間の映像が印象的に使われていました。当時の気持ちや空気を詰め込んだ記録は、時間を超えて人の心を動かす力があることが伝えられました。
こうして見ると、タイムカプセルは単なる遊びやイベントではなく、未来への希望と、今を大切にする気持ちが詰まった「時間のメッセージ」だということが分かります。
過去から現在、そして未来へとつながるこの文化は、これからも大切に受け継がれていくはずです。
まとめ
今回の『チコちゃんに叱られる!』では、当たり前のように見ている物事の裏にある深い理由を、専門家の解説とともに楽しく知ることができました。
・メジャーリーガーが種を食べるのは、集中力を保つための暇つぶし
・寿司屋の湯飲みは、おかわりを減らすための知恵と味の工夫
・タイムカプセルは未来へ「いま」を残すロマンの詰まった文化
どれも「なるほど!」と納得できるテーマばかりでした。次回も身近な“なぜ?”に出会えるのが楽しみです。
※放送内容と一部異なる場合があります。ご了承ください。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

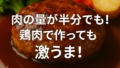
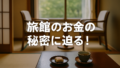
コメント