毒のトゲと美しさの秘密!ミノカサゴ徹底特集|2025年4月4日放送回
2025年4月4日(金)19時25分から放送されるNHK Eテレの『ギョギョッとサカナ★スター』では、「ミノカサゴ」を特集します。赤と白のしま模様が印象的で、長いヒレをひらひらと動かして泳ぐ姿が美しいこの魚。しかし、見た目とは裏腹に毒のあるトゲを持つ危険な魚としても知られています。今回はそんなミノカサゴについて、さかなクンとミノカサゴ佳乃さん(木村佳乃さん)が楽しく、わかりやすく解説します。
ミノカサゴってどんな魚?
ミノカサゴは、インド洋から西太平洋にかけて広く分布する魚で、日本では主に本州の南側から沖縄にかけての暖かい海で見られます。浅い岩場やサンゴ礁のまわりにすんでいて、体長はだいたい25〜30cmくらいまで育ちます。見た目はとてもきれいで、赤と白のしま模様と、大きく広がるヒレが目立ちます。このヒレはまるで扇のように広がり、水の中をゆったりと泳ぐ姿はとても優雅で、水族館でも人気者です。
ですが、この美しい見た目には危険な秘密がかくれています。実はミノカサゴのヒレの中には毒のあるトゲがいくつもあるのです。
-
背ビレには13本の毒トゲがあります。このトゲが一番目立っていて長く、近づくとピンと立ち上がるように広がります。
-
おしりのヒレ(臀ビレ)には3本の毒トゲがあり、水の流れでバランスを取るときなどにも使われます。
-
おなかの下にある腹ビレにも左右1本ずつ、合計2本の毒トゲがついています。
これらのトゲは見た目には分かりづらいこともありますが、さわってしまうと強い痛みと腫れを引き起こします。毒の種類はたんぱく質性で、体の中に入ると吐き気・めまい・呼吸が苦しくなるなどの症状が出ることもあります。特に背ビレの毒トゲは鋭く、ちょっと触れただけでも刺さることがあるので、海で見かけたときは絶対に近づかないことが大切です。
ミノカサゴは夜になると活動的になり、小さな魚やエビなどをそっと近づいて食べます。このときもヒレを広げて相手を囲むようにして動かず、突然吸い込むようにして捕まえます。その姿は静かですが、実はとてもすばやくて上手なハンターです。
見た目はきれいだけど、油断するととても危険な魚。それがミノカサゴのほんとうの姿です。観察するときも、調理するときも、毒のトゲに注意して、正しい知識をもって向き合うことが大切です。
どうして派手な体なのに狙われないの?

ミノカサゴの赤と白の目立つしま模様は、とてもきれいで目を引きますが、実はただの飾りではありません。この模様は「警告色(けいこくしょく)」と呼ばれていて、「自分には毒があるから、近づくと危ないよ」というサインなのです。
自然の中では、このような派手な模様を持つ生き物はほかにもいます。
-
ハチやスズメバチも黒と黄色の警告色を持っていて、敵に「刺すぞ」と知らせています。
-
カエルやトカゲにも毒をもっている種類は、体がカラフルなことが多いです。
ミノカサゴも同じで、その目立つ見た目で相手に「自分は簡単には食べられないぞ」と伝えているのです。そのため、天敵はミノカサゴを見ても「これは危ないかも」と感じて、わざわざ襲おうとしません。
さらに、ミノカサゴは岩場やサンゴのすき間にじっとしていることが多いです。このとき、派手な模様が逆に岩やサンゴの影とかさなって見えにくくなることもあります。
-
細いしま模様が、光の入り方や岩の形にまぎれてカモフラージュのような働きをする
-
動かずにじっとしていることで、敵に気づかれにくくなる
このように、派手な体は目立つだけではなく、敵に「毒があるぞ」と伝えるためのサインであり、隠れるときには自然に溶け込む工夫にもなっているのです。きれいな見た目の中に、しっかりとした「生き残るための知恵」がつまっている魚です。
小魚が気づかないのはなぜ?

ミノカサゴはとてもゆっくりと泳ぐ魚です。胸ビレを大きく広げてフワフワと動く姿は、まるで泳ぎの下手な魚のように見えることもあります。でもこれは、わざとそうしているのです。動きがゆっくりで目立たないように見せかけることで、獲物に警戒心を持たせないようにしています。
-
ミノカサゴの動きは「のろのろ」ではなく「静かに近づくための作戦」
-
胸ビレを広げることで、逃げ道をふさぎながら獲物を追い込む
-
最後の瞬間に一気に口を開いて、吸い込むようにして獲物をとらえる
このとき、ヒレがまるで壁のようになり、小魚は行き場を失ってしまいます。そして近くに来たミノカサゴに気づいたときにはもう遅く、すでに口の中に吸い込まれてしまうのです。
ミノカサゴの口はとても大きくて、前にパッと開いて一瞬で水ごと獲物を飲みこみます。しかもその動きはほんの一瞬なので、獲物が逃げるスキもありません。
このように、「ゆっくり動く」「胸ビレで囲む」「吸い込むように食べる」という三つのテクニックを使って、小魚をだまして捕まえるのが、ミノカサゴのすごいところです。見た目は優雅でのんびりしているように見えても、その裏ではしっかりとした「ハンターの技」を使っているのです。だからこそ、小魚たちはミノカサゴが危ない存在だと気づく前に捕まってしまうのです。
もし刺されてしまったらどうするの?

ミノカサゴに刺されると、とても強い痛みが走り、びっくりしてしまうことがあります。でも、あわてずにすぐに応急処置をすることが大事です。毒はたんぱく質でできているので、熱でこわすことができます。だから、対応が早ければ早いほど、症状を軽くすることができます。
まず最初にするべきことは、トゲが皮ふに残っているかどうかを確認することです。
-
トゲが見えている場合は、ピンセットなどでゆっくりと取り除くようにします。手で無理に引っぱるのではなく、清潔な道具を使うことが大切です。
-
トゲを取り除いたあとは、傷口をよく洗って清潔に保ちます。海水や泥がついたままだと、あとで腫れたり化膿したりすることもあります。
次に行うのが、お湯につける処置です。
-
40〜45℃くらいの熱めのお湯に患部をひたすことで、毒のたんぱく質がこわれて痛みがやわらぎます。
-
このとき、60〜90分くらいを目安に、ゆっくり温めます。ただし、やけどしないように温度には注意が必要です。
-
お湯が冷めたら、あたため直して続けるのが効果的です。
それでも痛みが強かったり、腫れがひどい場合は、すぐに病院で診てもらうことが必要です。人によってはアレルギー反応を起こしてしまうこともあるので、「少しガマンすればいいや」と思わず、様子を見ながらきちんと医療機関で処置を受けるようにしましょう。
-
特に、刺された場所が指や関節、顔まわりなど重要な部分だった場合は要注意
-
呼吸が苦しくなる、めまいがする、気分が悪いなどの全身症状が出たときも、すぐに救急へ行く必要があります
ミノカサゴは見た目がきれいでゆったりしているので油断してしまいがちですが、背中やおなかのトゲには本当に強い毒があります。万が一刺されてしまったときのために、「トゲを取る」「お湯につける」「必要なら病院へ行く」という手順を覚えておくと安心です。自然の中で遊ぶときには、きれいな魚ほど注意が必要なこともあるのです。
毒のトゲには秘密がある?

ミノカサゴの体にある毒のトゲには、ただ「刺す」だけではないさまざまな秘密がかくれています。まず、このトゲは外敵に近づかれたとき、自分を守るためにとても重要です。ヒレを大きく広げて「これ以上近づくな」とアピールする姿は、まるで武器をかまえているようにも見えます。
-
毒トゲは攻撃ではなく防御のために使われることが多いです。むやみに他の魚を刺すわけではなく、危険を感じたときにだけ働きます。
-
ヒレを大きく広げることで体が大きく見え、相手にプレッシャーをかける効果があります。これは自分を強く見せる「けん制」の行動です。
さらに、トゲのついたヒレの間にはうすい膜のような部分があり、これが光を反射したり、水の中で音を立てたりすることもあります。敵に対して「自分はただ者じゃないぞ」と伝えるための、視覚や聴覚に働きかける方法と考えられています。
-
光を反射させることで、キラッと光るヒレはより目立つようになります
-
ヒレを動かす音や振動で、相手に警戒心を与える効果もあると言われています
このように、ミノカサゴの毒トゲはただ痛いだけのトゲではありません。見た目を強調し、行動で敵を追いはらう「警告装置」としての役割を持っています。実際にミノカサゴに近づくと、胸ビレや背ビレをいっぱいに広げて、敵がそれ以上入ってこないようにする様子が見られます。
きれいでおとなしく見えるミノカサゴの裏側には、しっかりとした防御の仕組みがあるのです。それをうまく使って、他の魚たちに「近づくと痛い目にあうよ」と伝えているのです。自然界では、生き残るための知恵がいろんな形で使われていることがよくわかります。
世界での困ったミノカサゴ問題とは?

ミノカサゴはもともとインド洋や西太平洋のあたたかい海にすんでいた魚ですが、人の手によって違う地域に広がってしまい、外来種として問題になっています。とくに大西洋やカリブ海では深刻で、生きものたちのバランスが大きくくずれてきています。
なぜミノカサゴが困った存在になっているのでしょうか?その理由はとてもはっきりしています。
-
もともとの天敵がいないため、ミノカサゴの数がどんどん増えている
-
小魚やエビなどをたくさん食べてしまい、在来の魚が減ってしまっている
-
食べられる側の魚が減ることで、サンゴ礁を守るバランスがくずれてしまう
サンゴ礁の近くには、サンゴをきれいにする魚たちがすんでいます。でも、ミノカサゴにその魚たちが食べられてしまうと、サンゴにゴミやコケがたまって、サンゴが弱ってしまうのです。その結果、サンゴ礁全体がこわれてしまうという深刻な問題が起きているのです。
ミノカサゴはとても強いハンターなので、現地の魚たちは逃げきれません。さらに、毒のトゲがあるため、ほかの生き物からもあまり攻撃されず、安心して増えていってしまいます。人間にとっても、「刺されると危ない魚」として注意が必要です。
この問題をどうにかしようと、世界ではいろいろな取り組みが行われています。
-
「ミノカサゴ駆除キャンペーン」で、ダイバーたちが協力してミノカサゴを取りのぞく活動をしている
-
「ミノカサゴ料理コンテスト」などで食材として利用し、たくさん食べて減らそうという動きもある
-
学校や水族館で「外来種について知ろう」という教育が進められている
見た目がきれいなミノカサゴですが、自然のバランスをこわしてしまう力を持っているということが、世界中で知られるようになっています。ただ「きれいだから」「人気があるから」だけではすまされない問題です。外来種とは何か、生きものの住む場所を守るとはどういうことか、ミノカサゴの問題から学べることはたくさんあります。
ミノカサゴ佳乃さんも登場!
今回の放送では、番組おなじみのキャラクター「ミノカサゴ佳乃さん(木村佳乃さん)」も登場します。さかなクンと一緒に、笑いあり学びありの内容でミノカサゴの魅力と怖さの両方を楽しく紹介してくれる予定です。さらに、番組内ではミノカサゴの絶品料理も登場する予定です。毒トゲさえ取り除けば、白身であっさりとした味わいが楽しめる魚でもあります。
ミノカサゴは身が水っぽいので、生食で食べるよりも火を入れて余分な水分を抜いてからの方が美味しく、特におすすめなのは塩焼きである。 他にも煮付けや唐揚げなどにしても美味しく食べることができる。 アラからも出汁が出るので、味噌汁やアラ汁にしても良い。 ミノカサゴをさばく際は各ヒレの毒に細心の注意が必要である。ミノカサゴ(カサゴ目 フサカサゴ科)|釣魚図鑑 – 釣割
放送が楽しみ!
4月4日放送の『ギョギョッとサカナ★スター』では、子どもから大人まで楽しめる内容でミノカサゴの不思議がたっぷり紹介される予定です。見た目の美しさに隠された驚きの事実や、世界の海で起きている深刻な問題まで、たくさんの発見がある回になりそうです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


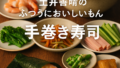
コメント