米中対立 日本の“勝機”はどこに?
2025年5月18日(日)21:00から放送されるNHKスペシャルでは、緊張が続く米中対立の現状とその影響を受ける日本について特集が組まれます。番組では関税問題をはじめとする経済的駆け引きがどのように展開され、日本企業がそこからどんなチャンスを見出しているのかが紹介されます。投資コンサルタントの齋藤ジン氏を迎え、スタジオから生放送で届けられる注目の内容です。
放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。
米中貿易対立に巻き込まれる日本の現実と対応策

アメリカと中国の対立は年々深刻さを増しており、特に経済・貿易分野での緊張が日本に大きな影響を与えています。トランプ前大統領による関税政策はその象徴で、日本から輸出される製品への追加課税や輸入コストの上昇が、日本経済に波紋を広げました。とくに鉄鋼や自動車部品、精密機器などの分野では打撃が大きく、企業の収益悪化や株価の不安定化を引き起こしました。
こうした中、アメリカは中国との経済関係を徐々に切り離す「デカップリング」政策を加速させています。これにより、中国に依存してきたサプライチェーンの見直しが急務となり、日本もその影響を強く受けています。
-
中国市場に依存していた日系企業は、取引の縮小や再編を迫られている
-
部品供給に遅れが出ることで製造ラインが停止した例もある
-
貿易摩擦の激化により、為替相場や物流コストの変動も激しくなっている
しかし、すべてがマイナスではありません。現在の混乱は、日本にとって新たなチャンスを生む場面にもなっています。日本企業の多くは、この状況を単なる危機としてではなく、“商機”として捉える柔軟な姿勢を見せ始めています。
例えば、アメリカが中国からの輸入品を制限する中で、信頼できる第三国のパートナーとして日本が注目されるようになっています。とくに精密機器や半導体関連の部品では、日本の高品質・高信頼性が評価され、代替供給先としての価値が高まっています。
-
アメリカ市場で中国製の空白を埋める形で、日本企業が受注を拡大
-
ベトナムやタイなど、アセアン諸国と連携しながら新たな拠点を開拓
-
サプライチェーンのリスク分散を図る戦略が進行中
また、政府も企業の動きを後押ししており、国内回帰や東南アジア進出への補助金制度や税制支援を拡充しています。これにより、今まで以上に海外展開と国内技術の強化を両立させる動きが活発になっています。
現在の日本は、米中の間に立たされているだけでなく、国際秩序の変化の中で自らの役割を模索し、新たなポジションを築こうとしている最中です。番組では、こうした企業や政府の取り組みがどのように現実の中で形になっているのかを、事実に基づき丁寧に伝える予定です。
日本企業のしたたかな商機への対応

米中対立が激しくなる中、日本企業は単に情勢に翻弄されるのではなく、自らの立ち位置を見極めて前向きに動いていることが注目されています。番組では、今の時代に対応しようとする企業の動きが、具体的な事例とともに紹介される予定です。
たとえば、これまで依存度の高かった中国市場から距離を取り、アセアン諸国や欧州市場に新たな活路を見出す動きが進んでいます。とくにベトナム、インドネシア、タイなどの地域では、現地に製造拠点を設けたり、営業網を拡大したりと、柔軟な戦略が取られています。
-
アセアン市場は経済成長が続いており、消費市場としての魅力も大きい
-
ヨーロッパでは環境技術や高品質製品へのニーズが高く、日本の得意分野と合致している
また、日米間の技術協力も大きな柱となっています。アメリカの規制強化によって中国企業が排除される場面では、日本の製品や技術が信頼できる代替手段として選ばれることが増えています。特に、電気自動車、再生可能エネルギー、人工知能などの分野では、共同開発や部品供給の面で日本企業の存在感が強まっています。
-
日米共同プロジェクトに参加する日本の中小企業も増加中
-
米国大手企業との提携によって、グローバル展開が進む企業もある
こうした変化に対応するために、多くの企業はサプライチェーンの再構築にも力を入れています。かつては一極集中していた調達先や生産地を分散させ、リスクに強い体制づくりを進めています。
-
国内回帰で安定供給を確保しつつ、東南アジアとのハイブリッド体制を構築
-
物流の混乱に備えた在庫の積み増しや、新ルートの確保も進行中
さらに、半導体や次世代技術の分野では、日本独自の強みを活かした研究・開発が本格化しています。ラピダスのような新たな取り組みも象徴的ですが、それだけでなく、長年にわたり蓄積された技術や人材を活かし、世界的な技術競争の中での存在感を高める努力が続けられています。
-
素材、製造装置、検査技術などで日本が世界をリードする分野が多い
-
大学や研究機関との連携で次世代人材の育成も加速中
これら一連の動きからは、困難な国際状況にもかかわらず、日本企業が前向きに“攻め”の姿勢でチャンスをつかもうとしている姿が感じられます。番組では、その裏側にある企業の戦略や現場の声が紹介されることで、視聴者にとっても今後の動き方を考えるヒントとなるでしょう。
半導体をめぐる激化する技術競争と日本の立場

米中対立が続く中でも、特に注目されているのが半導体産業をめぐる争いです。アメリカは中国に対し、最先端の半導体技術や製造装置の輸出を厳しく規制する姿勢を強めており、この分野の競争はますます激しくなっています。主導権を握ろうとする両国の思惑がぶつかるなか、日本はこの流れにどう関わっているのか、番組ではその実態が丁寧に掘り下げられる予定です。
特に注目されるのは、材料や製造装置といった分野での日本の存在感の大きさです。半導体製造にはナノレベルの精度が必要とされますが、日本企業はそこに欠かせない高純度の材料や、超精密な製造機器を提供することで、世界のサプライチェーンに深く組み込まれています。
-
日本はシリコンウェーハやレジスト(感光材)、研磨材などで世界シェアの多くを占めている
-
製造装置の分野でも、露光装置や検査装置で信頼性の高い製品が評価されている
また、日本の強みは技術だけでなく、製品の安定供給と品質管理の高さにもあります。特に、自動車や産業機器向けの半導体では、その信頼性の高さが際立っており、故障やトラブルを避けたい業界からのニーズは非常に高くなっています。
-
自動車用半導体では「安全性」が最重視されるため、日本製は重要な選択肢
-
生産現場では、厳格な品質基準を守る日本のものづくり力が活かされている
さらに、国内での半導体開発を支えるため、政府も支援を本格化しています。たとえば、最先端半導体の国産化を目指す「ラピダス」には、多額の補助金が投入されており、国内に生産拠点を持つことで供給の安定性も強化されようとしています。
-
経済産業省は2030年までに2ナノメートルの量産を目指すと発表
-
先端技術における自立を目指す国の姿勢が明確になってきている
その一方で、日本は単独で立ち向かうのではなく、アメリカとの連携によって次世代技術の開発を進めています。共同研究や技術交換を通じて、量子コンピューティングやAI向けの特殊半導体など、新しい分野への取り組みも始まっています。
-
日米共同で半導体研究センターの設立が進行中
-
研究開発分野での人的交流や知見共有が加速している
こうした背景から、日本は単なる技術供給国ではなく、世界の半導体供給網を支える中核的な存在であると考えられています。番組では、このような日本の立場や取り組みが、実例を交えて紹介される予定であり、視聴者にとっても現代の技術競争の最前線を知る貴重な機会となるでしょう。
投資コンサルタント齋藤ジン氏が読み解く“勝機”
今回の特集の案内役を務めるのは、投資コンサルタントの齋藤ジン氏です。トランプ政権の経済ブレーンへの取材経験もあり、現場でのリアルな情報をもとに、日本がこの困難な国際状況の中でいかに立ち回るべきかを解説します。
齋藤氏の視点からは、米中それぞれとの適切な距離の取り方や、日本独自の強みを活かした戦略的な動き方が語られることが期待されます。経済の専門家としての知見だけでなく、企業活動にも通じたリアリティのある分析が注目されます。
成長のチャンスをつかむために
現在のような国際的に不安定な時代では、ただ守るだけでは成長につながりません。不確実性の中にこそチャンスが潜んでいるという考えのもと、日本企業は柔軟かつ冷静に対応を進めています。番組ではその姿を丁寧に紹介し、視聴者にとっても世界の動きと自分たちの生活のつながりを実感できる内容になるはずです。
放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。放送内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

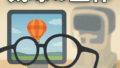

コメント