「なぜクマが町で“暴走”? 独自調査で迫る実態とは」
最近、「庭でクマを見た」「通学途中に子どもが遭遇した」というニュースを耳にする機会が急増しています。以前なら山奥にひっそりと暮らしていたはずのクマが、なぜ今、住宅地や商店街に姿を現すようになっているのでしょうか。もしかすると、あなたの暮らす町でも同じような危険が近づいているのかもしれません。今回のNHK総合『クローズアップ現代』(2025年9月22日放送)は、その背景に迫るため、研究者や自治体と共に独自の調査を実施。その結果から見えてきたのは、クマと人間の暮らしが重なり合う新たな現実でした。
独自調査で判明した“クマの行動変化”
NHKの取材チームは東京農業大学や東京農工大学の研究者と連携し、クマの生態を追跡。捕獲したツキノワグマにGPS発信機を装着し、2時間ごとに送られる位置情報を解析しました。その結果、クマは季節ごとに行動範囲を変えており、特に夏から秋にかけては人里に近づく動きが顕著であることが分かりました。さらに、同じ個体の昨年と今年の行動を比較すると、今年はより市街地へと接近している事実も確認されています。
その理由の一つは、人間がかつて植えたスモモや梨、栗の木。今は放置され、果実が大量に実ったまま残っており、クマにとって格好の餌場となっていました。野山に餌が少なくなる季節、彼らは自然に導かれるように人間の生活圏へ足を踏み入れてしまうのです。
人を襲う被害が“日常化”
これまでに秋田大学医学部附属病院で100人以上の被害者を治療してきた佐藤隆一医師は、患者の多くが顔や頭に深刻な外傷を負っていると指摘。今年は特に「山へ入った人が襲われる」のではなく、「ゴミ出し」「庭の手入れ」「畑作業」といった日常生活の中で襲われるケースが増えています。こうした変化は、クマが人間の暮らしの場に積極的に入り込んでいることを物語っています。
出会わないために、出会ってしまったら
番組には森林総合研究所の大西尚樹さんが出演し、クマと出会わないための具体策を解説しました。
まず大切なのは、山や里山を歩くときに音を出すことです。鈴やラジオを持ち歩き、人間の存在をクマに知らせれば、クマのほうから避けてくれる可能性が高まります。静かに歩くと気づかれにくく、突然の遭遇につながるため注意が必要です。
次に挙げられたのが、複数人で行動することです。単独行動はクマに狙われやすく、危険が増します。数人で一緒に歩くだけでも声や足音が自然と大きくなり、クマに人間の存在を伝える効果があります。
そして、万が一出会ってしまったときの対応も重要です。目を見ながらゆっくり後退し、決して背を向けて走らないこと。走るとクマの追いかける本能を刺激してしまうからです。落ち着いて距離を取り、クマに背を見せないことが生存のカギになります。
一見すると単純な行動のように思えますが、これらを守れるかどうかが生死を分けることもあるのです。実際に山菜採りやジョギング中にこれらの行動を実践し、危険を回避できた人の事例も報告されています。
市街地で始まった「緊急銃猟」
2025年9月から新たに、市街地に出没したクマに対し市町村が発砲命令を出せる制度が導入されました。従来は警察のみが権限を持っていましたが、現場判断を迅速化する狙いがあります。各地の猟友会は訓練を重ねていますが、「住宅地では発砲が難しい」「子どもや通行人が巻き込まれる危険がある」といった現場ならではの課題も。実際に山形県鶴岡市では、市の判断で発砲許可が下りたものの、準備中にクマが人に迫り、最終的には警察の命令で発砲されたケースがありました。
北海道の“攻め”のクマ対策
クマ被害が特に深刻な北海道では、従来の「守り」から「攻め」へと方針を転換。春の冬眠明け直後に山に入り、クマの数を積極的に調整する春期管理捕獲が導入されました。また、スノーモービルで音を立てるなどして、クマに「人は怖い存在だ」と植え付け、山奥に戻らせる取り組みも進められています。しかし、この作業を担うのは高齢化の進む北海道猟友会のメンバー。多くは本業を持ちながら活動しており、持続可能な仕組み作りが大きな課題です。
行政の責任と専門職員の必要性
大西尚樹さんは「猟友会は経験豊富だが民間団体。地域住民の命を守る責任を負わせるのは本来違う」と警鐘を鳴らします。実際に秋田県では、県の職員としてクマ専門職員を雇用し、行政が主体的に取り組む体制を整え始めています。今後は研究者・行政・地域住民が一体となり、長期的な視点でクマとの共存を考える必要があります。
まとめ
この記事のポイントは以下の通りです。
-
クマは果実の放置や餌不足を背景に、市街地に近づいている
-
被害は山中よりも日常生活の場で増加し、顔面外傷など重傷例が多い
-
市街地での「緊急銃猟」制度が始まったが、安全性や運用面に課題が残る
-
北海道では春期管理捕獲や音による追い返しなど“攻め”の対策を実施
-
行政が責任を持ち、専門職員を配置することが今後の大きな鍵
私たちが安全に暮らしていくためには、個人の注意だけでなく、社会全体で仕組みを整えることが欠かせません。クマと出会うリスクは確実に高まっています。山や里に出かけるときは今回紹介した行動を意識し、また地域の取り組みにも関心を持つことが、未来の共存へとつながります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

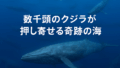
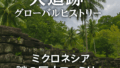
コメント