「さよなら“男らしさ”!?イマドキ男子の育て方」揺れる価値観と子育てのヒント
「男の子なんだから泣かないの」「男らしく強く育ってほしい」——そんな言葉を耳にしたことはありませんか。親としては良かれと思って言った一言が、子どもの心に「男らしさ」という重い枠を作ってしまうことがあります。特にジェンダー平等が進む2025年の今、こうした考え方に迷いや違和感を持つ親が増えているのも事実です。
今回の『おとなりさんはなやんでる。』では、タカアンドトシを司会に迎え、男の子を育てる母親たちや専門家が集まり、子どもとジェンダーをめぐるリアルな悩みを率直に語り合います。この記事では、番組の内容を文化社会学の視点から整理し、「男らしさ」とは何かを考える手がかりをお届けします。
ランドセルの色から見える固定観念
番組の冒頭で取り上げられるのは、ランドセルの色の問題です。小倉優子さんやpecoさんは「息子が赤やピンクを選びたいと言ったとき、どう受け止めればいいのか」という悩みを告白します。
私たちは当たり前のように「ピンク=女の子、青=男の子」と考えますが、実はこの色分けは歴史的に変化してきた文化的な産物です。かつて欧米では、赤やピンクは「力強さ」を象徴する色として男の子に結びつけられていた時代もありました。それが日本に輸入される中で逆転し、現在のイメージが定着したのです。つまり「ピンクは女の子の色」というのは、普遍的な真実ではなく“後から作られた常識”にすぎません。この事実を知るだけでも、親の心の中にある抵抗感が少し和らぐのではないでしょうか。
男子社会に潜む同調圧力と『有害な男らしさ』
次に焦点が当てられるのが、男子同士の世界に存在する独特の同調圧力です。番組では「パシリ」「罰ゲーム」といった事例が紹介されます。そこには「仲間外れにされたくない」「弱音を吐いたら笑われる」という恐れが隠れています。
専門家はこの現象を『有害な男らしさ』と指摘します。強くなければならない、リーダーシップを取らなければならない、そんな無言の期待は、思春期の男子を追い詰め、心の自由を奪います。こじらせた先には、いじめや不登校、さらには成人後の人間関係の歪みにつながる危険もあります。社会全体がこの「男らしさの呪縛」を見直すことが求められているのです。
『男性脳』『女性脳』という思い込みの落とし穴
さらに番組では、『男性脳』『女性脳』という有名な説についても議論が交わされます。「男の子は理系が得意」「女の子は感受性が豊か」といったフレーズは、一見わかりやすく聞こえますが、科学的には根拠が薄いとされます。
星野俊樹さんら専門家の解説によれば、脳の特徴は性別よりも個人差のほうがはるかに大きいとのこと。にもかかわらず、性別による固定観念を信じてしまうと「女の子だから文系を選ぶべき」「男の子だから理系に進むべき」といった無意識の抑圧につながってしまいます。これこそが子どもの可能性を狭める最大のリスクなのです。
変わりゆく社会と「新しい男の子像」
番組全体を通じて浮かび上がるのは、社会が求める「新しい男の子像」です。かつては「力強さ」「我慢強さ」が称賛されてきましたが、今は「共感力」「優しさ」「協調性」が重要視されるようになっています。特に学校や家庭では「男の子だから泣かないで」ではなく「泣いてもいい」「気持ちを表現していい」という言葉かけが、子どもに安心感を与えます。
文化社会学的に見ても、ジェンダー観は社会の変化とともに常に書き換えられてきました。だからこそ、今の親世代には「昔の常識にとらわれない勇気」が必要とされています。
番組出演者と専門家の役割
今回の放送には、タレントだけでなく多彩な専門家が登場します。清田隆之さんは文筆家として多くのジェンダー本を執筆しており、生活の中で感じる小さな違和感をどう言葉にすればよいかを教えてくれます。四本裕子さんはジェンダー研究の立場から、親が陥りがちな思考パターンを社会的に整理して示します。こうした解説は、視聴者に「自分だけが悩んでいるわけではない」という安心感を与えてくれるでしょう。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
-
『男らしさ』は普遍的な真理ではなく、文化や歴史が作り出した価値観にすぎない
-
男子社会にある同調圧力は『有害な男らしさ』を生み出し、子どもを追い詰める要因となる
-
『男性脳』『女性脳』という思い込みは子どもの可能性を狭める危険があり、多様性を尊重する子育てが求められる
この番組は「性別に縛られずに生きること」を子どもにどう伝えるかを考える大きなヒントになります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

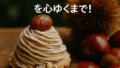

コメント