おおらか金継ぎ 器と人生を繕う
思い出の器は、長い時間を共に過ごすほど、その人の暮らしや気持ちが刻まれていきます。割れてしまった瞬間はショックでも、金継ぎという技法を通じて器が再び輝きを取り戻す様子には、単なる修復以上の深い意味があります。今回の『おとな時間研究所』では、その“器のよみがえり”のプロセスと、そこに宿る人生観に迫る内容が紹介される予定です。壊れた器が金色の継ぎ目をまとって生まれ変わるように、人の心も再び立ち上がる力を持っていることを静かに教えてくれる放送になりそうです。
金継ぎとは?思い出の器がよみがえる理由
金継ぎは、壊れた陶磁器を漆で接着し、継ぎ目に金や銀の粉を施して仕上げる方法です。割れてしまった部分が金色に浮かび上がることで、むしろ器そのものの存在感が増し、使い手が器と共に過ごしてきた歴史が際立ちます。
元通りに見せる西洋の修復技法とは異なり、隠さず“見せる”という発想が中心にあるため、破損の跡こそ美しさとして扱われます。日本独自の美意識が宿る文化で、傷を肯定し、時間の積み重ねを受け止める姿勢が深く反映されています。
また、修復された器はただ元の姿に戻るのではなく、壊れる前よりも魅力的に感じられることも多く、人によっては“戻った器”というより“新しい器が生まれた”という感覚を覚えるほどです。生活に寄り添ってきた思い出までよみがえるように感じられる点が、多くの人を惹きつけています。
堀道広さんが伝える“おおらかな金継ぎ”の心
今回の放送では、漆職人であり漫画家でもある堀道広さんが登場します。堀さんは都内各地で金継ぎ教室を開き、日々たくさんの器と向き合っています。教室には女性の参加者が多く、それぞれが家に眠っていたお気に入りの器や、家族から受け継いだ大切な皿などを持ち寄り、修復に挑戦します。
堀さんが大切にしているのは「完璧に戻そうとしない」「傷を否定しない」という考え方です。欠けた部分があるなら、その欠けを活かして新しい景色をつくればいい。金継ぎは、失われた部分を“取り戻す”のではなく、“その器が持つストーリーを深める”行為なのだと伝えています。
また堀さん自身が「自分の人生は繕った金継ぎのようだ」と語るように、作品づくりの中で得た実感や体験がそのまま人生観にも重なっています。日々の作業の中で、修復されていく器の姿から励まされる瞬間があり、それを教室の人たちにも自然と伝えているようです。
都内で人気が高まる金継ぎ教室と参加者のリアルな体験
都内には金継ぎが学べる教室が増えており、堀さんの教室も多くの人が通う場所です。持参される器は、旅先で買った思い出の湯呑みや、家族から受け継いだお皿など、どれも特別なエピソードが込められていることが多いそうです。
修復作業は、漆を使うため工程ごとに乾燥させる時間が必要で、すぐに完成するものではありません。ひとつの器にじっくり向き合う過程で、参加者の心に静かな時間が流れるのが金継ぎ教室の魅力です。
参加者からは
・よみがえった器を見ると胸が熱くなる
・丁寧に作業する時間が気持ちを整えてくれる
・壊れても捨てずに使い続けたいという気持ちが芽生えた
といった感想が上がることが多く、器だけではなく“暮らしへのまなざし”そのものが変化する体験となっているようです。
また、近年は『サステナブル』や『丁寧な暮らし』に関心が高まっており、金継ぎはそうした価値観と相性が良いことから、若い世代にも人気が広がってきています。
器と人生を繕う――堀道広さんの二刀流の歩み
堀道広さんは、漆職人として器を繕いながら、漫画家として自身の人生や日常を描く活動も行っています。これら二つの仕事は全く別物のようでありながら、実は共通点が多いそうです。どちらにも“壊れたものをどう扱うか”“何を残し、何を生かすか”という視点が求められるからです。
器の継ぎ目が金色に輝くように、堀さんの人生も、経験を重ねるほど味わいと深みが増しています。番組では、この二つの活動がどのように交わり、堀さん独自の世界観をつくっているのかが紹介される予定です。教室での指導の様子や、漆を扱う手の動きから伝わる“おおらかさ”にも注目したいところです。
金継ぎが教えてくれる「傷を受け入れる生き方」
金継ぎの核となるのは「壊れても価値が失われるわけではない」という考え方です。
器の欠けや割れは“汚点”ではなく、その器がたどってきた歴史そのものであり、金継ぎによって浮かび上がる金の線は、その歩みを肯定する光になります。
人の人生も同じように、経験や傷ついた記憶がその人の魅力や強さの一部になるという考え方が、金継ぎの哲学と通じています。器を通じて自分を重ねる人が多いのも、この考え方が理由です。
番組では、堀さんの言葉や作業風景から金継ぎが持つ優しい力が伝わり、見る側の心にもそっと寄り添う時間になるはずです。
金継ぎを始めるには?初心者がそろえたいもの
金継ぎを自宅で始めるには、漆・金粉・筆・ヘラ・器を固定する道具などが必要ですが、最近は初心者向けのキットも多く販売されています。割れた器が1つあれば、挑戦するための扉はすぐに開きます。
漆を扱うので乾燥に時間が必要ですが、その“待つ時間”こそ金継ぎの魅力です。焦らずじっくり取り組むことで、器が少しずつ変わっていく様子を感じられます。暮らしの中にゆっくりとした時間を取り戻したい人にとっては、はじめやすい手仕事です。
現代の暮らしと金継ぎが相性の良い理由
大量消費が見直される2025年、金継ぎは“長く使い続ける”という価値観を象徴する技法として注目され続けています。修復された器は世界にひとつだけの存在となり、食卓に置くだけで生活の質が上がります。
また、器を丁寧に扱う時間が心の安定につながるという声もあり、忙しい日々の中で“手を動かしながら心を整える習慣”として金継ぎを取り入れる人も増えています。暮らしと心の両方にゆとりをもたらす技法として、今後も人気は高まるでしょう。
まとめ
今回の『おとな時間研究所』は、壊れた器を繕うというシンプルな行為の中に、人生を重ねる深い視点を持つ回になりそうです。堀道広さんの金継ぎへの思い、教室に集まる人の体験、そして金継ぎの持つ穏やかな哲学は、見た人の心に静かに響きます。器の継ぎ目が金色に輝くように、自分の中の傷も光に変わるかもしれない——そんな余韻を残してくれる内容です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

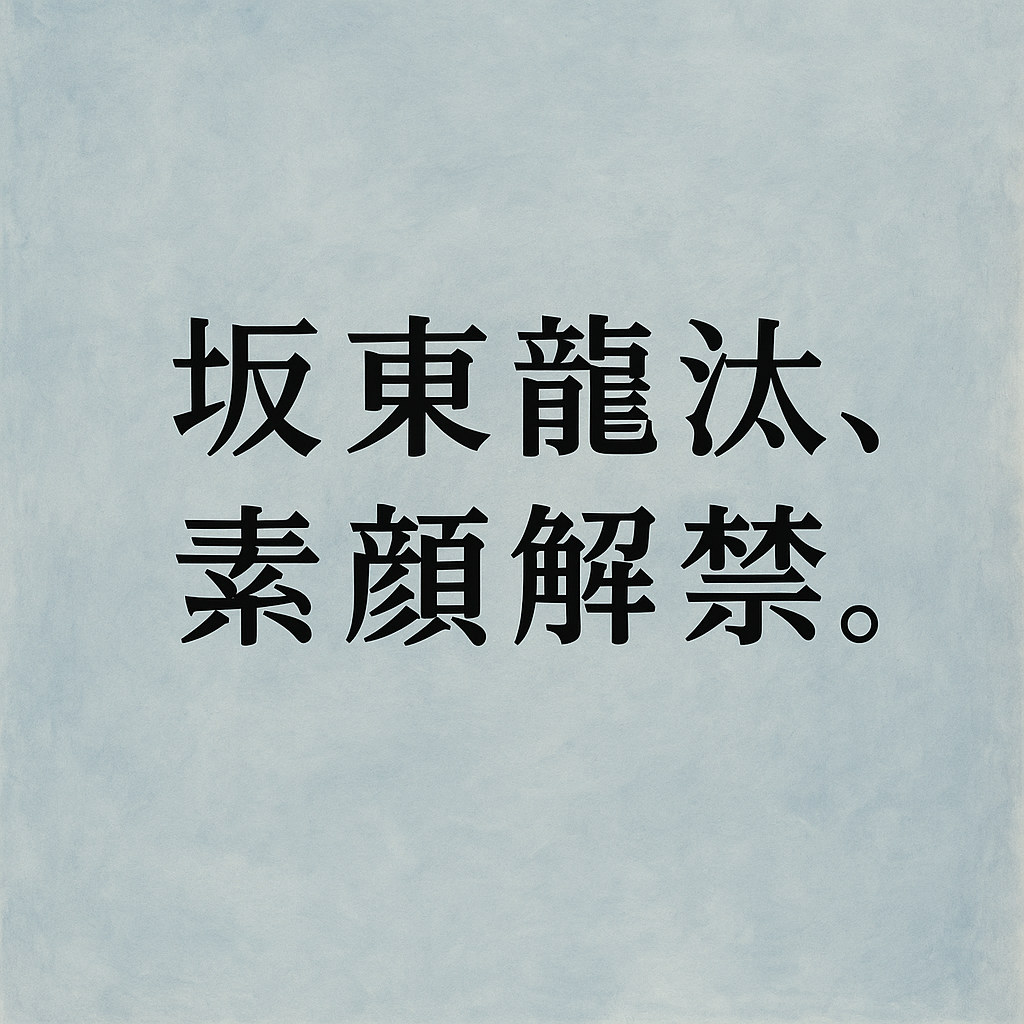
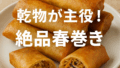
コメント