鹿児島・菱刈鉱山で金を掘り続ける人たちの物語
鹿児島県伊佐市の山奥にある菱刈鉱山は、日本で唯一、商業規模で金を掘り続けている場所です。年間およそ3.5トンという国内トップの産金量を支えるのは、坑道の奥深くで働く人たちの技術と覚悟でした。『ドキュメント72時間』が密着した3日間には、この山を守り続けてきた40年間の重みと、世代を超えて受け継がれる思いが刻まれていました。
【ドキュメント72時間】函館限定“ラッキーピエロ”の奇跡 地域を救うご当地バーガーと幸せの72時間|2025年10月17日
金が眠る山と鉱脈に向き合う作業の日々
鹿児島県伊佐市で1985年から採掘が続く菱刈鉱山。この山では、鉱石1トンにつき20グラム前後の金が採れるとされ、世界の平均値(3〜5グラム)をはるかに上回ります。番組では、現場によっては1トンから30〜50グラムの金が採れる高品位の鉱脈が確認されていました。
鉱石は黒い岩の中のわずかな部分に金が含まれています。一見地味な石ですが、その中には医療や電子部品にも使われる貴重な資源が眠っています。
坑内は長年の掘削で網目のように延びており、総延長は100キロメートル規模とも言われています。火山活動の名残で65℃ほどの高温水が湧く場所もあり、特殊な環境の中で作業員たちは日々向き合っています。
採掘現場では、岩の硬さを見極めながら爆破を行うための穴を掘り進め、爆破で落ちる岩の量や方向を計算しながら作業が続けられます。視界の悪い場所や湿気の多い区画、熱気が漂う空間など、環境は決して快適とは言えません。それでも黙々と、手順を守りながら作業する姿がありました。
夕方になると交代の時間が訪れ、坑内から上がってきた人々が汗を拭きながら休憩所へ向かいます。2交代制で作業は昼夜問わず続き、夜の作業員が坑道に入っていきました。
夜の休憩時間、入社1年目の若手社員が弁当を広げていました。慣れない環境に戸惑いながらも、「ここで頑張りたい」という思いがにじむ表情でした。
深夜0時すぎ、責任者が全員の退坑を確認すると、その日の最後の爆破が行われ、長い一日がようやく終わりました。
手選場から精錬工場へ続く金の流れ
2日目の朝、手選場では、鉱石の山から金を含む部分を人の目で判断しながら選り分ける作業が行われていました。金は目では分かりにくく、黒い石のごくわずかな部分に含まれているため、経験を積んだ作業員の目が欠かせません。
選別された鉱石はトロッコやコンベヤーで工場へ運ばれ、そこで精錬されて金に生まれ変わります。この金は電子機器の細かな部品、医療の現場で使われる精密機器、さらには国際的な需要が高い素材として社会のさまざまな場所へ旅立っていきます。
夕方には、探査課の担当者が新しい鉱脈を調べていました。スプレーで岩盤に印をつけ、金が含まれていそうな部分の境界を丁寧に確かめていきます。鉱脈の位置、深さ、厚さを見極めるこの作業がなければ、採掘は進みません。
同じ時間帯、入社1年目の社員が先輩から重機の操作を教わっていました。巨大な機械を扱うには技術だけでなく、土や岩のクセ、坑道の空気の流れなど、現場の感覚も必要です。少しずつコントロールを覚えていく姿には、この山で働く者の「はじまり」が詰まっていました。
夜の休憩所では、勤続42年のベテラン社員が静かに話していました。体力が以前より落ち、新しい機械に気持ちが追いつかないと感じる日もあるとのこと。60歳を前に、早期退職を考えていると語る表情は、長年現場を支えてきた人だけが見せるもののように見えました。
親から子へ受け継がれるこの山の誇り
3日目には、勤続39年の社員が登場しました。現在は管理業務を担当し、現場で働く息子を見守っています。かつて父と一緒に働いたという同僚からは、父の仕事ぶりを語るエピソードを聞くこともあるといい、「その背中を超えられるように頑張っています」と語っていました。
父が息子に伝えたのは「大切なのは謙虚さだ」という言葉。鉱山という厳しい環境の中で長年働いてきた人が大切にしてきた姿勢が、次の世代へと手渡されていました。
一方、勤続42年の社員は、自分が鉱山の仕事を選んだ理由、そして働き続けた年月の重みを語っていました。体力的に厳しい日もあった中で、「この山で働いてきたことには絶対に誇りがある」と話した言葉には、揺るがない思いが込められていました。
長い時間をかけて多くの人が支えてきた山だからこそ、「これからも残っていてほしい」という願いが強く感じられました。
まとめ
菱刈鉱山は、日本で唯一の商業金鉱山として今も金の採掘を続けています。高品位な鉱脈を支えるのは、暑さと湿気に満ちた坑道、複雑に延びる地下の道、そして厳しい環境で働く人たちの技術と覚悟でした。
若い世代が先輩から技術を学び、ベテランたちは長年守ってきた山への誇りを胸に、日々の仕事に向き合っています。金という資源を掘り出すだけでなく、この場所には人々の思いが積み重なり、世代を超えて受け継がれていく静かな物語がありました。
この山から生まれる金は、社会のあらゆる場面で使われています。見えない場所で支え続ける人々の力が、日本のものづくりや医療、技術の裏側を支え続けていることを改めて感じられる3日間でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

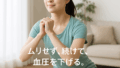
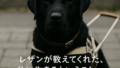
コメント