武田勝頼の知られざる強さと悲劇に迫る!
歴史が好きな人なら誰もが耳にしたことのある武田信玄。しかし、その後を継いだ武田勝頼の人生には、どこか影のような印象がつきまとっています。今回の『歴史探偵』(2025年11月5日放送)では、そんな勝頼の実像に光を当てました。「父を超えたい」という強い思い、そして「運命に翻弄された武将」としての姿――。あなたは、勝頼が本当に“無能な二代目”だったと思いますか?この記事では、番組の内容をもとに、武田勝頼の生涯を分かりやすく振り返ります。
【名将たちの勝負メシ】武田信玄の「ほうとう」とは?領土拡大と内政力が見える勝負メシとは
偉大な父を継いだ若き当主、重圧の中で挑んだ初陣
1573年、戦国の風雲児武田信玄が病に倒れ、その座を継いだのが四男の武田勝頼でした。勝頼は側室の子であり、当主としては異例の立場からの出発。父の絶大なカリスマ性の影に隠れ、「器ではない」と批判する家臣もいたといいます。
それでも勝頼は強い信念をもって戦国の世に立ち向かいました。信玄の死からわずか1年後、彼は徳川家康に寝返った高天神城(静岡県掛川市)を攻略します。戦況が長引けば、織田信長の援軍が到着する危険があったため、時間との戦いでした。
勝頼は東側の険しい崖から攻撃を仕掛け、敵の注意を引きつける“陽動作戦”を実施。そのすきに西側の緩やかな斜面から主力部隊が突入するという巧妙な戦術で、一気に形勢を逆転させました。さらに、「命は保証する」「降伏すれば恩賞を与える」との約束で城を開かせたのです。
この鮮やかな勝利に織田信長は「若輩なれど油断ならぬ」と書状で述べ、勝頼の才能を認めました。つまり、彼は父の遺産に頼らず、自らの知略で初陣を制したのです。
長篠の戦い──誇りと誤算、そして奇跡の脱出
その後、武田家は最大版図を誇り、甲斐・信濃から遠江まで広がる領国を築きました。しかし、1575年、運命の分かれ道となる長篠の戦い(愛知県新城市・設楽原)が訪れます。
武田軍1万5000に対し、織田・徳川連合軍は3万8000。数だけでなく、装備の差も歴然としていました。平地の南側は武田軍に有利な地形であり、勝頼は「ここで両将(織田信長・徳川家康)を討てるかもしれない」という誘惑に駆られたと、番組で平山優氏は分析します。
しかし信長はすでに対策を講じていました。数千丁の鉄砲を備えた三段撃ちの布陣、さらに馬を通さないための柵を幾重にも設置。誇り高き武田騎馬隊はその前に壊滅的打撃を受け、名将山県昌景ら重臣が次々と討死。勝頼はやむなく退却を命じました。
退却戦はさらに過酷でした。連合軍の追撃、増水した川での混乱、溺死する兵士たち――まさに地獄の光景。そんな絶望の中で、勝頼を救ったのが喜八という若い案内人でした。彼の導きにより、勝頼は夜通し50kmを歩き、段戸山を越えて武節城へと逃れます。わずかな護衛だけで命を繋いだこの脱出劇は、まさに奇跡と呼ぶべきものでした。
敗北の陰に隠れがちなこの逸話には、命懸けで家を守ろうとする勝頼の気迫が表れています。
敗戦ののちに見せた改革者としての顔
長篠の敗北後、武田家の名声は揺らぎました。しかし勝頼は諦めませんでした。敗因を冷静に分析し、戦国時代の変化に対応するために軍政改革に着手します。
特に力を入れたのが、鉄砲隊の強化でした。戦国時代後期、戦の主流が馬から火器へと移り変わる中で、勝頼はその潮流を的確に読み取っていたのです。さらに外交面でも、宿敵上杉謙信と和睦を結ぶなど、柔軟な戦略を展開しました。
領国の内政にも目を向け、税の見直しや道路整備を進めるなど、地域の安定を重視していたことも知られています。戦に明け暮れる武将でありながら、民を思う政治家の一面もあったのです。
再び訪れた悲劇、高天神城の落城
しかし、運命は勝頼に再び試練を与えます。かつて落とした高天神城が、今度は彼を追い詰める舞台となりました。
1579年、徳川家康が大軍を率いて城を包囲。周囲には20を超える砦を築き、補給路を完全に断ち切りました。籠城する将兵は救援を要請しますが、当時の勝頼は北条氏との関係が悪化しており、重臣たちも「動けば国が危うい」と反対。結果として援軍を送ることができませんでした。
孤立した高天神城では、食料が尽き果て、兵たちは命を懸けた突撃を決行。しかし、織田信長は降伏を拒否し、全員が討死します。
この悲劇的な結末により、「主君が家臣を見捨てた」という噂が広まり、武田家の求心力は一気に低下。ついに家臣たちの離反が相次ぎ、戦国最強と謳われた名家は崩壊の道をたどります。
武田家滅亡、そして信長が残した一言
1582年、織田信長と徳川家康の連合軍が甲斐に侵攻。追い詰められた勝頼は、最期まで戦い抜いたのち、自ら命を絶ちました。享年37。
驚くべきことに、敵であった信長は「勝頼は日本にまたとない武人であった。運がなかった」と述懐したと伝わります。
勝頼の戦いぶりには、信長ですら心を動かされるほどの気高い誇りがあったのです。スタジオで佐藤二朗さんも、「もし違う時代に生まれていたら、もっと大きなことを成し遂げていたかもしれない」と語り、その生き様に深く共感を寄せていました。
武田勝頼が現代に伝えるメッセージ
武田勝頼の人生は、たった9年の当主期間の中に光と影が共存しています。父の遺志を継ぎ、逆境に抗い、理想を貫いた男。その姿は、結果ではなく「過程」にこそ価値があることを教えてくれます。
人は時に“勝敗”で評価されがちですが、勝頼のように「信念を貫く強さ」こそが、真の武士の姿だったのではないでしょうか。
まとめ:敗れても誇り高き“最後の武田”
この記事のポイントを整理します。
・武田勝頼は父の遺産を超えようとした知略と情熱の武将だった
・長篠の戦いでは壊滅的敗北の中にも人間的な強さと執念があった
・敗戦後も改革と外交を重ね、最後まで武田家の再興を目指した
・高天神城の悲劇が滅亡の引き金となったが、それは運命のいたずらでもあった
・織田信長さえ称えた「武人・勝頼」は、今もなお語り継がれる存在である
敗北の中にこそ、武田勝頼の真の価値がある。彼の生き方は、どんな時代にも通じる「誇りと再起の物語」なのです。
(情報出典:NHK『歴史探偵』2025年11月5日放送)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


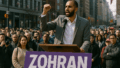
コメント