花と出会う幸せを、日常に
花屋の前を通りかかると、思わず目に留まる色とりどりの花々。けれど、「買ってもすぐ枯れそう」「どう飾ればいいか分からない」と、ついそのまま通り過ぎてしまう――そんな経験はありませんか?でも実は、花を一輪飾るだけで、部屋の空気も、心の温度もほんの少し変わるのです。
11月4日(火)放送のNHK Eテレ『心おどる 花のある暮らし』は、そんな“花のある時間”を提案する新番組。初回テーマは「花と出会う」。新進気鋭の華道家・写真家 池坊専宗が、誰でも気軽に取り入れられる花の飾り方や心の向き合い方を教えてくれます。
この記事では、池坊専宗という人物の魅力と、番組で紹介された“花との付き合い方”のエッセンスを、やさしく丁寧に紐解いていきます。
Eテレ【おとな時間研究所】図書館・学校・花屋に息づく“木の癒やし”をたどる旅|2025年6月13日放送
京都で生まれた若き芸術家・池坊専宗の歩み
池坊専宗は、いけばなの総本山である華道家元池坊の家に生まれました。父は次期家元の池坊専好。千年の歴史を誇る池坊の伝統を受け継ぐ立場でありながら、彼自身はその枠にとらわれず、現代の感性で花を見つめ続けています。
興味深いのはその経歴です。幼い頃から花に囲まれて育った一方で、学業の道ではまず慶應義塾大学理工学部に進学。その後、東京大学法学部に進み、卒業時には「卓越」の表彰を受けました。理系的な構造の美と、法学的な論理の美、その両方を学んだことが、後の“花と光”の関係を見つめる芸術的視点につながっているのかもしれません。
彼はまた、写真家としても知られています。自らいけた花を撮影するのではなく、草木の一瞬の表情や光の変化、影の呼吸をカメラで捉え、「命の時間」を記録するのです。花を“飾る”だけでなく、“観る”ことの大切さを、作品を通じて語ります。
現在は池坊青年部代表として次世代の華道家育成に尽力し、東京国立博物館アンバサダーや花の甲子園審査員として、文化と教育の両面から花の魅力を発信しています。伝統と革新、静けさと情熱――その両方を併せ持つ稀有な存在です。
花屋に入る一歩が、心をひらく第一歩
番組「花と出会う」で池坊専宗がまず語ったのは、「花屋に入ることを恐れないで」というメッセージ。
花を買うという行為は、誰にとっても少し緊張するものです。「どれを選べばいいか分からない」「センスがないと思われたら…」と尻込みしてしまう人も多いでしょう。そんな人たちに専宗が勧めるのは、“店の人と話してみること”。
「こんにちは、今日はどんな花が入ってますか?」
たった一言のやりとりから、花との関係が始まります。
花屋との会話を通じて、自分の“好き”が少しずつ見えてくるのです。鮮やかな色に惹かれる人、香りで癒される人、茎や枝ぶりに味を感じる人――それぞれの感性が花に映ります。専宗はこう語ります。「名もなき花ほど、あなたの暮らしに寄り添う」。ブランドや流行にとらわれず、自分の直感で選んでいいのだと背中を押してくれるのです。
花を選ぶときは「気取らない会話」がヒントになります。たとえば「この花はどの季節に咲くんですか?」「長持ちするのはどれですか?」など、素朴な質問で十分。会話を重ねるうちに、花が自分に語りかけてくるような感覚を味わえます。
“あるもの”を一緒に買うだけで、花がもっと輝く
番組の中で印象的だったのが、「お気に入りの花を買ったら、“あるもの”を一緒に買うと良い」というアドバイスです。
その“あるもの”とは、花を支える器や道具のこと。
花はただ花瓶に入れれば美しくなるわけではありません。器との相性が、花の魅力を引き立てるのです。
たとえば、真っ白なユリを飾るなら、深い紺色の陶器を。可憐なスイートピーなら、透明のガラスカップが似合う。花の形や色、茎の長さに合わせて器を選ぶことで、まるで小さな舞台のような空間が生まれます。
専宗は、わざわざ高価な花瓶を買う必要はないと言います。
「家にあるマグカップ、ジャムの空き瓶、湯飲みでもいいんです。それを“花の居場所”にしてあげれば、それだけで部屋が生き生きする」
また、霧吹きや花ばさみといった基本の道具も、暮らしの中で花を長く楽しむための重要な“相棒”。霧吹きで葉にうるおいを与えるだけで、花の表情は驚くほど変わります。
さらに、花を留める“花留め”を工夫すると、より自然な形に生けることができます。専宗は「花を立てるより、花に立ってもらうように」と語ります。まるで花と人が一緒に暮らしているような優しさが、その言葉には込められています。
ヒントは『自然の姿』の中にある
専宗が花を生ける際、常に意識しているのが『自然の姿』。この言葉には、いけばなの哲学が凝縮されています。
花を真っすぐ立てるのではなく、野原で風に揺れているように、自然のままの形を尊重する。花びらの角度、枝の曲がり方、葉の重なり方――そのすべてに自然の意志が宿っていると彼はいいます。
「光を感じ、草木の命をまなざす」
この信条には、写真家としての視点も重なります。自然光の中で草木が呼吸する姿を観察し、その“命のリズム”を感じながら生ける。そうすることで、花は単なるオブジェではなく、ひとつの“生き物”としてそこに存在するのです。
部屋の中でもこの考え方は活かせます。
窓辺の光の入り方、背景の壁の色、花を置く高さ――ほんの少し意識を変えるだけで、空間が生まれ変わります。
朝は東向きの窓に黄色の花を、夕方は西日を浴びる場所に紅い花を。光と影のコントラストを利用すれば、時間によって花が違う表情を見せてくれます。まるで一枚の絵を描くように、花を配置することが暮らしの“デザイン”になるのです。
暮らしに花を取り入れる5つのステップ
池坊専宗の哲学を実践するために、今日から始められる簡単なステップを紹介します。
-
花屋の前を通ったら、まず一輪だけでも買ってみる
-
名前を知らない花でも「好き」と思ったら迷わず選ぶ
-
家にある器を使って飾ってみる(コップでもOK)
-
光の当たる位置を観察し、時間帯で置き場所を変える
-
花を見ながら深呼吸して、自分の心の動きを感じる
これだけで、部屋の空気が柔らかくなり、気分も穏やかになります。
花を育てることは、実は“自分を育てる時間”でもあるのです。
花のある暮らしがくれる豊かさ
番組を通して感じるのは、花が単なる装飾品ではないということ。花は「今を生きること」を教えてくれます。
咲く時期も、枯れる時も、すべてが自然の流れ。花の一生を見つめることで、私たちは「今ここにある命」の尊さを知るのです。
池坊専宗の言葉にある「自然の姿」は、花だけでなく人間の生き方にも通じます。完璧でなくていい。少し傾いていても、曲がっていても、美しい。
それこそが、花のように生きるということかもしれません。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
-
池坊専宗は、京都生まれの華道家・写真家。伝統を重んじつつも「花を身近に」という現代的なスタイルを提唱している。
-
番組『心おどる 花のある暮らし』第1回では、「花屋に入る」「店員と話す」ことで花と出会う喜びを紹介。
-
『自然の姿』をヒントに、器・光・会話・時間を通して花を暮らしに取り入れることで、心に潤いと安らぎを生む。
花は特別なものではなく、生活の中に寄り添う小さな幸せです。
一輪の花が、あなたの一日を変えるかもしれません。
番組の内容と異なる場合があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


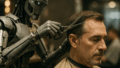
コメント