なぜ教会で結婚式?別腹の正体?漫画雑誌の紙の色の秘密
2025年5月23日放送の『チコちゃんに叱られる!』(NHK総合 19:57~20:42)では、「なぜ教会で結婚式を挙げるの?」「なぜ甘いものは別腹?」「漫画雑誌の紙がカラフルなのはなぜ?」という3つの身近な疑問が取り上げられました。今回のゲストは藤本美貴さんと天野ひろゆきさん。思わず人に話したくなる情報が満載の45分間でした。
教会での結婚式が多いのは「ローマ教皇のお試しOK」から

番組の最初に取り上げられた疑問は、「なぜ日本ではクリスチャンではないのに教会で結婚式を挙げる人が多いのか?」というものでした。チコちゃんの答えは「ローマ教皇がお試しでOKしてくれたから」というもので、これには歴史的な背景が深く関わっています。
解説を行った流通科学大学の道前美佐緒准教授によれば、日本のキリスト教徒は全体の約1%に過ぎませんが、結婚式において教会式を選ぶカップルは約46%にも及びます。これはとても大きな割合です。
もともと日本では、結婚の儀式には明確な全国共通の形式がなく、地域ごとや身分ごとに異なるやり方が存在していました。明治時代になって、近代国家としての体裁を整える必要が出てきたことから、伊藤博文の主導で神前式という新たなスタイルが作られました。これは簡素で厳かな形式として全国に普及させるためのものでした。
しかし、戦後になると状況が変わります。
-
1954年に映画『ローマの休日』が公開され、主演のオードリー・ヘプバーンの純白のウエディングドレス姿に憧れを抱く女性が増えました。
-
その影響を受け、ミッション系の学校を卒業した芸能人などが実際に教会で結婚式を挙げるようになり、その様子がテレビや雑誌で広く紹介されるようになりました。
-
こうした流れが一般の人々の意識にも影響し、教会式の結婚式が「特別で華やか」なものとして広まっていったのです。
ただし、ここで問題が生じます。カトリック教会では、本来は信徒でない人の結婚式を教会で行うことを認めていませんでした。それでも社会的な需要は高まり続け、1974年に日本カトリック司教協議会がローマ教皇に「信徒でない人の挙式を認めてほしい」と正式に申請しました。
その結果、翌年1975年、当時のパウロ6世が「条件付き」で特例を認める決定を下しました。その条件とは以下の3つです。
-
ミサ(宗教儀式)を行わないこと
-
この特例は日本国内のみに適用し、他国では認めないこと
-
あくまで「試験的な許可」であること
この決定によって、日本国内のカトリック教会では信徒でないカップルでも教会での結婚式が可能となり、一般に浸透していきました。
一方で、プロテスタント系の教会では、それぞれの教会が判断する形式を取っていたため、1970年代中頃にはすでに信徒でない人の挙式を受け入れていたところも多くありました。
このようにして、今では日本で教会での結婚式が当たり前のように行われるようになった背景には、ローマ教皇による特例許可や芸能文化の影響があり、さらに宗教的な柔軟性があったことが重なった結果なのです。教会式が日本の結婚文化として定着していったのは、宗教というより美しさや憧れのイメージが先に立った社会的な流れによるものでした。
甘いものは「本当に別腹ができる」から

番組で紹介された2つ目の疑問は、「なぜ甘いものは別腹なのか?」という身近で多くの人が感じたことのあるテーマでした。チコちゃんの答えは「本当に別腹ができるから」という科学的なもので、驚きの仕組みが明らかになりました。
解説を行ったのは、川西市立総合医療センターの三輪洋人先生です。人の体には、空腹時と満腹時で異なる信号を送る2つの中枢があり、空腹時には血糖値が下がり、脳の摂食中枢から「食べなさい」という指令が出されます。一方で満腹時には、血液中の糖分が十分にある状態になり、満腹中枢が「もう食べなくていい」と指令を出す仕組みになっています。
番組ではこの仕組みを確認するために、プロレスラーの真壁刀義さんが協力した実験が行われました。真壁さんはまず豚丼をしっかりと食べ、満腹の状態になった胃の様子を撮影。その後、大好物のモンブランを見て、においをかぐという刺激を与えた後に再度胃を撮影すると、明らかに胃にすき間ができていることが映し出されました。
このようにして生まれる「別腹」の仕組みに関係しているのが、「オレキシン」というホルモンです。
-
好きな食べ物の見た目やにおい、味の想像などが脳を刺激
-
脳はその情報を受けてオレキシンを分泌
-
オレキシンの作用で胃が広がり、胃液が多く分泌される
-
さらに胃の中の食べ物が小腸へ送られて、新しいスペースができる
この反応により、満腹だったはずの胃に「甘いもの用の空間=別腹」が物理的に現れるのです。
また、オレキシンの分泌は甘いものに限らず、「大好物」など強い食への欲求を感じる対象であれば同様の反応が起こることも紹介されました。甘いスイーツだけでなく、から揚げや焼き肉などでも別腹は発生します。
こうした仕組みは、原始時代の「食べられる時に食べておけ」という本能的な行動の名残とも考えられています。自然界ではいつ食料が手に入るかわからないため、たとえ満腹でも「好きなもの」「エネルギーになりやすいもの」を目の前にすると、身体は食べる準備を始めるのです。
さらに、栄養素をバランスよく摂取するために必要な仕組みでもあると考えられています。甘いものは糖分を効率よく補えるため、体にとって必要なエネルギー源となるのです。
このように、私たちが「別腹」と感じる現象は、実際に体の中で起きている科学的な反応であり、生存本能と栄養のバランスを保つための重要な機能であることが分かりました。
漫画雑誌の紙がカラフルなのは「インク残り&飽きさせないため」
番組の最後に紹介された疑問は、「なぜ漫画雑誌の紙はカラフルなのか?」というものです。チコちゃんの答えは、「再生紙のインクが抜ききれないから、そして飽きさせないため」でした。見慣れたあの色つきの紙には、ちゃんとした理由があったのです。
昭和40年代、日本の週刊漫画雑誌は空前の人気を誇り、発行部数は年間で2億部以上にまで達していました。そのため、出版社はとにかく大量に印刷する必要がありました。コスト削減のために選ばれたのが、「更紙(ざらがみ)」と呼ばれる再生紙です。
この更紙は、古紙を再利用して作られているため、黒インクなどの色素が完全には取り除けないという性質があります。
-
インクが残ってしまうと紙がグレーっぽくなり、印刷された文字が見えにくくなります。
-
そこで、あえて紙に色をつけてインク残りをごまかす工夫が生まれました。
静岡県富士市周辺は、富士山の豊富な水資源を活かして製紙業が盛んな地域として知られており、ここで漫画雑誌用の更紙も生産されています。番組では、富士市にある製紙工場の様子が紹介され、そこで使われている代表的な色として、
-
樺色(かばいろ)
-
ひわ色(黄緑に近い淡い色)
-
黄色
などが紹介されました。
これらの色にはいくつもの工夫が込められています。
-
文字が読みやすくなるようにグレーを避けて明るい色を使用
-
読者が飽きないようにページごとに色を変える工夫
-
色の変化により、漫画作品の切れ目が視覚的にわかりやすくなる効果もあります
つまり、紙がカラフルになったのは単なるデザインではなく、視認性の向上と読者への配慮、さらには印刷コストや資源再利用の工夫が重なった結果なのです。
こうした紙の使い方は、昭和時代から今に至るまで引き継がれており、日本独自の雑誌文化のひとつと言えるでしょう。たくさんの作品が収録される週刊誌にとって、色でメリハリをつけることは、読者の読みやすさや楽しさを支える大事な要素でもあります。
目には見えにくい紙の工夫にも、長年の知恵と工業技術が詰まっていることがよくわかる回でした。
休憩コーナーと視聴者おたより紹介
番組中盤では、藤本美貴さんの悩みとして「モノが所定の場所にないと困る」ことが紹介されました。さらにエンディングでは、視聴者から寄せられたキョエちゃんの衣装とおたよりが紹介され、番組は温かく締めくくられました。
まとめ
今回の『チコちゃんに叱られる!』は、歴史、医学、日常生活の工夫など、ジャンルを超えた疑問に答える充実した内容でした。毎週、子どもから大人まで楽しめる知識が詰まった番組として、今後も見逃せません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

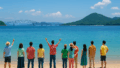
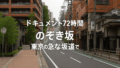
コメント