ファミリーヒストリー 立川志らく 〜好きな道にこだわり歩め〜
落語家の立川志らくさんの人生とその家族の物語が描かれた今回のファミリーヒストリー。番組では、父方・母方それぞれの祖父母から始まり、幼少期の体験、そして落語家として歩んできた道が丁寧に紹介されました。この記事では、放送内容をわかりやすく整理し、検索してきた方が知りたい情報をすぐに得られるようにまとめます。志らくさんがどんな家族のルーツを持ち、どのように落語の道に進んだのかを知ることができます。
祖父・伊三郎 お灸の大家として名を残す
志らくさんの父方の祖父・深谷伊三郎は、明治33年に東京・四番町で生まれました。当時の四番町は、皇居に近い地域で、武家屋敷の名残を持つ土地柄。高級官僚や会社の役員といった裕福な家庭が多く住む中で育ちましたが、伊三郎の家庭は決して恵まれていたわけではありません。幼い頃に母を亡くし、父が別の女性と家庭を持ったため、複雑な家庭環境で少年期を過ごしました。このような背景は、後の人生の選択や価値観に大きな影響を与えたと考えられます。
小学校を卒業した伊三郎は、進学することなくすぐに奉公に出ます。当時はまだ教育の機会が限られており、生活のために働かざるを得ない子どもも少なくありませんでした。伊三郎もまた、その一人でしたが、そこで培った勤勉さや忍耐力が、後に彼が大きな成果を残す土台となっていきました。
転機となったのは、24歳の時に日本大学専門部法律科へ進学したことです。これは特別な制度を利用したもので、学歴にとらわれず、優秀と認められた人材を受け入れる仕組みでした。伊三郎は通信教育を経て試験に合格し、見事に入学を果たします。当時は昭和初期で、金融恐慌など社会が混乱していた時代。そんな中で大学を卒業したことは、彼の強い意思と努力を物語っています。
その後、自分に何ができるのかを深く考えた伊三郎は、過去に自らが肺結核を患い、苦しんでいた時にお灸で救われた経験を思い出しました。これをきっかけに、鍼灸師の道を志すことを決意します。彼は既存のやり方にとどまらず、自ら新しい道具を開発し、より効果的な治療法を模索しました。また、お灸の効果を単なる経験談としてではなく、客観的な文章にまとめて広く伝えたことも特徴的です。こうして伊三郎は、後世にまで名を残す「お灸の大家」として、多くの人から尊敬される存在になっていきました。
父・英雄 ギタリストとしての情熱
父の新間英雄は昭和10年に生まれました。幼い頃から好奇心旺盛で、特に手先を使うことや芸術的なことに強い関心を持っていました。中学時代には祖父である深谷伊三郎の影響を受け、早くもお灸の技術を習得します。同時に、絵を描くことにも力を注ぎ、身近な風景や人物を描きながら表現力を磨きました。芸術に向けた多彩な関心は、若い頃からすでに芽生えていたのです。
特に大きな転機となったのは、クラシックギターとの出会いでした。英雄は世界的に有名なギタリストであるアンドレス・セゴビアに強く憧れ、彼の演奏スタイルや音色を理想として自らの道を決めました。練習に打ち込み、情熱を注ぎ続けた結果、24歳のときに念願のプロとしての活動をスタートさせます。しかしその選択は、現実的な生活を重んじる父・伊三郎からは強く反対されました。芸術の道は安定せず、生活の保証が難しいと考えられていたためです。
そんな中、英雄はギター教室で運命の出会いを果たします。そこで出会ったのが後に妻となる新間富士子でした。二人は音楽を通じて惹かれ合いましたが、最初は周囲からの結婚への反対もありました。それでも英雄は富士子との人生を選び、最終的に婿入りという形で新しい家庭を築くことになります。昭和37年に二人は結婚し、やがて長男である一弘(のちの立川志らく)が誕生しました。
志らくさんが落語に関心を持ち、芸の道に進むきっかけを作ったのは、まさにこの多趣味な父・英雄の影響でした。ギターや絵画に限らず、好奇心を持ってあらゆる分野に挑戦する姿勢が、息子にも自然と受け継がれたのです。
母・富士子と浜松の新間家
母の新間富士子は、静岡県浜松市の出身です。家系は裕福で、祖父の新間金三郎は当時としては珍しく選挙権を持つほどの人物でした。その娘である祖母の新間好子は、浜松市の八幡地にある家で育ちました。地域の中でも文化的な環境に恵まれており、幼い頃から礼儀や芸事に親しむ機会が多かったと考えられます。
しかし、好子の人生は決して平坦ではありませんでした。昭和4年に最初の夫を亡くし、若くして未亡人となります。その後、学生時代から思いを寄せていた川井明との結婚を決意しました。川井明は成績優秀で中央大学へと進学し、親族からの反対を押し切ってまで好子と一緒になる道を選びました。この強い意思は、のちに家族の絆や価値観に大きな影響を与えていきます。
戦後になると、好子は生活のために浜松駅前で旅館を営むようになります。焼け野原となった町に立ち、定員19名ほどの小さな宿を切り盛りしましたが、ただ働くだけではなく、自身の楽しみであった三味線や踊りといった稽古ごとも続けました。困難な時代にあっても芸事を愛する姿勢を貫いた好子の生き方は、その後の家族にも色濃く受け継がれ、子や孫が芸に打ち込む原点となっていきました。
家族の芸事への情熱と志らくへの影響
父の新間英雄は、ギターの演奏だけでなく、けん玉やビリヤード、ダーツといった幅広い趣味に熱中していました。遊びの延長ではなく、本気で極めようとする姿勢が強く、子どもたちにも自然と影響を与えていきます。志らくさんも弟の清登と一緒に父の趣味に参加し、技を競い合ったり夢中になったりすることで、遊びながら学ぶ楽しさを体験しました。
一方で、母の新間富士子もまた芸事に対して強い関心を持っていました。専業主婦となってからは新しい挑戦として長唄三味線を習い始め、家庭の中に音楽や芸の雰囲気を持ち込みました。夫婦それぞれが自分の好きなことに誠実に取り組む姿は、子どもたちに「好きな道を選んでいい」という空気を自然と伝えていたのです。
このように、家族全員が自分の興味や関心に本気で向き合う環境の中で育ったことが、のちに志らくさんが落語という芸の道に進む大きな原動力となりました。自由で個性を尊重する家庭の空気が、彼の人生の選択を後押ししたのです。
志らく 落語家への道
昭和57年、立川志らくさんは日本大学芸術学部に入学しました。学生生活では幅広い芸術に触れる機会を得ましたが、次第に心惹かれていったのは落語の世界でした。そして大学4年生の夏、周囲が就職活動を進める中で、自らは落語家になるという大きな決断を下します。
その後、昭和60年に落語界の異端児とも言われた立川談志に入門。個性を大切にする談志のもとで、厳しい修行の日々を歩み始めました。両親もこの選択を支えるために談志に挨拶に赴きましたが、志らくさんは緊張を見せることなく、堂々とした態度で師匠と向き合ったと伝えられています。この強い姿勢こそが、芸の道を生き抜く覚悟を示していたのでしょう。
修行の成果は早くも現れ、昭和63年には二ツ目に昇進します。この大きな節目の際、祖母の新間好子からは高価な袴が贈られました。芸事を愛し、自らも三味線や踊りに親しんできた好子にとって、孫が本格的に芸の道を歩む姿は何よりの喜びだったのです。志らくさんはその思いを胸に、高座に立ち続けました。
好子は孫の成長を見届け、平成5年に88歳でその生涯を閉じました。志らくさんにとって、祖母の存在は芸の世界で生きる決意をさらに強くする支えとなり、今もその精神は受け継がれています。
落語以外への挑戦と弟の道
志らくさんは落語の世界にとどまらず、常に新しい挑戦を続けています。舞台での高座だけでなく、映画の制作や演出、さらには評論活動にも積極的に取り組み、その表現の幅を大きく広げてきました。多彩な活動はすべて、「表現者として自分にできることを試したい」という強い意欲から生まれたものです。芸人という枠を超え、文化や社会に対してもメッセージを発信し続けている姿勢が、多くの人に影響を与えています。
一方で、弟の新間清登もまた、自らの道を切り開きました。長らく別の仕事に携わっていましたが、40歳を過ぎて父・新間英雄と同じギタリストへと転身。年齢にとらわれず、情熱を持って新しい挑戦に踏み出した姿は、家族らしい生き方の象徴といえるでしょう。
こうして兄弟それぞれが異なる道を歩みながらも、共通しているのは「本気で好きなことに取り組む」という家族の気質です。祖父・伊三郎の探究心、父・英雄の芸術への情熱、母・富士子や祖母・好子の芸事を愛する姿勢。そうした代々の生き方が脈々と受け継がれ、志らくさんや清登さんの選択にも自然と根付いているのです。
まとめ
今回のファミリーヒストリーでは、立川志らくさんがなぜ「好きな道にこだわり歩む」のかがよくわかりました。祖父・伊三郎の努力と革新、父・英雄の芸術への情熱、母方の新間家が持つ芸事の伝統。そのすべてが志らくさんの中に息づいています。落語という道を選んだのは偶然ではなく、家族の歴史に導かれた必然ともいえるでしょう。視聴者にとっても、自分の好きなことを追い続ける大切さを改めて感じさせられる内容でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

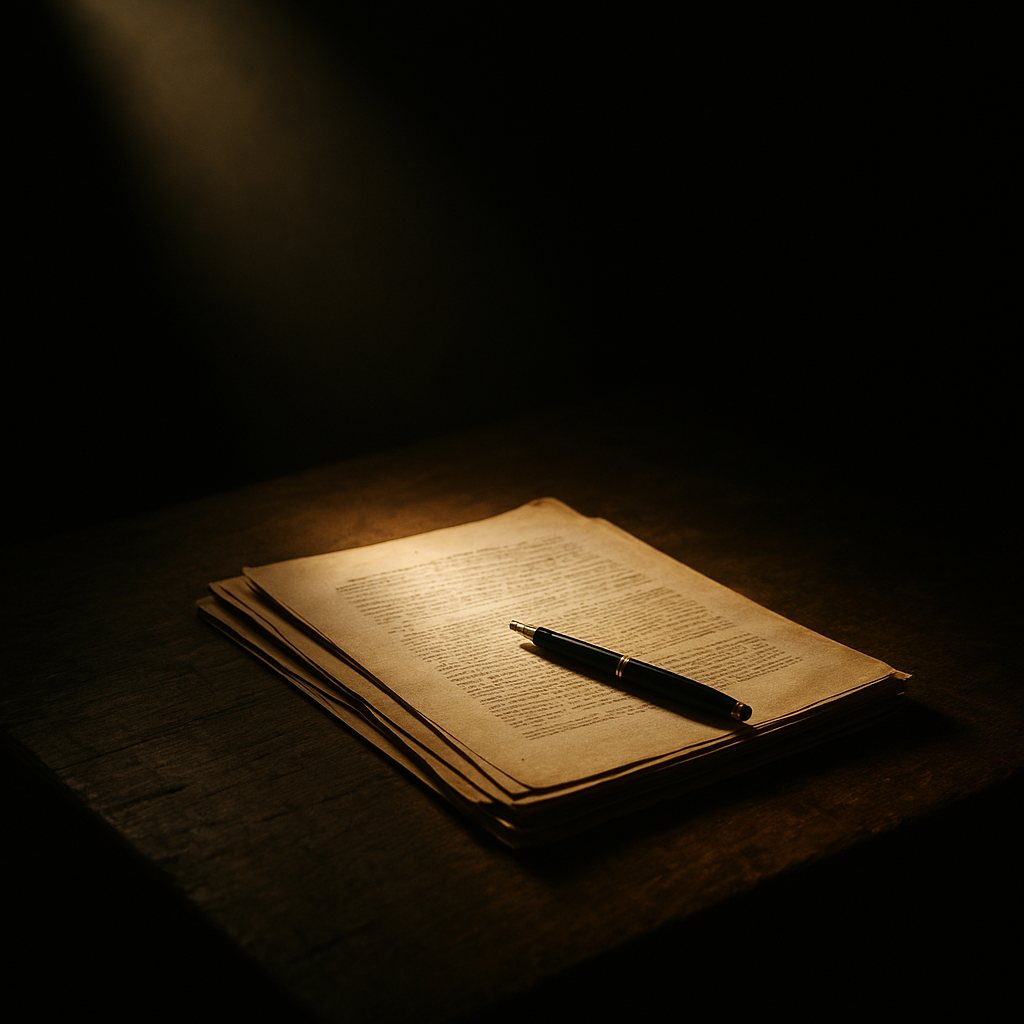

コメント