算額を知りたい!外国人博士が追う和算の秘密
2025年9月2日にNHK総合で放送された「最深日本研究〜外国人博士の目〜 算額を知りたい」では、江戸時代に生まれた算額絵馬と、それを今も追い続けるドイツ出身の思想史学者アントニア・カライスルさんの研究が紹介されました。算額とは何か、なぜ日本独自の数学「和算」と深く結びついているのか、そしてなぜ現代の私たちにとっても大切なのか――番組ではその答えを探る旅が描かれていました。ここでは、その内容をさらに詳しく整理しながらご紹介します。
江戸時代に広がった算額文化とは
算額とは、寺社に奉納された大きな絵馬のことです。ただし描かれているのは絵や願い事ではなく、数学の難問とその解答です。奉納者の名前も記され、誰がその難問を解いたのかがわかる仕組みになっていました。江戸時代、和算と呼ばれる日本独自の数学が庶民に広まり、難問を解くこと自体が一種の娯楽や誇りとなっていました。その成果を社会に示す場が算額だったのです。
奉納された算額には、円や三角形を使った図形問題が多く見られました。例えば「円に内接する正方形の面積を求めよ」といった問題で、図形の下に解答と証明が丁寧に書かれています。単に学術的な意味だけでなく、数学を通して人と人とを結びつけるコミュニケーションの場でもあったのです。
アントニア・カライスルの研究の旅
アントニアさんは来日して2年、日本全国を自転車や電車で巡りながら算額を撮影・記録しています。番組では山形県若松寺(若松観音)を訪れた様子が紹介されました。江戸後期の元治元年に奉納された算額には、当時の数学愛好家たちの名前と問題が残されており、彼らが「解けたことを公に示す」文化があったことがわかります。
算額の撮影は簡単ではありません。高解像度カメラを使い、標準と広角レンズを切り替えながら何十枚も撮影。そのうち使えるのはわずか1〜2枚とのこと。鮮明な記録を残すため、彼女は独学で撮影技術を学びました。これまでに全国で500枚以上の算額を記録し、残りは約400。研究の過程自体が大きな挑戦です。
和算が庶民に広まった背景
和算は7世紀に中国から伝来した暦や天文学の技術を基に日本で発展しました。江戸時代には寺子屋で庶民の子どもが読み書きとともに和算を学び、生活に役立つ知識として普及しました。特に**「塵劫記」**は大ベストセラーとなり、買い物や建築の計算方法などがわかりやすく書かれていたため、庶民の必読書となったのです。
また、和算を専門に教える和算家が現れ、私塾を開き人気を集めました。算木やそろばんを使った授業はエンターテインメント的な要素もあり、数学が「遊び」として楽しまれていたことも特徴です。アントニアさんは、西洋に広がったユークリッド幾何学が日本に根付かなかった背景に、この和算文化の存在があると考えています。
地域に残る算額と人々の思い
山形県の御嶽神社には明治23年に奉納された算額が残されており、地元の算額研究会が今も守り続けています。算額の中には、当時の人が遊び心で書き込んだ落書きもあり、和算が地域に浸透していた証拠となっていました。
さらに「宝珠山 立石寺」では長さ3mにもなる巨大な算額が公開されました。12問の和算問題と、それに関連する絵が描かれており、単なる数学の記録を超えて芸術作品のような存在感を放っていました。ここでは関孝和の「関流」や山形の会田安明率いる「最上流」といった流派が確認され、和算が多様な学派の競争の中で発展していたことが示されています。
無人寺に残された算額の発見
長野市の土倉文殊堂では、大正時代に奉納された算額が天井にはめ込まれていました。老朽化で崩れた天井を修復するために地域の人々が奉納したもので、算額は信仰と生活の両面に根ざしていたことがわかります。さらに奥の本堂には文殊菩薩が算木で計算する姿が描かれており、知恵の神と算術が結びついた独特の文化を感じさせました。
デジタルアーカイブ化と未来への継承
アントニアさんは撮影した算額をデータベース化し、日本語と英語で公開しています。誰でもアクセスでき、さらにオープンソースとして加筆可能にすることで、研究者だけでなく一般の人も算額の知識に触れられるようにしています。中国出身の助手が漢語で書かれた算額を翻訳するなど、多国籍の研究体制も整えています。来年春にはアーカイブの完成を予定し、流派ごとの広がりや地域差を分析する計画です。
算額が伝える日本文化の奥深さ
算額は、数学の難問を記録するだけの存在ではありません。江戸時代、人々が算額を囲んで交流したように、今も算額は人と人をつなぐメディアとしての役割を果たしています。学問、遊び、信仰、地域の誇りが交差する算額は、日本文化の多層性を示す大切な遺産です。
アントニアさんの研究はまだ途上ですが、算額を通して「日本人と数学の知られざる関係」を解き明かす試みは、今後ますます注目されるでしょう。和算の精神と算額の魅力がデジタルで未来に引き継がれることで、世界中の人々が日本独自の数学文化に触れられる日も近いはずです。
算額はただの数学の絵馬ではなく、人々の知恵や努力、そして地域をつなぐ力を持った文化的遺産です。今回の番組をきっかけに、私たちも身近な寺社に眠る算額に目を向けてみると、新しい発見があるかもしれません。
算額の代表的な問題例とその特徴

ここからは、私からの提案です。算額には江戸時代の人々が考え出した多くの数学の問題が描かれています。ここでは代表的な例を取り上げ、その内容と魅力を詳しく紹介します。当時の算額はただの計算問題ではなく、美しい図形と学問的挑戦を組み合わせた知の遊び場でした。
円に内接する正方形の面積を求める問題
円の中に正方形を描き、その面積を求める算額です。例えば「半径10の円に内接する正方形の面積は?」という問いが出されます。解法の重要なポイントは、円の直径と正方形の対角線が同じ長さになるという性質にあります。この関係を利用すれば、対角線から正方形の辺の長さを求め、さらに面積を導き出すことができます。このように算額では、図形の関係を見抜くことが鍵となり、ただ公式を当てはめるだけではなく、図形の美しさを感じながら解く楽しみがありました。江戸時代の和算愛好者は、こうした問題に挑戦し、解けた喜びを算額として奉納したのです。
2つの円に接する小円の半径を求める問題
大小の円が並び、その間にもう一つ小さな円を描いて、それぞれにぴったり接するように配置した図があります。条件は、大きな円と小さな円、さらに地面のような直線にも接することです。このとき真ん中に描かれた円の半径を求めるのが問題です。接円問題と呼ばれるもので、幾何学的に高度な内容を含んでいます。欧米の数学にも似た課題がありますが、江戸時代の日本ではすでに神社に算額として奉納されていました。この問題は単純に見えながら、複雑な関係を読み解く必要があり、多くの和算家たちの挑戦心をかき立てるものでした。算額は人々がその解答を残し、互いに腕前を示す場でもあったのです。
三角形と円を組み合わせた問題
算額では三角形と円を組み合わせた問題も多く残されています。例えば「与えられた三角形の中に円を描き、その円の半径を求めよ」といったものです。逆に、円の外に三角形を置き、その面積や辺の長さを求めるケースもありました。これらは単なる数値計算ではなく、図形の性質を理解しながら解き進める知的な挑戦であり、江戸時代の人々がどれほど数学を楽しんでいたかを示しています。図形と公式を組み合わせる形式は、和算を学ぶ人々にとって格好の腕試しとなり、算額の人気を支える要素でもありました。
算額問題の特徴
算額にはいくつかの共通した特徴があります。まず、解法は細かく説明されず、答えだけが簡潔に記されることが多かった点です。見る人が自分の力で考える余地を残していました。次に、短いヒントとして「術曰(じゅついわく)」と呼ばれる簡潔な言葉が添えられていたことです。これは解き方の大まかな道筋を示すもので、学ぶ者にとって大切な手掛かりとなりました。そしてもう一つの特徴は、算額が当時の数学パズルのような役割を果たしていたことです。問題を眺めるだけで「どう解くのか」と想像を膨らませ、学びの楽しさを共有できる仕組みがありました。算額は、ただの学術的記録ではなく、人々が数学を通して交流し、挑戦する文化を象徴する存在だったのです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


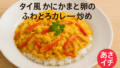
コメント