コメ価格の未来はどうなる?“増産”を阻む壁と家計への影響
「スーパーでお米の値段が上がってきて家計が苦しい…」「ニュースで“増産”って言うけれど、本当に米価は安定するの?」そんな不安を感じていませんか?最近、コメ価格は3週連続で高値が続き、毎日の食卓を支える主食だけに、多くの家庭が敏感になっています。私自身も買い物に行くたびにその影響を実感している一人です。この記事では、2025年9月26日に放送された首都圏情報 ネタドリ!「コメ価格は安定するのか〜“増産”を阻む壁〜」で取り上げられた現場の声と課題をもとに、消費者が知っておくべきポイントを整理します。読み終える頃には、コメ価格の今後とあなたの生活にどう関わってくるのかが、はっきりと見えてくるはずです。
栃木・大田原市 所有者不明農地という壁
続いて取り上げられたのは、栃木県大田原市のほ場整備事業です。農地を整備し、区画を大きくまとめることで大型機械の活用を容易にし、生産性を高めようとする取り組みです。整備事業は10年単位の長期プロジェクトですが、所有者の同意が必要であるため、そこで大きな壁に直面しています。農地の所有者が不明で連絡が取れないケースが相次いでおり、さらに所有者が亡くなっていて相続人が確定していない例も多いのです。
栃木県は司法書士会と連携し、農家を支援する仕組みを5月から始めました。しかし「所有者不明農地」は全国で全体の約2割を占め、いわば“虫食い”のように農地の集約を阻んでいます。区画整理が進まなければ効率的な農業も実現できず、増産のブレーキとなるのです。
中山間地の農地を守る意味
番組後半で注目されたのは、中山間地の農業でした。新潟県十日町市の農家徳永稔さんは、従業員2人とともに20ヘクタールの田んぼを耕作しています。2年前にはGPS付き田植え機を450万円かけて導入しましたが、山間部では電波が弱く、十分に活用できないことが判明。先進技術も、地形や環境によっては力を発揮できないのです。
それでも徳永さんが中山間地を守りたいと考える理由ははっきりしています。中山間地の田んぼは、鹿や猪などの獣害を防いだり、雨水を貯めることで水害を防いだりと、地域全体を守るインフラ的な役割を担っているからです。こうした役割はお金には換算できませんが、平地の暮らしを支える上で欠かせないものなのです。
さらに、新潟県上越市の保坂一八さんが率いる農業法人では、平地と中山間地を一体的に管理し、地域にある12の農業法人や農家と連携しています。農機具や肥料を共同で購入・使用することでコストを削減し、若手が中山間地を手伝う中でベテラン農家から学ぶ仕組みを作っています。結果として、中山間地を守りながらも生産力を維持できる実例が紹介されました。
家計に直結するコメ価格の安定化
番組のスタジオでは、日本総合研究所の三輪泰史さんが解説を行いました。「所有者不明農地」問題の背景には高齢化と相続があり、2024年から始まった相続登記の義務化でようやく改善が期待できるといいます。義務化に対応しない場合は10万円以下の過料が科される可能性もあるため、農地を放置せずに次世代にバトンを渡す流れが作られつつあります。
一方で、私たち消費者にできることも示されました。消費者と農業者はこれまで「買う側」と「作る側」で分断されがちでしたが、今後は農業現場に関心を持ち、農業イベントや地域の取り組みに参加することが重要です。米価の安定は単に食費の問題ではなく、日本の食料安全保障や地域社会の維持にも直結しているのです。
まとめ:コメ価格を守るのは誰か
この記事のポイントは以下の3つです。
・大規模化と最新技術の導入だけでは不十分で、資金力と農地集約が大きな壁になっている
・所有者不明農地が農地整備の妨げとなり、増産を阻んでいる
・中山間地は農業だけでなく防災や環境維持の役割を担っており、守る仕組みづくりが必要
家計を預かる立場として、お米の値段の上下は非常に気になる問題です。しかし価格の背景には、農家の努力や農地制度、地域を守る中山間地の存在があることを知ることで、単なる「安ければよい」という視点から一歩進んだ理解ができます。今後の政策や技術の進展によって米価が安定していくことを願うと同時に、私たち一人ひとりが農業と少しでもつながることが未来の食卓を守る力になるでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

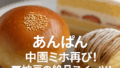
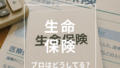
コメント