総理大臣は誰に?いま日本政治が迎える「転換点」
政治のニュースを見ても「連立」「閣外協力」「政権交代」などの言葉が飛び交い、正直わかりにくい…そう感じている人は多いはずです。そんな中、NHK『クローズアップ現代』(2025年10月20日放送)では、「総理大臣は誰に?政局激動のゆくえは」というテーマで、自民党と日本維新の会による“連立政権合意”の舞台裏を徹底的に掘り下げました。番組の進行は桑子真帆キャスター。政治部の小口佳伸記者、そして政治学者の中北浩爾教授がスタジオで、いまの政治がどこに向かっているのかを丁寧に解説しました。この記事では、その放送内容をもとに、連立合意の背景・各党の思惑・そして日本政治の今後について、わかりやすくまとめます。
きっかけは突然の接触 高市総裁と吉村代表の“政権合意”舞台裏
番組の冒頭で映し出されたのは、日本維新の会の吉村洋文代表が、自民党・高市早苗総裁との党首会談に向かう姿。実はこの会談の連絡が入ったのは、わずか2日前のことだったといいます。
日本維新の会が自民党に提示した要求は12項目にのぼり、そこには「企業団体献金の廃止」「食品への消費税率を2年間0%にする」といった大胆な政策も含まれていました。その中でも吉村代表が「絶対に譲れない条件」として挙げたのが「衆議院議員の定数削減」。政治改革の象徴ともいえるテーマを軸に、自民党との交渉が進められたのです。
番組では、吉村代表が「政治の信頼を取り戻す第一歩として、まず身を切る改革を示したい」と語る場面も紹介。対して、立憲民主党など一部の野党は「人気取りにすぎない」と批判するなど、波紋が広がっている様子も映し出されました。
なぜ「閣外協力」なのか?維新が閣僚を出さない理由
今回の連立合意では、日本維新の会が“閣僚を出さない”という選択をしたことも注目を集めました。いわゆる「閣外協力」という形です。
政治部の小口佳伸記者は、この背景について「維新はまだ全国的な政権運営の経験が少なく、人材育成の面でも課題を抱えている。いきなり閣僚を出すより、政策面で実績を重ねたいという判断」と解説。さらに、「閣外協力という形であれば、政策実現のための連携は保ちながらも、責任の範囲を明確にできる」という政治的な計算もあると指摘しました。
実際に維新側は、経済政策や社会保障改革、そして定数削減といった改革テーマで主導権を握る意向を示しており、「政権参加の前段階」という位置づけでこの協力体制を選んだとみられます。
政党間の思惑が交錯 “野党再編”の動きも
一方で、野党側も黙ってはいません。番組では、立憲民主党・野田佳彦代表が「定数削減はかつて自分が自民党と交わした約束だ」と振り返る場面が紹介されました。野田代表は、「その約束が果たされないまま、維新が同じテーマで自民と組むのは看過できない」と述べ、強い警戒感を示しました。
立憲民主党は、今回の連立合意を「政治の方向を決める重大な分岐点」と捉えつつも、焦点を「政治とカネの問題」や「政策の透明性」に移していく構えを見せています。
また、国民民主党も自民党との連携を模索。高市総裁は国民民主党に対し、「経済対策や子育て支援など、共通の政策を進めたい」と語りかけたとされ、将来的な連立参加の可能性をにおわせました。
公明党は「反対はしない」としつつも、「小選挙区と比例代表の両方で削減すべき」と主張し、制度の公平性を訴えています。各党の利害が複雑に絡み合い、次の一手を探る動きが続いています。
専門家が語る「定数削減」実現の壁
番組後半では、政治学者の中北浩爾氏が登場。注目の「定数削減」について、実現の見通しを冷静に分析しました。
中北氏は「選挙制度は政党政治の“ルールそのもの”。ここを変えるには、与野党の幅広い合意が不可欠です」と強調。その上で、「衆議院にはすでに選挙制度協議会があり、来年に向けて議論が進行中。今回の動きはその流れを追い越す形で出てきたもので、唐突感は否めない」と語りました。
つまり、政治改革としては意義があるものの、スピード感を重視しすぎると制度上の整合性を欠く危険もある、ということです。日本の議会制度の根幹に関わる問題であるため、今後の議論には慎重さと丁寧な説明が求められます。
2025年、日本政治の地殻変動が始まった
番組の最後に中北氏が語ったのは、「いまの動きは十数年に一度の政権再編の兆し」だという言葉でした。
自民党と日本維新の会という“新しい組み合わせ”が政権を動かし始め、そこに国民民主党や公明党がどう関わるかによって、日本の政治地図は大きく変わる可能性があります。
また、経済政策・社会保障・地方分権といったテーマで維新の政策がどこまで反映されるかも、今後の注目点です。高市総裁にとっても、今回の連立は政権基盤を強化するための重要な賭け。世論の評価によっては、次の総選挙や総理指名選挙に直接影響を与えることになりそうです。
まとめ:いま問われるのは「誰がリーダーか」ではなく「どんな政治をつくるか」
この記事のポイントを整理します。
・自民党と日本維新の会が連立合意。維新は“閣外協力”として政策面で連携
・最大の焦点は「衆議院議員の定数削減」。野党や公明党もそれぞれの立場で意見を表明
・専門家は「与野党合意が不可欠。唐突な印象は否めない」と指摘
・日本政治は今、十数年に一度の“再編期”に突入
今回のクローズアップ現代が伝えたのは、「誰がトップになるか」だけではなく、「どんな政治を築くのか」という問いでした。政治の信頼を取り戻す改革は、スローガンではなく、具体的な制度変更と責任の共有によってしか実現しません。2025年の秋、日本の政治は確実に新しい局面へと進みつつあります。
出典:NHK『クローズアップ現代 総理大臣は誰に?政局激動のゆくえは』(2025年10月20日放送)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

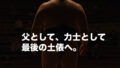
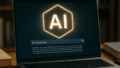
コメント