日本人とカツオだしの深い歴史を知ると、毎日の味噌汁が特別になる
2025年11月12日に放送された NHK総合『歴史探偵』「ニッポン カツオだし浪漫」 では、日本人とカツオの長い歴史が徹底的に調査されました。この記事では、番組内容をもとに、古代の天皇が味わったカツオスープから、江戸時代に庶民まで広まっただし文化までを小学生にもわかる言葉で丁寧に紹介します。
カツオだしの歴史を知ると、ふだんの料理がもっと面白く感じられるはずです。
NHK【明日から使える プロの食材術(3)】干しシイタケは戻さず使える!冷凍きのこでうま味倍増テク|2025年4月14日放送
奈良時代の天皇が味わっていた“カツオのスープ”の正体
古代の日本では、カツオは非常に貴重な食材として扱われていました。
そのことを示す決定的な証拠が、奈良文化財研究所に保管されている木簡です。
木簡には「堅魚(かつお)」の文字がはっきりと記され、伊豆や駿河の海から平城京へと運ばれていた事実が分かります。
当時の運搬は徒歩・船・牛馬を使っても、約20日前後はかかる長い旅でした。それでも平城京の天皇や上級貴族の食卓に供され続けていたということは、カツオがどれほど“特別な食材”だったかを雄弁に物語っています。
さらに驚くべきことに、そのカツオのスープは
天皇や限られた上級貴族だけが味わえる“特別な御膳”
だった可能性が高いと紹介されました。
古代人の知恵「塩鰹」は保存性と旨味の結晶
ここで登場したのが、古代の保存技術である『塩鰹』です。
この塩鰹を解説したのは、古代食文化を専門とする 三舟隆之 特任教授。
カツオの内臓を取り除き、1匹につき約2kgもの塩でしっかり塩漬けにするという、非常に手間がかかる保存法です。
この塩鰹はそのまま食べるのではなく、切り身をご飯に乗せ、お湯を注いで溶かすことで、旨味と塩味が広がる“古代のお茶漬け”として楽しまれていた可能性があると紹介されました。
さらに、塩鰹は今でも富士山に奉納される伝統が続いており、カツオが古代人にとって“特別な食材”として崇められてきた背景が鮮やかに浮かび上がります。
駿河湾を黒く染めたカツオの群れ
番組では、古代の文献をひもといて「駿河湾が黒く染まるほどのカツオの大群が押し寄せた」という記録も紹介されました。
当時の日本人はこの現象を“天からの恵み”として受け取り、命を支える大切な食材としてカツオを特別視していたようです。
豊かな海に支えられた古代日本の生活を想像すると、カツオが特別な意味を持った理由が直感的に理解できます。
謎の液体『堅魚煎汁』を再現する壮大な試み
木簡には、もうひとつ気になる言葉が残されています。
それが『堅魚煎汁(かつおのせんじじる)』です。
これはカツオを煮出し、さらに煮詰めた濃縮エキスだと考えられていますが、文献が少なく、その正体は長く謎とされてきました。
番組では、三舟隆之教授のほか、栄養学・考古学の専門家、そしてカツオの漁のプロが協力し、本気の再現に挑みました。
再現では海水を煮詰め、塩分濃度を高め、腐敗しにくい状態を作り出す方法を試験。塩分濃度が15%に達すると、常温でも腐らない保存液になることがわかり、長期輸送に耐える理由が明らかになりました。
しかし古代は鉄鍋ではなく“土器”が使われていたため、ひび割れや大量の薪が必要で、相当な重労働。
古代人の“食への執念”が伝わってくる場面でした。
スタジオで味わう“古代スープのリアルな味”
再現された堅魚煎汁は、スタジオにも2種類登場しました。
・カツオのアラを使ったもの
・アラを使わず、身から煮出したもの
佐藤二朗は試飲後、
「和食の原点を見た気がする」
「古代と現代がつながったように感じる」
とコメント。
スタジオの空気が一気に“古代の食卓”へタイムスリップしたようでした。
さらに、春に採れるワカメも天皇の食卓に並んでいたと紹介され、季節と海の恵みの結びつきも描かれました。
平城京跡から見つかった“古代のペットボトル”
平城京跡からは、徳利のような形をした土器も多数発見されています。
これについて 奈良文化財研究所の小田裕樹 は、土器の窯跡が伊豆・駿河にしかないことから、これらは
“堅魚煎汁を入れて運ぶための容器だったのではないか”
と話しました。
まさに“古代のペットボトル”。
そこからも、カツオだしがいかに重要だったかが読み取れます。
木簡には『古自(こじ)』という香草の名前もあり、これはいわば“国産パクチー”のような存在と解説されました。
番組内ではこの香草を使ったスープの再現にも挑戦し、古代の食文化の豊かさを体感できる内容となっていました。
江戸時代にカツオだしが庶民へ広がるまで
ここから時代は大きく進み、江戸時代へ。
カツオだしが日本全国へ広がる大きなきっかけとなったのが、鰹節の発展です。
土佐から 徳川家康 へ贈られた記録も残っており、カツオ文化が武家社会へ一気に浸透しました。
物流革命「菱垣廻船」がだし文化を全国に運んだ
1619年に運航を開始した『菱垣廻船』は、生活物資や食品を大量に運ぶ大型の船でした。
この船は“人気商品を早く届けるレース”まで行われるほどの需要を背負い、鰹節はその中でも特に人気の品として扱われていました。
さらに、各地が品質競争を行い、“鰹節番付表”まで作られました。
ただし秘伝の技を他に漏らした職人は、二度と故郷に戻れないという厳しい掟もあり、それほどに技術は重んじられていたのです。
江戸庶民を支えた「だしかけ」という知恵
江戸時代後期になると、料理本が多数出版されました。
料理研究家の 車浮代 は、
「ご飯は1日1回しか炊かないため、冷やご飯を美味しく食べるために“だしかけ”文化が生まれた」
と説明。
また 福留奈美 によると、カツオだしと味噌の組み合わせが庶民に一気に広がり、現代の“味噌汁文化”の原型になったと紹介されました。
この“だしかけ文化”こそが、カツオだしを一般家庭へ定着させた大きな要因といえます。
和食の発展を支えたのは海の豊かさと人々の努力
スタジオでは 河合敦 が、
「江戸時代が平和で、豊富なカツオが獲れたからこそ和食が発展した」
と解説。
最後に 佐藤二朗 は、
「海の恵みに感謝したい」
と語り、今回の長い調査は静かに締めくくられました。
この記事のポイントをおさらい
・奈良時代の天皇はカツオのスープを味わっていた
・塩鰹や堅魚煎汁など、保存と輸送の知恵が古代から確立していた
・江戸時代には鰹節の発展と物流革命が起こり、庶民の食卓にだし文化が広がった
1300年以上続く“カツオだし”の物語には、海の恵みと人々の努力がしっかりと刻まれています。
今日の味噌汁や煮物が、いつもより香り豊かに感じられる知識になったはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

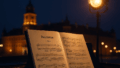
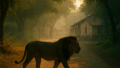
コメント