駅が語る100年の物語に心を寄せて
最北の無人駅として知られてきた北海道・宗谷本線の抜海駅(ばっかいえき)。鉄道ファンの間では「日本最北の木造駅舎」として親しまれてきました。今年3月、この駅が100年の歴史に幕を下ろしました。
吹きすさぶ北風の中で、駅が見つめてきたのは人々の人生そのものでした。戦争、別れ、愛、そして静かに進む時代の流れ。そのひとつひとつに、駅はただ黙って寄り添ってきたのです。
この記事では、抜海駅が語る“100年の物語”を通して、私たちが忘れかけている「土地と記憶のつながり」をたどっていきます。
NHK【時空鉄道〜あの頃に途中下車〜】京葉線・東京駅ホームはなぜこんなに遠い?貨物線ルーツに隠された驚きの理由|2025年10月13日
吹雪の日も、人を送り出し迎えた駅
抜海駅の開業から約20年後、日本は戦争の時代に突入しました。
番組では、駅から戦地へと送り出されたある少年のエピソードが紹介されます。彼は村の人々の万歳三唱に送られ、列車に乗って旅立ちました。
しかし、その帰りは“無言の帰郷”。棺を乗せた列車が抜海駅に着いたとき、誰もが声を出せず、ただ線路沿いで静かに見守るしかなかったといいます。
雪が降り積もる中、汽笛の音だけが空に響いたあの日。駅は、戦争の悲しみと、人々の祈りを見つめる“証人”となったのです。
こうした別れの風景は、抜海駅だけでなく、戦時下の日本各地にあった鉄道の記憶を思い起こさせます。けれども、北の果てで吹雪に耐えながら立ち続けた抜海駅の存在は、その象徴のようでもありました。
“待ち続ける人”の記憶を宿す駅
もう一つ、心に残るのが99歳の女性の証言です。
若き日に夫を駅で見送り、それから何十年ものあいだ、毎年その日になると線路の先を見つめてきたという女性。彼女にとって駅は、思い出と祈りの場所でした。
冬には雪をかき分けてホームへ行き、夏には花を供えたといいます。そこには、戦争で失われた“日常”を取り戻そうとする静かな願いがありました。
駅のベンチに腰掛けた彼女の視線の先にあるのは、もう動かない線路。けれど、その目には“生きてきた証”が映っていたのです。
番組は、そんな人間の想いが染み込んだ駅舎の木目や風の音を丁寧に描き出します。
変わりゆく鉄道の時代を見届けた駅
抜海駅の100年は、まさに日本の鉄道史そのもの。
戦後の復興期、そして高度経済成長を経て、鉄道は再び地方の交通の要として機能しました。しかし1987年、国鉄の民営化によって、駅の運営方針や人員配置が大きく変化します。
抜海駅もその波にのまれ、無人化されました。駅を守ってきた職員たちは、寂しさを胸に去っていきました。
彼らは、国鉄マンとして鉄道を誇りに思い、吹雪の中でも列車を遅らせないよう懸命に働いてきました。
番組では、当時を知る元職員たちが「駅を離れても、抜海の雪の匂いは忘れられない」と語ります。
それは、ただの勤務先ではなく、“人生そのもの”だったのです。
無人駅としての静かな日々
無人化された後も、抜海駅には鉄道ファンが訪れ続けました。
木造駅舎の天井にはツバメの巣があり、ベンチには地元の人が手作りのクッションを置いていた時期もありました。
列車の待ち時間には、旅人同士が会話を交わしたり、カメラを構えたり。駅は小さな交流の場でもあったのです。
けれど、利用者は次第に減少。令和初期には1日あたり2人前後という数字が報じられました。
それでも、駅を訪れる人の表情は穏やかで、どこか満たされていました。
誰もいないホームに立つだけで、過ぎ去った時間と向き合える。抜海駅には、そんな“時を超えた静けさ”がありました。
そして迎えた“最後の日”
2025年3月14日、ついに抜海駅は廃止を迎えました。
最終列車の発車を見送るため、全国から鉄道ファンや地元住民が集まり、カメラを手にその瞬間を焼き付けました。
駅前には「ありがとう抜海駅」と書かれた横断幕と花束が並び、長年通学で利用した人々も涙を浮かべていました。
地元では「抜海駅100周年記念実行委員会」が結成され、記念イベントが開催されました。
人が減っても、駅は“地域の誇り”であり続けたことを証明する光景でした。
列車が去った後、ホームに残るのは風の音だけ。しかしその風は、どこか温かく、まるで駅が「ありがとう」とつぶやいているように感じられました。
駅が教えてくれる“記憶の力”
抜海駅の物語は、単なる鉄道の歴史ではなく、人間の記憶と土地の絆を描いたものです。
「駅が語る」とは、つまり人がその場所に残した想いを感じ取ること。
雪の降るホームで別れを経験した人、誰かを見送った人、静かに待ち続けた人――その一人ひとりの記憶が、この駅舎の木に、風に、音に、染み込んでいます。
そして、駅の廃止は“終わり”ではなく“受け継ぎ”の始まり。
抜海駅を訪れた人々の記憶は、写真や記録、そして語り継ぎによって生き続けるでしょう。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・抜海駅は1924年に開業し、2025年に100年の歴史を閉じた日本最北の無人駅
・戦争・民営化・過疎化という激動の時代を通じ、人々の記憶を見つめ続けてきた
・廃止後も“地域の記憶と誇り”として、多くの人の心に残り続けている
吹雪に耐えながら立ち続けた駅舎は、100年間ものあいだ、人間の喜びや悲しみを静かに受け止めてきました。
列車が去ったあとも、そこには確かに“人の時間”が流れていました。
この番組を通じて、私たちは改めて「風景の中に生きる記憶」というものを感じることができるでしょう。
放送日時:2025年11月15日(土)23:00〜24:00
放送局:NHK Eテレ(ETV特集)
※番組の内容と異なる場合があります。
参考・出典リンク
・ウィキペディア「抜海駅」[https://ja.wikipedia.org/wiki/抜海駅]
・トラベル Watch「日本最北の木造駅舎“抜海駅”が100年の歴史に幕」[https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1659345.html]
・note「最北の無人駅・抜海駅を訪ねて」[https://note.com/osatsu_journey50/n/n8ffb56f3374f]
・稚内・利尻・礼文観光WEBサイト「抜海駅(ばっかいえき)」[https://www.north-hokkaido.com/spot/detail_1103.html]
・メルクマール「最北の無人駅・抜海駅が廃止へ」[https://merkmal-biz.jp/post/18461/3]
・2nd-train「宗谷本線抜海駅が廃止」[https://2nd-train.net/topics/article/63490/]
・稚内プレス「抜海駅100周年記念実行委員会の取り組み」[https://wakkanaipress.com/2025/03/13/76058/]
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

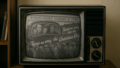

コメント