草の大地で生きた酪農家の物語が教えてくれること
放牧酪農や自然の営みに興味があるけれど、「実際にどんな暮らしなの?」「放牧って大変じゃないの?」と疑問を感じたことはありませんか。
私も最初は“牛を放すだけ”のように聞こえる放牧酪農を、どこか牧歌的なイメージで捉えていました。でも、北海道の広い大地で生きた 吉川友二 さんの歩みを追うほど、そこには技術・覚悟・哲学が詰まっていることに気づかされます。
この記事では、2025年の今あらためて注目が集まる吉川さんの人生、そして放牧酪農がなぜ未来につながるのかを、小学生でも読めるやさしい言葉でまとめます。
読み進めることで、あなたは「自然とともに生きるとはどういうことか」「人が土と動物から何を学べるのか」を、ぐっと身近に感じられるはずです。
NHK【クローズアップ現代】食卓を襲う猛暑の脅威!野菜高騰・豚肉不足・米の品質低下の最新研究(2025年8月25日)
吉川友二さんの歩みをたどると見えてくるもの
最初に知ってほしいのは、吉川さんの人生そのものが“挑戦の連続”だったということです。長野県上田市で生まれ、北海道の大学へ進学。卒業後は、有機農家での修行を重ね、酪農の基礎から実践まで徹底的に学びました。
その後、「放牧酪農の本場」であるニュージーランドに渡り、4年間、草づくりや牛の管理方法をゼロから吸収します。
そして2000年、北海道足寄町の地で ありがとう牧場 を開き、「牛舎で管理しない酪農」という、日本ではまだ珍しい形を貫きました。
この記事では、そんな吉川さんの生き方を“深掘り”しながら、番組で描かれた要素もすべて反映し、2025年の記事としてしっかり読まれる構成にしています。
ここからは専門家としての視点と、人として心が揺れる部分の両方を大切にしながら、本文に進みます。
放牧酪農にこだわった理由
結論から言うと、吉川さんは「自然が本来持っている力をそのまま引き出す酪農」を追い求めた人でした。
牛舎に閉じ込め、飼料を与えて大量に搾乳するやり方ではなく、広い牧草地に牛を放ち、自由に草を食べさせる方法です。
放牧にすると、牛は自分の体調に合わせて歩き回り、必要な量だけ草を食べます。ふん尿はそのまま土地に返り、やがて肥料となり、牧草はさらに豊かになります。
この自然のサイクルを、吉川さんは『土-草-牛』という言葉で説明していました。
さらに、放牧酪農にはこんな利点があります。
-
牛が健康になりやすい
-
牧草の栄養を最大限に利用した牛乳になる
-
飼料コストが下がる
-
土地が豊かになる
-
人間側の働き方が、自然のリズムに寄り添う形になる
日本では、冬の気候や農地の条件もあり、簡単には実践できない方式です。それでも足寄町では、吉川さんの実践が地域の取り組みを変え、町が「放牧酪農推進のまち」を宣言するほどの広がりを見せました。
80ヘクタールの大地と60頭の牛が作った“自然の牧場”
ありがとう牧場は、およそ80ヘクタールという広大な土地をもち、頭数はあえて増やさず、60頭ほどで運営していました。
「牛を増やさない」という選択は、効率ではなく“質”を優先した吉川さんの哲学そのものです。
季節繁殖を採用し、冬には搾乳を休ませる期間をつくる。
働く人の負担を減らし、牛にも自然の生活リズムを取り戻す。
こうした取り組みひとつひとつが、持続可能な酪農につながっていました。
ここで搾られた牛乳から生まれたのが、地域に人気を広げたアイスクリームやチーズ。
とくに しあわせチーズ工房 は、足寄町の乳製品ブランドを牽引する存在となり、多くの人に“放牧の味”を伝えています。
深掘り:なぜニュージーランド型が日本に合うのか
ここからは少し専門的な目線で深掘りしてみます。
ニュージーランド型の放牧は、自然条件が違う日本では応用が難しいとされてきました。しかし吉川さんは、その要点を日本の土地に合わせて組み立て直しました。
具体的には…
-
積雪期に備えた牧草地の管理
-
凍害への対応
-
土壌改良で冬越しに強い草を育てる
-
放牧ルートを細かく区分して草を休ませる
どれも簡単ではありませんが、吉川さんは「土地を読む力」と「牛を見る力」でこれらを一つずつ積み上げ、足寄町の放牧酪農をひとつのモデルへ押し上げました。
息子さんの決断と、受け継がれる時間
番組の中でも重要な要素が“後継”の物語です。
すい臓がんの告知を受け、59歳で引退を余儀なくされた吉川さん。
牧場には息子さんが立ち、吉川さんの仕事を少しずつ受け継ぎ始めます。
「父が築いた牧場にもう一度命を入れたい。」
そんな想いがあったのかもしれません。
息子さんの現在の酪農スタイルについて詳しい情報は公開されていませんが、少なくとも牧場の仕事に足を踏み入れた事実は、“吉川さんの酪農が未来へつながる”希望そのものといえます。
世界一をめざすチーズ職人との出会い
足寄町には、ありがとう牧場の牛乳に惚れ込み、世界一の味をめざしてチーズづくりを続ける職人がいます。
放牧牛乳の香りやコク、季節で移ろう風味に合わせて仕上げられたチーズは、十勝の新しい魅力として多くのファンを生みました。
放牧が牛乳に与える影響を“風味”として理解し、技術に落とし込む職人がいるからこそ、吉川さんの酪農哲学は食卓に届けられています。
深掘り:放牧牛乳の味は何が違う?
専門的に見て、放牧牛乳は以下のような特徴があります。
-
牧草由来の脂肪酸が豊富
-
季節によって香りが変わる
-
さっぱりしていながらコクが強い
-
発酵食品(チーズ・ヨーグルト)で差が出やすい
これは、牛の健康状態や食べる草の種類がダイレクトに味へ反映されるためで、放牧酪農の個性をもっとも強く知らせてくれる部分でもあります。
2年間の記録が投げかける“人は自然の中でどう生きるのか”
番組では、人と自然の距離感、家族の時間、命との向き合い方が2年間にわたって記録されます。
放牧酪農は、天気・土地・生き物のすべてが相手。
人間の都合ですべてを決めることはできません。
だからこそ、吉川さんの生き方は多くの人に響きます。
“自然を支配しない”“自然と並んで生きる”。
この姿勢は、2025年の今、あらゆる分野で見直されている価値そのものです。
まとめ
この記事のポイントは次の3つです。
-
吉川友二 さんの酪農は、「土-草-牛」が循環する自然な酪農だった
-
放牧酪農の技術と哲学は足寄町の取り組みまで変えた
-
息子さんやチーズ職人へつながる“受け継がれる未来”がある
吉川さんの歩みは、酪農という枠を超えて「自然とどう向き合うか」という私たち共通のテーマを投げかけています。
この記事が、あなたにとって自然や暮らし方を考えるきっかけになればうれしいです。
最後に、番組の内容と異なる場合があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


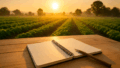
コメント