まさかの想定外が…がんとお金のリアル
2025年4月30日(水)朝8時15分からNHK総合で放送される『あさイチ』では、がん治療にかかる「想定外のお金」に焦点を当てます。がんは早期発見すれば安心と思われがちですが、治療や検査に思わぬ費用がかかることが少なくありません。今回の放送では、がんを経験した人たちが直面したリアルなお金の問題、保険の落とし穴、今どきの治療費事情、公的支援制度の活用方法まで幅広く取り上げます。
想像以上!治療費以外の“見えない出費”とは?
今回の特集では、がん治療にともなう「治療費以外の思わぬ出費」について、首都圏で暮らす佐野さんの具体的な体験が紹介されました。佐野さんは7年前、ステージ4の乳がんと診断され、パートの仕事を続けながら抗がん剤治療や手術、通院を長期間続けてきました。治療そのものにも多くの費用がかかりましたが、それ以上に家計を圧迫したのが日常生活で必要となった予想外の出費だったといいます。
術後、佐野さんはリンパ浮腫という後遺症に悩まされ、腕のむくみや痛みにより、重いものを持つことが難しくなってしまいました。この変化に対応するため、これまで使っていた調理器具やキッチン用品をすべて軽量タイプのものに買い替える必要が生じたのです。たとえば、大きな鍋や鉄製のフライパンは使えなくなり、ステンレスや樹脂製の軽い製品に変えるなど、生活の道具を一から見直す必要がありました。
さらに、リンパのケアに必要な専用の医療用スリーブや弾性包帯、マッサージ機器なども日常的に必要になりました。これらは病院で処方されるものとは別に、自費で購入する必要があり、品質の良いものは高価です。その他にも、外出時のサポート用バッグや、むくみを避けるための衣類の買い替えなども加わり、少しずつ、しかし確実に出費がかさんでいきました。
その結果、治療費とは別にかかった費用は7年間で総額125万円にのぼったと報告されています。これは1年あたりに換算しても約18万円と、家計にとっては無視できない金額です。
佐野さんの例は特別なものではなく、全国のがん患者・家族を対象としたアンケート結果でも、治療費以外にかかる費用の年間平均が約55万円であることがわかりました。この中には、次のような多岐にわたる支出が含まれています。
-
通院や検査のための交通費(タクシーや高速代などを含む)
-
遠方の専門病院に通う際の宿泊費や食費
-
病室での冷えを防ぐための専用衣類や寝具
-
家の段差をなくすための住宅リフォームや手すりの設置
-
体力の低下にともなう家事代行サービスや宅配弁当の利用
-
抗がん剤の副作用による脱毛に対応した医療用ウィッグや帽子の購入
-
長期入院時に家族が交代で病院に通う際の有休取得や収入減少の補填
こうした支出は、病気そのものに直接関係がなくても、患者が日常生活を維持するために必要不可欠な出費です。そして多くの場合、これらは医療保険や高額療養費制度の対象外となり、自費で賄わなければなりません。
見えにくいけれど確実に家計を圧迫するこれらの費用は、治療が長引くほど増えていく傾向があります。とくに一人暮らしや共働き世帯、高齢世帯では、日常生活にかかる負担をサポートする費用の準備がより重要になります。
治療費だけではなく、「暮らしにかかるコスト」も含めて備えておくことが、安心して治療に向き合うために必要な現実的な対策なのです。事前にどんな支出があるかを想定し、必要なときに必要な支援を受けられるよう準備しておくことが、経済的・精神的な負担を軽くする第一歩となります。
保険と支援制度の見直しで差が出る!
がん治療にかかる費用は非常に高額であり、家計への影響は決して小さくありません。そんなときに力になってくれるのが公的支援制度や民間の保険ですが、それらをどこまで理解し、適切に活用できるかによって支出に大きな差が生まれます。
まず注目すべきは、高額療養費制度です。これは1か月の医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合、その超過分が後日払い戻される制度です。たとえば、年収が約370万円から770万円の人であれば、自己負担の上限は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」となり、それ以上の費用については返金されます。つまり、どれだけ高額な治療でも、制度を使えば負担を大幅に軽減できる可能性があるのです。
-
この制度は「自動的に適用されるものではなく、申請が必要」です
-
支給には領収書や保険証などの提出が必要になるため、事前に書類の準備をしておくことが重要です
-
よりスムーズに対応したい場合は、「限度額適用認定証」を事前に取得しておけば、窓口での支払いを抑えることができます
また、会社員や公務員として働いている人の中には、健康保険組合に加入していることで「付加給付」が受けられる場合もあります。これは高額療養費制度の上限額よりもさらに少ない金額で済む制度であり、
-
自己負担が月2万円台に抑えられる組合もある
-
扶養家族にも適用される場合があり、世帯全体の医療費が軽減される
ただし、これはすべての加入者に自動で適用されるわけではなく、制度の存在を知らなければ何の恩恵も受けられません。自分の健康保険証に記載されている組合名を確認し、その公式サイトや相談窓口で付加給付の内容を調べておくことが大切です。
一方、民間のがん保険や医療保険も、備えとして重要な役割を果たしますが、契約内容を定期的に見直さなければ、いざというときに保障が不十分だったということになりかねません。とくに注意すべきなのが次のような項目です。
-
診断給付金が1回限りの契約では、再発時の保障が受けられない
-
通院治療が保障の対象外になっていると、現代のがん治療の主流に合っていない
-
自由診療や先進医療に非対応のプランでは、最新治療にアクセスできないリスクもある
こうした条件を知らずに「保険に入っているから安心」と思い込んでしまうと、実際にがんになったときに思っていたような給付が受けられないという悲しい事態に直面してしまいます。
だからこそ、
-
加入している保険の保障範囲と給付条件を年に1回は見直す
-
保険証券や契約内容を紙でもデジタルでもすぐ確認できるように保管
-
不明点は保険会社やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談する
といった行動を取っておくことが、将来の安心につながります。保険は契約して終わりではなく、ライフステージや治療法の進化に合わせて柔軟に見直すべき備えです。
制度と保険、どちらも正しく知って賢く使えば、がん治療の経済的負担は大きく軽減できるのです。何もしないままでは差がつき、備えた人だけが安心を手に入れることができます。
小テストで再確認!今すぐできる“がんとお金”の備え
放送の後半では、視聴者が自分の理解を深められるよう「小テスト形式」でがんとお金に関する重要なポイントがおさらいされました。内容は非常に実用的で、誰でもすぐに実行できる備えについて、確実に押さえておくべき4つの基本が紹介されました。
まず1つ目は、高額療養費制度の自己負担限度額をあらかじめ確認しておくことです。自分がどの所得区分に当てはまるかによって、月々の医療費の上限が異なります。たとえば、年収370万〜770万円の人の場合、自己負担は約8万円台で済みます。事前に知っておけば、いざというとき慌てずに済み、「お金が足りないから治療を迷う」という不安を減らせます。
-
各所得区分ごとの上限額は全国共通で決められており、厚生労働省や保険組合のサイトで確認可能
-
窓口負担を抑えるには、限度額適用認定証をあらかじめ取得しておくのが理想
2つ目は、自分の加入している健康保険に「付加給付」があるかを調べておくことです。これは高額療養費制度よりもさらに手厚い給付を受けられる制度で、主に企業の健康保険組合に見られます。知らずに通常の申請だけをしていると、本来受けられる給付を取りこぼしてしまうこともあります。
-
付加給付があると、自己負担が1〜2万円程度に抑えられることも
-
加入している保険組合のホームページや総務部門で確認可能
3つ目の備えは、がん保険・医療保険の契約内容を定期的に見直すことです。診断給付金が1回限りだったり、入院しか保障されていない古い契約では、現在の通院中心の治療には対応しきれません。「保険に入っているから大丈夫」と思い込まず、実際に何が対象で何が対象外か、保障範囲を細かくチェックしておく必要があります。
-
給付金の支給回数、通院・自由診療の対応有無などを確認
-
がん治療が長期化することも考えて、再発時の保障の有無も重要なチェックポイント
そして4つ目の備えは、医療費だけでなく、日常生活の変化にともなう出費も見越して準備しておくことです。治療中は体力が落ちることで、食事の準備や掃除、洗濯などが思うようにできなくなります。さらに、通院のための交通費や付き添いの家族の宿泊費、必要な日用品の買い替えなど、暮らしの質を保つための支出が想像以上にかかってくるのです。
-
配食サービスや家事代行、介護用品など生活支援サービスの検討も重要
-
在宅治療や通院治療が中心になることで、日々の生活費に変化が生まれることを前提に家計を見直す
がん治療は、「病院での治療にかかるお金」だけでは語れません。治療中も日常は続くという現実を受け止め、食事・移動・身の回りのケアといった広い視点での準備が必要です。特にひとり暮らしや共働き世帯では、助けが得にくい分、支援制度や民間サービスの活用を前提とした計画を立てておくことが大切です。
今回の小テストを通して伝えられたのは、「知っているか知らないかで、安心に大きな差が生まれる」という事実です。今すぐにでも確認できる項目ばかりなので、今日から1つずつチェックを始めてみてください。備えは行動から。自分と家族を守るのは、事前の知識と準備です。
いまオシ!LIVE 北海道・森町 駒ヶ岳を背にした桜の絶景中継
今回の「いまオシ!LIVE」では、北海道・森町にある公園から、桜の見頃を迎える美しい風景が生中継で届けられました。背景には雄大な駒ヶ岳がそびえ立ち、春の澄んだ空気の中で山と桜が織りなす絶景が広がっています。この時期の森町では、地域ならではのさまざまな種類の桜が咲きそろい、春を彩る自然のショーが見られます。
中継時点では、染井吉野が7分咲きとなっており、これからまさに満開を迎えるタイミングでした。染井吉野は日本全国で親しまれている代表的な桜ですが、森町ではそれに加えて、北海道ならではの品種も数多く見られるのが特徴です。
-
千島桜(ちしまざくら):北海道の北東部でよく見られる桜で、花びらはやや小さめながらも色が濃く、力強さを感じさせる品種です
-
蝦夷山桜(えぞやまざくら):北海道の広い範囲で見られる桜で、花色は濃いめのピンク。葉と同時に花が開く特徴があり、自然の生命力を感じさせる姿が魅力です
-
駒見桜(こまみざくら):駒ヶ岳の景色とともに楽しめる地元で親しまれている桜で、山と桜を一緒に見渡せる絶好のロケーションに咲いています
さらに注目されたのが、堀井緋桜(ほりいひざくら)という珍しい桜の存在です。この桜は、もともと堀井さんという方のお墓に自然に生えていた1本の桜から始まりました。その花のあまりに美しい緋色の色合いが地元の人たちの心を打ち、「この桜をもっと多くの人に見てもらいたい」との思いから、増やされることになりました。
-
現在、公園には約30本の堀井緋桜が植えられており、そのどれもが濃いピンク色の花をつけ、訪れる人々の目を楽しませています
-
堀井緋桜は他の桜と比べて色が濃く、特に曇り空や夕暮れ時に際立つ美しさがあるといわれています
-
墓地にあった1本の桜が、今では森町を代表する地域の宝として育てられているという物語が、人々の心に残ります
このように森町では、ただの桜鑑賞ではなく、それぞれの桜の歴史や背景を感じながら花を楽しめる特別な体験ができます。桜の種類ごとに色や咲き方、咲く時期も少しずつ異なるため、訪れるタイミングによって毎回違った風景と出会えるのも魅力です。
満開を迎えるこれからの時期、駒ヶ岳の雄姿を背景に、風に揺れる多様な桜の花びらを眺める時間は、まさに心がほどけるひととき。北海道・森町の春が見せてくれる、壮大で繊細な景色に、視聴者からも注目が集まりました。中継は映像だけでなく、現地の空気感や季節の移ろいまでが感じられる内容となり、画面越しでも春を存分に味わえる時間となっていました。
みんなゴハンだよ!旬の若竹ごはんとたけのこ入り豚つくね
「みんな!ゴハンだよ」コーナーでは、春の食材「たけのこ」と「わかめ」をふんだんに使った、旬を味わう二品が登場しました。紹介されたのは、香り豊かで食感も楽しい「若竹ごはん」と、シャキッとしたたけのこの歯ざわりが楽しい「たけのこ入り豚つくね」です。季節感を大切にしたやさしい味つけで、春の食卓を彩るレシピとなっています。
いまオシ!REPORT 東京・北区で進化を続ける“たわし”の魅力に迫る
今回の「いまオシ!REPORT」では、東京・北区にある100年以上の歴史を持つ“たわし工場”に注目。長年にわたって受け継がれてきた職人の技と、現代のニーズに合わせて進化を続けるたわしの世界が紹介されました。掃除道具としてだけでなく、ボディケア用品としても注目されているたわしの、知られざる魅力が明らかになりました。
訪れたのは、都内でも数少ない手作業によるたわしづくりを続けている老舗工場。ここでは、熟練のたわし職人・関谷さんが作業を担当しており、その製法やこだわりを案内してくれました。
たわしの素材には、
-
シュロの繊維(やわらかくしなやか)
-
ココナッツの繊維(硬くてしっかりした洗浄力)
など、自然素材が使われています。天然素材ならではの感触や吸水性が、使うほどに手に馴染んでくるのが特徴で、それぞれの用途に応じて選ばれています。
すべてが手作業で製造されるため、仕上げの検品作業が欠かせません。この工場では1日になんと約5000個のたわしを検品しており、形やバランス、繊維の整い具合まで細かくチェックして出荷されます。1つひとつに職人の目と手が行き届いた品質管理が、100年以上続く信頼の理由です。
次に訪れたのは、たわし工場に併設された専門ショップ。ここでは掃除用だけでなく、近年特に注目されているボディたわしが並び、人気を集めています。ボディたわしは、肌に直接使えるように4段階の硬さが用意されており、デリケートな肌や小さなお子さまでも安心して使える柔らかさから、しっかりとした洗い心地の硬めタイプまで幅広く展開されています。
-
柔らかめ:赤ちゃんや高齢者の肌にやさしいタイプ
-
中間タイプ:日常使いにちょうどよいバランス
-
硬め:角質ケアや足裏などのしっかり洗いに最適
-
超硬め:汚れの多い部分や水まわり掃除にも応用可能
このように、たわしは「汚れを落とす道具」から、「暮らしに寄り添うケアアイテム」へとその用途が広がっています。職人の技と時代のニーズが融合して生まれた新しいたわしの形に、多くの来店者が驚きと関心を寄せていました。
100年を超える伝統を守りながら、使う人の暮らしに合った製品を提案し続けるたわし工場の挑戦は、これからも注目を集めそうです。ものづくりの現場を見つめ直すことで、私たちの暮らしの中にもまだ知らない「良い道具」があることに気づかせてくれる特集でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

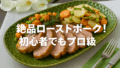

コメント