金利と家計の不安・初夏の京都グルメと絶景・鴨川納涼床と映画の町太秦まで大特集
2025年5月22日放送のNHK「あさイチ」では、家計に直結する金利上昇の話題から、初夏の京都の絶景、人力車や納涼床の楽しみ方、太秦の映画文化まで幅広い内容が紹介されました。ゲストには俳優の中島歩さん、タレントの坂下千里子さんを迎え、実際の体験を交えながらわかりやすく伝えられました。料理コーナーでは初夏にぴったりな食材を使ったレシピも登場。生活に役立つ情報と旅気分が同時に味わえる内容でした。
金利上昇で家計はどう変わる?影響と今できる対策を整理

今、日本の金利がゆっくりと上がり続けています。とくに注目されているのが定期預金と住宅ローンへの影響です。東京都港区にある銀行では、定期預金の相談件数が通常の5倍以上に増加しており、0.9%という高めの金利を提示しているケースもあります。背景には、2024年3月以降に始まった日銀の政策金利引き上げがあり、現在の政策金利は0.5%に達しています。この動きによって、金融機関間での預金獲得競争が活発化しているのです。
家計にとってより大きな影響が出るのが住宅ローンです。番組ではファイナンシャルプランナーの八木陽子さんが、実際の数字を挙げて具体的に説明していました。たとえば、以下のような条件の住宅ローンでは、金利の変動によって返済額が大きく変わります。
-
借入額:5000万円
-
ローン期間:35年
-
変動金利型ローン
この条件で金利が1%上がり、年1.595%になると、月々の返済額が2万4204円増加します。年間では約29万円の負担増です。これは日々の生活に直結する大きな数字で、家計にとっては無視できない変化です。
また、最近注目されているのが、預金キャンペーンとリスク商品のセット販売です。高金利をうたう商品に申し込もうとすると、実は投資信託などとセットになっている場合があります。これにより元本割れのリスクを背負うことにもなりかねないため、キャンペーン内容の詳細確認が必須です。
現在すでに住宅ローンを組んでいる人ができる対策としては、以下のような行動が紹介されました。
-
返済額の将来シミュレーションを行う
-
ボーナス時期などに繰り上げ返済を検討する
-
金利の動向をこまめにチェックする
-
金融機関に相談して固定金利型などへの変更も含めた比較をする
特に変動金利型のローンは、金利が上がれば支払額も自動的に増える仕組みです。そのため、金利のわずかな上昇が数万円単位の負担増につながることを意識しておく必要があります。
今後の経済の動き次第では、金利がさらに上がる可能性もあるため、早めに対策を講じておくことが安心につながります。このように、金利上昇は預金者にとってはチャンスになる一方、借り入れをしている人にとっては家計の見直しが求められるタイミングでもあります。賢く動くことで、将来の不安を少しでも減らしていくことが大切です。
中島歩さんが巡る嵐山の絶景と祈りの地・初夏の京都を味わう旅

俳優・中島歩さんが案内役となり、初夏の京都を訪ねるロケが放送されました。舞台は、青もみじがまぶしい季節を迎えた京都・嵐山エリア。最初に向かったのは、観光の定番スポット渡月橋から続く「竹林の小径」です。歩いて巡るルートと人力車のルートがありますが、今回は人力車に乗って体験する竹林風景が紹介されました。
人力車で進むルートは、一般の徒歩ルートとは異なる角度で竹の高さや密度を体感でき、パノラマで眺める竹林は幻想的な雰囲気。この竹林の美しい景観は、天龍寺が整備を担当しており、管理に携わる庭師・平木信行さんによれば、竹は成長が早いため、年間50~100本を計画的に間引くことで風景の保全が行われているそうです。こうした観光の裏側を支える職人たちの努力にも焦点が当てられていました。
竹林のあとは、嵐山で人気のスイーツ店へ。訪れたのは綿菓子専門店で、提供されているのはいちご、京抹茶ラテ、ほうじ茶ラテなど7種類のフレーバー。特に注目されたのは、綿菓子の棒に使用されている竹が、嵐山の竹林で間伐された資源であるという点です。地元の素材を無駄なく使う工夫と環境への配慮が、見た目の可愛らしさと共に高く評価されています。
続いて中島さんが向かったのは、京都の奥に佇む静かな寺院祇王寺。ここでは、新緑の青もみじと苔が絨毯のように広がる景色が紹介されました。この寺は、50種類以上の苔が自然のままに育つ珍しい場所で、四季折々で表情を変える自然美が訪れる人を癒してくれます。さらに、良縁祈願の地としても知られ、連続テレビ小説「あんぱん」のロケ地にもなっている場所です。
中島さんは旅を振り返り、「気温がちょうどよくて、暑くも寒くもない本当にいい季節だった」と語りました。初夏の京都は湿度が低く、新緑も鮮やかでまさに旅にぴったりのタイミングです。
また、スタジオでは坂下千里子さんが、自分が小学生の頃から何度も訪れている場所として「醍醐寺」を紹介。ここは豊臣秀吉が花見をするために建立した歴史ある寺院で、春だけでなく新緑の季節にも美しさが際立つ場所として知られています。
嵐山の絶景、竹林の美しさ、伝統と新しさが融合したスイーツ、そして苔と青もみじが織りなす静かな祈りの風景。中島歩さんが巡った京都の旅は、季節の息吹と日本の美を感じさせる時間でした。行楽シーズンに訪れる価値のあるスポットが丁寧に紹介されていました。
鴨川の納涼床で味わう京都の夏の情緒と伝統の魅力
初夏の京都の風物詩といえば、やはり鴨川の納涼床です。5月から始まったこの季節限定の光景は、鴨川沿いに80店舗以上の飲食店が仮設の床(ゆか)を川沿いに設け、訪れる人々に涼しさと風情を届けています。今回紹介されたのは、その中でも特に大規模な店舗で、270平方メートルという鴨川最大級の納涼床を誇り、京風フレンチを楽しめるスタイルでした。料理と景色が一体となった時間は、訪れる人々の記憶に残る特別な体験になります。
納涼床には、地域で受け継がれてきた暗黙のルールが存在します。たとえば、
-
座席の向きは鴨川に背を向けないこと
-
BGMなどの音楽をかけない
-
使用する資材には木材を用いる
-
隣接する店舗と床や手すりの高さを揃える
といったルールがあり、いずれも風情や景観を守るための心配りです。法律で定められているわけではありませんが、京都らしい美意識と品格がこうしたルールによって支えられていることがわかります。
今回の放送では、料理人の小野塚大治さんが紹介されました。彼は「いつか自分の料理を納涼床で提供したい」という夢を持ち続けており、今年その夢を叶え、鱧料理を提供できるようになったとのことでした。納涼床に立つ姿からは、長年の思いと職人としての誇りがにじみ出ていました。
さらに、近年では納涼床にも多彩なバリエーションが登場しています。伝統的な和食に加えて、
-
焼き肉床
-
バー床
-
朝床(モーニングスタイル)
-
ジェラ床(ジェラートが楽しめる)
など、新しい形の楽しみ方が広がってきています。今回のロケでは、俳優の中島歩さんがジェラ床を体験し、スイーツと川風の両方を堪能していました。
納涼床は、観光客だけでなく地元の人々にとっても特別な場所です。「大人になったら行きたい」というあこがれの存在であり、子どもの頃に横目で眺めていた納涼床が、いつしか自分の憧れの空間になる。そんな時間の流れと世代を超えた文化のつながりを感じさせてくれるのが、この鴨川の納涼床の魅力です。
古くは江戸時代に始まった納涼文化が、現代のライフスタイルとともに少しずつ形を変えながらも、京都らしさを失わずに息づいている——そんな印象深い内容が伝えられた特集でした。
映画の都・京都太秦で体感する時代劇の世界と文化の深み

番組の後半では、時代劇の聖地として知られる京都・太秦エリアが特集されました。この地域は、長年にわたり数々の映画やドラマの舞台となってきた場所であり、“映画の町”としての誇りと伝統が息づく場所です。
まず紹介されたのは、創立50周年を迎えた撮影施設。ここでは、観客が参加できる臨場感あふれるショーが定期的に開催されており、剣劇や立ち回りのリアルな演技が間近で楽しめます。訪れる人々は、ただ見学するだけでなく、映画の世界に入り込むような体験を通して、時代劇の迫力と魅力を肌で感じることができます。
次に訪れたのは、三吉稲荷神社。ここは、映画関係者たちが作品の成功を祈願して訪れる神社として有名です。小さな社ではありますが、業界内での信仰は厚く、数々のヒット作がここから生まれたとも言われています。京都の映画文化を支える“裏の聖地”といえる場所です。
続いて登場したのが、創業107年の小道具レンタル会社。ここでは、実際に映画撮影に使用された甲冑や刀などの小道具が多数保管されており、来館者が甲冑の試着体験をすることもできます。さらに、VRゲームで戦国武将とバトルする体験コンテンツもあり、昔ながらの文化に最新技術を掛け合わせたユニークな試みが行われています。
また、敷地内のレストランでは映画で使われた小道具が展示されており、食事をしながら映画の世界に浸ることができます。ここで働くスタッフの中には、時代劇をこよなく愛し、自ら演劇活動を行いながら学校などで公演を続けている人物もいるとのことで、文化とエンターテインメントの両立を体現する存在として紹介されていました。
さらに、視聴者から寄せられた情報として、北野天満宮のおすすめも紹介されました。北野天満宮といえば学問の神様として知られていますが、実はここにも豊臣秀吉が作らせた「もみじ谷」が存在し、紅葉シーズンには圧巻の景色が広がる京都屈指の名所です。
このように、京都・太秦には、時代劇という文化を守り育ててきた人々の情熱と、それを支える地域の力があります。伝統を大切にしながらも、現代の技術や観光ニーズに応じて進化し続ける場所として、非常に多くの魅力が詰まっていることが伝わる内容でした。時代劇ファンはもちろん、歴史好きや子ども連れの家族にもおすすめできるエリアです。
幻の古陶「珠洲焼」に見る再興の物語

最後に紹介されるのは、石川県能登半島の伝統工芸「珠洲焼(すずやき)」です。中世に栄えながらも15世紀に姿を消した焼き物で、「幻の古陶」と呼ばれています。1978年に再興され、現在ではさまざまな作家が制作を行っています。
-
鉄分の多い土を使い、釉薬をかけずに高温で焼き締める「還元焔焼成」
-
仕上がりは黒灰色で、独特の艶と深みが特徴
-
叩き技法による模様や装飾も魅力
現代の珠洲焼は、酒器や茶器、花器、食器など幅広く展開されています。使い込むほどに味が出る器として、日々の暮らしに寄り添う存在になっています。放送では、作家の制作風景や珠洲焼の魅力について紹介される予定です。
佐賀・唐津の新しい花文化「カラーリングマム」で広がる推し活の世界
番組の「いまオシ!LIVE」では、佐賀県唐津市からの中継が行われ、カラフルに染められた菊の花「カラーリングマム」が紹介されました。これは、通常は白や黄色が多い菊を、特別な染料でさまざまな色に染めた新しいスタイルの菊です。自然の色では見られない鮮やかなピンク、ブルー、パープルなどの色が並び、視覚的にもとても華やかです。
染色に使われるのは食品にも使える安全な染料で、菊が水を吸い上げる性質を利用してゆっくりと色を変えていく仕組みです。こうすることで、花びらの先までムラなく均一に色が染まり、見た目にも美しく仕上がるとのことです。
特に注目されたのは、地元の女性たちがカラーリングマムを使って「推し活」を楽しんでいる様子でした。女性の一人は、アイドルグループSnow Manのファンで、メンバーそれぞれの担当カラーに染めた菊を自宅に飾っていると紹介されていました。たとえば、青や緑、ピンクなど、推しの色で花をそろえることで、部屋全体が“推しカラー”に染まる演出ができ、見るたびに楽しい気持ちになれるそうです。
こうした使い方の広がりは、以下のような点でも注目されています。
-
仏花のイメージが強かった菊のイメージを変えた
-
若い世代にも親しみやすい花としての魅力を発信
-
季節やイベント、推し活に合わせて自由に楽しめる
これまであまり注目されてこなかった菊の新しい一面が見られ、花の楽しみ方そのものが進化していることを感じさせる内容でした。カラーリングマムは、見た目のインパクトだけでなく、その背景にある想いや楽しみ方が共感を呼び、SNSでも話題になっているそうです。花が「贈る」ものから「飾って楽しむ」もの、さらに「推しを表現するツール」へと変化していることが伝わる印象的な中継でした。
みんな!ゴハンだよ:2品の初夏レシピ
料理コーナーでは、季節の食材を活かした2品が紹介されました。
-
豆腐と豚バラの塩にんにく煮
豚バラ肉を折って小麦粉をまぶし、豆腐、ピーマン、パプリカ、ごま油、水と一緒にフライパンで蒸し煮にします。ふたをして5分間煮て、仕上げに黒こしょうをふるだけの簡単レシピです。 -
パプリカとナッツの甘辛炒め
別のフライパンで、パプリカ、しめじ、ミックスナッツを炒め、砂糖としょうゆで甘辛く味付け。七味とうがらしを加えることで、ピリッとしたアクセントになります。
坂下さんは「シンプルだけどすごく深い味」と感想を述べていました。
まとめ
今回の「あさイチ」は、暮らしの中の「今」と「季節」を深く掘り下げる内容が満載でした。金利上昇という難しい話題もわかりやすく解説され、京都の旅は映像だけでも涼やかさを感じるひとときでした。納涼床や時代劇体験など、京都の魅力がギュッと詰まった放送でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


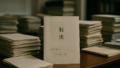
コメント