世界を変えた巨大災害
2025年6月9日に放送されたNHK『映像の世紀バタフライエフェクト』では、「世界を変えた巨大災害」が特集されました。一つの災害が、社会、政治、文化、科学の在り方を変え、時には国の形までも動かしてきたという視点から、世界中の歴史的な災害の映像と証言が紹介されました。自然の脅威が引き金となり、人々の生き方や国の政策、技術の進化が動き出す。その様子を丁寧に追った回でした。
NHK【クローズアップ現代】東日本大震災の被災者が自治体に訴えられる異例の事態とは?返済期限13年と災害援護資金の現実|2025年4月1日放送
2004年スマトラ島沖地震とYouTube誕生のきっかけ
2004年12月26日、インドネシア・スマトラ島沖で発生したマグニチュード9.1の巨大地震は、プレート境界での急激な断層運動により、インド洋全域に大津波を引き起こしました。この津波は、タイやスリランカ、インド、モルディブなどの観光地を直撃し、22万人以上の死者・行方不明者を出す未曾有の災害となりました。
この時、世界中から訪れていた観光客が手元のビデオカメラやデジタルカメラで、津波の襲来を偶然撮影していました。ホテルの屋上や浜辺、レストランからの映像が数多く存在していたにもかかわらず、それらを広く共有・発信できる手段が当時のインターネットにはありませんでした。
YouTube共同創業者のジャウド・カリム氏は、この津波の映像を「ネットで簡単に探せないことに強い疑問」を抱いたと後に語っています。彼がその瞬間に感じたのは、次のような問題でした。
-
インターネット上に動画は存在しているはずなのに、信頼できる一括共有の場がなかった
-
動画ファイルの投稿・再生が難しく、一般ユーザーが気軽に発信できる仕組みが未整備
-
他人とリンクを通じて動画を「見る・見せる」ことすら難しい時代だった
これらの課題が、カリム氏らの中で「動画をもっと簡単に共有できる方法を作ろう」という構想へとつながっていきます。2005年2月にYouTubeは設立され、同年4月に初の動画「Me at the zoo」が投稿されました。
つまり、2004年スマトラ沖地震の津波映像を誰もが手軽に見られなかったという“もどかしさ”が、YouTubeというサービス誕生の根本動機になったのです。自然災害という悲劇が、情報の共有方法そのものを変える転換点を生んだ出来事だったといえます。
サイクロンが引き起こした国の独立
1970年11月、南アジアを襲ったボーラ・サイクロンは、記録的な勢力で東パキスタン(現在のバングラデシュ)沿岸部に上陸し、数十万人もの命を奪った未曾有の大災害となりました。暴風雨と高潮によって多くの村が一夜にして消え、家族を失った人々が瓦礫の中で助けを待ち続ける姿が続出しました。ところがこのとき、東パキスタンを統治していた西パキスタン政府は被災地への対応をほとんど行わず、この対応の遅さと冷淡な態度が、東部の人々の怒りを強く引き起こしました。
・災害発生後、数日間にわたって支援が届かず、多くの被災者が放置された
・西パキスタン政府はメディア対応に終始し、実質的な救援が進まなかった
・地域住民の間に、「自分たちは見捨てられた」という感情が拡大
この災害を境に、東パキスタンでは「自分たちの国を自分たちの手で守りたい」という思いが急速に強まり、独立を求める声がかつてなく高まります。すでに存在していた民族的・言語的な対立や経済的不満に、この災害が導火線のように火をつけたのです。翌1971年、独立を求めた運動はバングラデシュ独立戦争へと発展しました。
国際社会でも、この独立の動きを支援する動きが生まれます。特に大きな影響を与えたのが、インド出身の音楽家ラヴィ・シャンカールとビートルズの元メンバージョージ・ハリスンです。2人はニューヨークで「バングラデシュ・コンサート」を開催し、世界中に支援と関心を呼びかけました。
・コンサートにはボブ・ディランなども参加し、チャリティーイベントとして歴史的成功を収めた
・このイベントを通じて、国際的な支援金が集まり、報道も拡大
・被災地と新興国バングラデシュの姿が、世界中に認知されるようになった
1971年12月、長く続いた混乱の末に、バングラデシュは西パキスタンからの独立を正式に達成。ボーラ・サイクロンによって始まった出来事が、国家の誕生という世界史的な転換点につながりました。自然災害がきっかけで、人々の意識、団結、そして政治が動いた歴史的な実例として、いまも語り継がれています。
火山災害が残した教訓と未来の防災へ
1985年11月13日、南米コロンビアのネバド・デル・ルイス山が噴火しました。この火山は標高5000メートル近くあり、山頂には氷河が広がっていました。噴火によってこの氷河が一気に溶け、大量の泥流(ラハール)が発生。夜のうちにふもとの町アルメロを襲い、およそ2万3000人の命が奪われるという大惨事となりました。泥流に埋もれた町では、がれきの中から救助を待つ人々の姿が各国メディアにより報道され、なかでも少女オマイラ・サンチェスの姿は世界中に衝撃を与えました。
・泥に埋まったまま救助を待ち続けた少女オマイラは、3日間も水に浸かりながら生き延びようとした
・当時の技術や装備では十分な救助ができず、多くの命が救えなかった
・この出来事は、災害における国際的な緊急支援体制の必要性を浮き彫りにした
この悲劇をきっかけに火山災害への注目が高まり、災害研究に取り組む科学者の活動が重要視されるようになっていきます。その中でも特に知られるのが、フランス人火山学者のクラフト夫妻です。モーリス・クラフトとカティア・クラフトは、世界中の火山を調査し、記録映像や教育用の資料を多数残しました。彼らは「人々が正しく火山を理解すれば、被害は必ず減らせる」と信じ、命をかけて火山に向き合っていました。
その思いが具体的に実を結んだのが、1991年にフィリピンで発生したピナツボ山の噴火です。このとき、クラフト夫妻の残した啓発ビデオが役立ち、多くの住民が噴火前に避難行動を取ることができました。この噴火では、火砕流よりも火山灰の重みで家屋が崩壊する被害が深刻でしたが、的確な予測と避難指示によって、人的被害は大幅に抑えられました。
・クラフト夫妻の映像が、噴火の特徴や危険性をわかりやすく伝えていた
・広範囲に避難が行われたことで、住民の命が守られた
・火山学の成果が、初めて明確に現場で役立った事例として評価された
しかしこの噴火は、それだけでは終わりませんでした。ピナツボ山の噴火によって大気中に大量の火山灰やエアロゾルが広がり、地球規模での気温低下を引き起こしました。特に北半球では気温が下がり、1993年の日本では冷夏に見舞われました。これにより米の収穫量が激減し、「平成の米騒動」が発生。タイ米の緊急輸入やスーパーの棚からコメが消えるという事態にまで発展しました。
火山災害が地球全体の気象に影響し、一国の食料危機につながる。この出来事は、自然災害がもたらす影響がどれほど広範囲で深刻なものかを、私たちに教えてくれたのです。そして同時に、災害を学び、備えることの重要性を強く示した象徴的なケースでもありました。クラフト夫妻の信念と行動は、今もなお世界中の防災活動に生かされ続けています。
日本を動かした地震とボランティアの力
1995年1月17日、兵庫県南部を中心に発生した阪神・淡路大震災は、都市型地震として日本の災害史に深く刻まれる出来事となりました。マグニチュード7.3の揺れは広範囲にわたり、住宅は64万棟が倒壊、多くの命が失われました。高速道路の橋脚が崩れ、ビルが横倒しになるほどの激しい揺れが、早朝の町を一瞬でのみ込んだのです。
避難所では水や食料が不足し、行政の初動対応にも限界がありました。そんな中で、被災者自身が自ら動いて助け合い、がれきの中から人を救い、炊き出しを始め、情報を共有する動きが広がりました。このような行動は、従来の「公助」に依存する体制から、「自助」や「共助」の意識へと大きく変わるきっかけとなりました。
・大学生や社会人、主婦、高齢者など、あらゆる層の人々がボランティアとして参加
・炊き出し、がれきの撤去、子どもの遊び場づくり、被災者の話し相手など、多様な支援が展開された
・各地で「自分にできることをやろう」という空気が自然に生まれていった
震災の数日後には、全国から多くの人が神戸や淡路島に向かいました。それは「誰かを助けたい」という思いによる自然発生的な行動でした。行政や企業、地域社会の枠にとらわれずに広がったこの動きが、やがて「ボランティア元年」と呼ばれる象徴的な変化を生み出します。
この震災を機に、政府も市民の力を防災の重要な一要素として認識するようになり、災害対応の仕組みや法制度の見直しが進められていきました。災害ボランティアセンターの設置や情報共有体制の整備など、市民と行政が連携する新しい防災モデルの基礎が築かれていきます。
阪神・淡路大震災は、甚大な被害をもたらした悲劇であると同時に、日本社会に「助け合う力がある」ことを証明した歴史的な出来事でもありました。そしてその後の東日本大震災、熊本地震、能登半島地震などでも、あのときの経験が生かされ、多くの人々の行動を支える原動力となっています。自然の力に翻弄されながらも、人と人とがつながることで希望を生み出す、その始まりがこの震災だったといえます。
ソーシャルメディアと災害
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、未曾有の大津波と原発事故という複合災害をもたらし、日本社会全体に深い影響を与えました。この震災では、テレビやラジオだけでなく、ソーシャルメディアが初めて災害時の情報発信手段として本格的に活用されました。TwitterやFacebookなどのSNSを通じて、安否確認や救助要請、避難情報の共有が行われ、多くの命が救われたといわれています。
・SNSでリアルタイムに避難情報が拡散され、多くの人が迅速に高台へ避難した
・停電中でもスマートフォンから情報収集が可能となり、テレビに頼らない手段が確立された
・個人が発信した情報が、大きな流れとなって支援を呼びかける役割を果たした
一方で、災害時の情報にはリスクも存在します。2016年の熊本地震では、SNSに投稿された偽の救助要請や、事実と異なる避難情報が現場の混乱を招きました。さらに2024年元日に発生した能登半島地震では、存在しない被災者の名前や捏造された動画が拡散され、実際の救助活動に支障が出るケースも発生しました。
・「○○地区で孤立中」「助けてください」といった投稿が実在しないケースも多数報告
・誤った情報により、支援物資が本当に必要な地域に届かない事態が発生
・一部の投稿が注目を集めることで、信頼できる情報の拡散が妨げられた
このような問題を受け、現在ではSNSの情報を検証・分類する仕組みの整備が進められています。また、海底地震観測網や津波観測網といった科学的インフラも強化され、早期警戒の制度が向上しました。たとえば、「日本海溝海底地震津波観測網(S-net)」や「南海トラフ地震臨時情報」といった新しいシステムが整備され、国民の安全を守る備えが着実に広がっています。
ソーシャルメディアは、災害時の希望と危険の両面を持つ道具です。正しい使い方を学びながら、信頼できる情報源を見極める力が求められる時代となりました。そして、情報インフラと市民の意識の進化が、日本の災害対応をさらに強くしていく鍵となっています。
まとめ
今回の特集を通じて伝えられたのは、「巨大災害はただの悲劇ではなく、歴史を動かす力を持つ出来事である」という事実でした。移民の流れ、公民権運動の加速、国の独立、報道の変化、防災技術の進歩――いずれも災害がきっかけで生まれたものでした。私たちが次に災害に直面したとき、ただの被害で終わらせるのではなく、未来を変える力に変えられるかどうかが問われているといえるでしょう。次回の放送にも注目です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

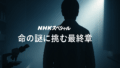
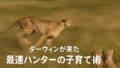
コメント