山梨・笛吹市で800年受け継がれる「鵜飼い」
2025年9月4日に放送されたNHK総合「ひむバス!」の舞台は、フルーツの名産地として知られる山梨県笛吹市でした。番組では、800年もの歴史を持つ伝統漁法「鵜飼い」に密着。日村勇紀さん(バナナマン)が運転するバスが、人々の思いをつなぎながら、伝統と未来を見守る旅が展開されました。今回の依頼人は、鵜匠の丸山智弘さんと息子の琉亜さん親子。いよいよ始まる鵜飼いシーズンを前に、その送迎をお願いしたいという依頼から物語がスタートしました。
船を使わない「徒歩鵜」スタイル
笛吹市で行われる鵜飼いの特徴は、全国的にも珍しい「徒歩鵜」というスタイルにあります。一般的な鵜飼いは船に乗って行いますが、笛吹市では鵜匠が自ら川に入り、歩きながら鵜を操って魚をとるのです。漁の主役となるのはもちろん鵜。アユなどを捕まえるために、水中に潜って魚をくわえて戻ってくる姿は迫力満点です。この独特の方法は地域に根付いた生活文化の証であり、代々受け継がれてきた貴重な伝統でもあります。
鵜匠と鵜の深い絆
依頼人の丸山智弘さんは、笛吹川石和鵜飼保存会の会長を務めています。保存会のメンバーは12人。彼らはそれぞれ本業を持ちながらも、一年365日欠かさず鵜の世話や訓練を行っています。鵜小屋には22羽の鵜がおり、2〜3年かけてじっくり訓練を受けます。鵜は人間の言葉を理解しているかのように、合図に従って泳ぎます。中には10年以上にわたり現役で活躍する鵜もいるのだそうです。日村さんと森田茉里恵さんは鵜小屋を訪れ、鵜匠たちの努力と愛情に支えられていることを体感しました。ここには単なる漁の道具ではなく、家族の一員として大切にされる鵜の姿がありました。
鵜飼い前夜の緊張感
シーズン開幕を前に、鵜匠たちは笛吹川で最終練習を行います。鵜を操る動きは一朝一夕で身につくものではなく、繊細な技術と長年の経験が必要です。日村さんも実際に鵜を操る体験をしましたが、鵜を思い通りに動かすのは容易ではなく、訓練の積み重ねの大切さを実感しました。練習の風景は、翌日の本番に向けた緊張感と期待感に満ちていました。
若い力が伝統を支える
ひむバスはさらに、鵜飼いをサポートする高校生たちを送迎しました。参加したのは山梨県立笛吹高等学校の生徒たち。中でも濱田桐吾くんは昨年に続いての参加で、体験を通じて「将来は鵜匠になりたい」と思うようになったと語っていました。こうした若者たちの存在は、伝統を未来へとつなぐ大きな希望です。世代を超えて受け継がれる姿は、見ている人の心にも温かさを残しました。
鵜飼い本番!かがり火に照らされた幻想的な夜
そして迎えた鵜飼い本番。川辺には1200人もの観客が集まり、夜の笛吹川は幻想的な雰囲気に包まれました。かがり火がゆらめく中、丸山智弘さんが川に入り、その後を高校生たちが続きます。鵜たちが水中へ潜り、最初のアユを見事に捕まえた瞬間、観客からは大きな拍手が起こりました。伝統の力と自然の迫力が一体となり、観る人々の心を震わせる光景でした。
一方、新人の長沼史佳さんは初めての本番で苦戦。初日はアユを捕まえることができませんでしたが、その後1か月の努力を重ね、ついに観客の前でアユを捕らえることに成功。大きな拍手を受けた瞬間は、彼女にとっても観客にとっても忘れられない時間となりました。
伝統を守るということ
今回の放送を通じて浮かび上がったのは、伝統を守り続ける人々の情熱と努力です。鵜匠たちの日常は地道な作業の積み重ねですが、それがあってこそ美しい鵜飼いの夜が実現します。また、高校生や若者が参加することで、この文化が次の世代へと受け渡されていくことも確認できました。観光のためだけでなく、地域の誇りとして守られていることに大きな意味があるのです。
まとめ
「ひむバス!」山梨・笛吹市の旅は、800年受け継がれる鵜飼いの魅力をたっぷり伝えてくれました。鵜匠と鵜の信頼関係、地元保存会の活動、若者たちの挑戦、そして1200人の観客が見守る本番。すべてが重なり合って、ふるさとの誇りを体現する時間となりました。もしこの記事を読んで興味を持った方は、ぜひ一度笛吹川石和鵜飼を訪れ、その迫力と感動を体験してみてください。きっと忘れられない思い出になるはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

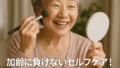

コメント