病気とともに働くには?
病気を抱えながらも「働き続けたい」と思う人は多いです。でも治療や体調の問題で「周囲に迷惑をかけてしまうのでは?」と悩んだり、「お金はどうなるの?」と不安に思う人も少なくありません。2025年9月8日放送のあさイチでは、実際に病気と向き合いながら働く人たちの体験や、支えてくれる制度や相談先について紹介されました。この記事では番組内容をもとに、治療と仕事を両立するためのヒントをわかりやすくまとめます。
多くの人が抱える「病気と仕事」の現実
厚生労働省の国民生活基礎調査によると、就業している人のうち約4割が、何らかの疾患を抱えて定期的に通院していることが分かっています。これは決して特別なケースではなく、多くの人が身近に直面している現実です。例えば、ある38歳の女性は、無月経や顎関節症、そして骨粗鬆症といった複数の病気を同時に抱えていました。長期間の治療や症状の影響で、体力的にも精神的にも大きな負担が積み重なり、最終的には会社を辞めざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。このように、病気は誰にでも突然訪れる可能性があり、健康に働き続けられるかどうかは多くの人にとって切実な課題です。だからこそ、仕事と治療をどう両立させるかは、個人だけでなく社会全体が向き合うべき大きなテーマとなっているのです。
著名人の体験から学ぶ
佐藤弘道さんは2024年に脊髄梗塞を発症し、現在も下半身麻痺という大きな後遺症と向き合いながら、自分にできる形で活動を続けています。また、矢方美紀さんは2018年に乳がんと診断され、いまもホルモン治療を継続しながら芸能の仕事を続けています。矢方さんは、当時の主治医から「治療を続けながら働く方法もある」と助言を受け、思い切って仕事を辞めずに治療を選択しました。この二人の姿勢からは、病気の治療を理由にキャリアを途中で諦める必要は必ずしもないという強いメッセージが伝わってきます。病気と仕事を両立させる道は人それぞれであり、工夫や支えがあれば前向きに歩んでいけることを示しているのです。
仙台での事例:産業保健総合支援センターの活用
宮城県仙台市で働く池田倫子さん(43歳)は、数年前にシェーグレン症候群を発症しました。体調が安定せず、同僚に迷惑をかけてしまうのではと悩み、ついに退職を申し出るまで追い込まれました。その時、専務の内田直子さんは「もっと支えられる方法があるのでは」と考え、驚きとショックを抱えながらも改善策を模索しました。ここで大きな助けとなったのが、全国に設置されている産業保健総合支援センターです。専門家から「業務量を減らすだけでなく、業務内容を工夫すれば負担を軽減できる」と具体的な助言を受けたことで、池田さんの心理的な不安も和らぎ、仕事に向き合う気持ちが楽になったといいます。さらに会社では新たに年10日の病気休暇制度を導入し、制度面でのサポートも整備されました。こうした取り組みは、病気を抱えながらも安心して働き続けられる環境づくりにつながっています。
がん相談支援センターでのサポート
東京・築地の国立がん研究センター中央病院には、毎年およそ800件もの相談が寄せられています。その中には、乳房悪性腫瘍と診断された49歳の女性のケースもありました。彼女は「治療を続けながら本当に仕事を続けられるのか」という不安を抱え、相談に訪れたのです。そこで対応したのは、病院に常駐する医療ソーシャルワーカーや看護師たちでした。治療のスケジュール調整や有給休暇の上手な使い方について具体的なアドバイスを行い、患者と職場をつなぐ役割を果たしてくれました。病院と会社の間に立ってサポートしてくれる存在がいることで、患者は安心して治療に専念しつつ仕事との両立に挑むことができ、まさに心強い支えとなっているのです。
治療とお金の両立
病気による経済的な負担も大きな悩みのひとつです。例えば看護師のまりこさん(55歳)は、乳がんの治療のために1年間休職を余儀なくされました。その間に支給されたのは傷病手当金ですが、金額は給料の3分の2にとどまり、生活を支えるには十分ではありませんでした。さらに追い打ちをかけるように、休職中でも社会保険料や住民税の支払いは続き、家計の負担はますます重くなりました。そんな中で大きな助けとなったのが、自己負担額を一定の上限額に抑えてくれる「高額療養費制度」です。また、もし自営業者であれば、自治体の生活福祉資金貸付制度を利用したり、あらかじめ就業不能保険に加入しておくと安心につながります。このように、病気と向き合うときには知らないと損をする制度が数多く存在します。だからこそ、いざという時に困らないように、早めに制度を調べて確認しておくことがとても大切なのです。
仕事を続けるヒントと「私のトリセツ」
番組では、病気とともに働く工夫のひとつとして「私のトリセツ」の活用が紹介されました。これは、自分の体調の特徴や配慮してほしいことを具体的に書き出す取り組みです。周囲に理解を求めやすくなるだけでなく、書きながら自分自身の気持ちや状況を整理する手助けにもなります。実際に、航空会社で働く渡部俊さんは、なんと9度目のがん再発を経験しました。その後はリモートワークを上手に取り入れ、新しい部署で無理のない働き方を実現しています。さらに渡部さんは、同僚に対して病気のことをオープンに伝えることで、必要な理解と協力を得られるようになりました。その結果、体力的な負担を減らしつつ、安心して仕事を続けられているのです。
いまオシ!LIVE 長崎・佐世保の伝統こま
特集のあとは、長崎県佐世保市から伝統工芸の佐世保独楽が紹介されました。およそ300年の歴史を持ち、芯にはひし形の鉄芯を使った独特の構造が特徴です。模様には十二支が描かれたものなどもあり、見た目にも華やかです。しかし今では、この独楽を専門に作る職人はわずか1人だけになっています。番組では工房での制作の様子や、完成した独楽を実際に回す場面も放送されました。力強く、そして美しく回る独楽と、それを黙々と作り続ける職人の姿からは、地域の伝統を守り抜こうとする強い思いが伝わってきました。
みんな!ゴハンだよ サバ缶レシピ
料理コーナーでは「さば缶と3色パプリカのパスタ」と「さば缶とトマトの冷たいスープ」が登場。パプリカの色合いとサバのうまみを生かしたパスタは、最後にちぎったバジルが香りのアクセント。冷たいスープはトマトジュースにみそを加え、クルトンやみょうがを添えて爽やかな仕上がり。ゲストの矢方さんも「臭みがなくて美味しい」と絶賛しました。
いまオシ!REPORT 信州サーモン
長野県安曇野市からは、地元の特産として注目される信州サーモンが紹介されました。これはニジマスとブラウントラウトを掛け合わせて誕生した養殖魚で、卵を産まないため栄養が身に行き渡り、旨みがぎゅっと凝縮されているのが特徴です。肉質はやわらかく、脂ののりもほどよく、料理にすると上品な味わいが引き立ちます。番組ではフレンチシェフの板花芳博さんが、この信州サーモンを使って「カプレーゼ」や「ソテー」に仕立て、彩り豊かで洗練された一皿に仕上げていました。地元の恵みを最大限に生かした料理を通して、信州サーモンの新たな魅力が伝えられていました。
エンディングとまとめ
最後に視聴者からのお便りも紹介されました。上司に手紙で自分の病気と希望を伝えたことで、安心して復職できたという声もありました。専門家の清水理恵子さんは「信頼できる上司にまず相談することが大切」とアドバイス。誰にどこまで伝えるかを整理することが、働き続ける第一歩になります。
今回のあさイチでは、病気とともに働く人の体験談、支援してくれる制度や機関、そして生活を支える工夫が幅広く紹介されました。病気を理由に仕事を諦める必要はなく、相談先や制度を知ることで、自分らしく働き続ける道は必ずあることが伝わってきました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


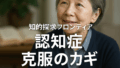
コメント