ようこそ オトナの“絵本時間”へ
子どもの頃に親しんだ絵本。大人になると手に取る機会は少なくなりますが、実はいま、大人の間で絵本がブームになっています。「なんで今さら絵本?」と感じる人もいるかもしれません。でも、シンプルな言葉と深いテーマが、日々情報にあふれる大人の心に響くのです。この記事では、首都圏情報ネタドリ!の特集「ようこそ オトナの“絵本時間”へ」の内容をもとに、大人が絵本に惹かれる理由や最新の人気作品を紹介します。放送後にさらに詳しい情報を追記予定です。
絵本が出版業界を動かす
本の世界で今もっとも注目されているのが絵本です。まず目を引くのは、出版指標年報(2025年版)に記された数字です。昨年の年間ベストセラーランキングのTOP10のうち、なんと3作品が絵本でした。これまで「絵本は子どものもの」というイメージが強かったのですが、いまやその枠を飛び越え、幅広い大人の読者層にも浸透しています。
ベストセラーに並ぶ絵本たち
ランキング入りしたのは『パンどろぼう』『ほっかほっカー』『大ピンチずかん』シリーズといった作品です。書店では専用の平積みコーナーが設けられるほどで、家族連れだけでなく、一人で訪れた大人が手に取る姿も珍しくありません。SNSでは、作品の感想やイラスト写真が数多くシェアされ、口コミを通じてさらに人気が広がっています。
出版不況のなかで存在感を増す
ここ数年、出版業界は長引く不況に直面しています。雑誌の売上は減少し、文芸書もヒット作が限られている状況です。そんな中で、絵本は市場をけん引するジャンルとして頭角を現しました。短い文章と絵が一体となって心に残る読書体験を生み出すことで、世代を問わず読者を引き寄せています。
読者層の広がり
特に注目されるのは読者層の変化です。親子で読むだけでなく、大人が自分のために購入するケースが増えています。ストレスの多い生活の中で、やさしい言葉や絵に癒やされる人、また社会的なテーマを含んだ作品から新しい学びを得る人もいます。結果として、絵本は出版市場の新しい中心になりつつあります。
表:出版業界における絵本の存在感(2024年データ)
| 指標 | 数字・事実 | 備考 |
|---|---|---|
| ベストセラーTOP10に入った絵本 | 3作品 | 『パンどろぼう』『ほっかほっカー』『大ピンチずかん』 |
| SNSでの関連投稿数 | 数十万件規模 | 感想・写真シェアが中心 |
| 読者層 | 子ども+大人 | 大人単独購入が増加傾向 |
このように、絵本は「出版不況」という言葉があふれる業界にあって、確かな希望を示しています。子どもから大人まで世代を越えて愛される存在へと進化した今、その力はますます大きな広がりを見せています。
命と向き合う物語『もうじきたべられるぼく』
近ごろ特に注目を集めているのが、はせがわゆうじさんの絵本『もうじきたべられるぼく』です。主人公は食肉として育てられた一頭の牛。自分がもうすぐ食べられてしまうと気づいたとき、離れて暮らす母親に会いに行こうとする姿が描かれています。作品全体を通じて流れるのは、命の有限さと親子の深いつながりです。
ネットから広がった絵本の力
この作品はもともと10年以上前にインターネット上で公開されていたものでした。当時は知る人ぞ知る存在でしたが、SNSで紹介されると共感の声が一気に広がり、多くの人の心を動かしました。その後、口コミとともに注目を集め、出版という形で多くの読者の手に届くようになりました。現代においてSNSが果たす役割の大きさ、そして絵本の持つ普遍的な力を示す事例といえます。
消費社会への問いかけ
千葉県出身の作者がこの物語に込めたのは、「命をいただく」という行為に対する真摯な問いです。牛を主人公とすることで、普段は意識しづらい食の裏側にある現実を、読む人にまっすぐ突きつけています。私たちが毎日の食事で口にする一皿が、多くの命の上に成り立っていることを改めて考えさせられます。
読者に残す余韻
この絵本を読んだ人の多くは、重たいテーマでありながらも、そこに流れる温かさや優しさに心を揺さぶられます。文字数は少なくても、絵と物語が一体となって深い余韻を残す。それこそが絵本の力であり、大人の読者が惹かれる理由のひとつでもあります。
『もうじきたべられるぼく』は、単なる物語を超えて、命と向き合う大切さを静かに教えてくれる一冊として存在感を放っています。
大人たちをつなぐ読書会
東京・千代田区で開かれている大人向け絵本読書会は、月に1度の小さな集まりです。参加するのは、子育てを終えて自分の時間を持てるようになった人や、一人暮らしをしている人などさまざま。彼らはそれぞれが心に残る絵本を持ち寄り、読み合いながら交流を深めています。
絵本を通じて広がる対話
読書会の魅力は、ただ本を読むだけでなく、そこから自然に会話や意見が生まれることです。参加した小原勇さんは「自分とは違う考えに出会える」と話し、そこで紹介された一冊が自分の人生にとってかけがえのない存在になったといいます。普段は出会えない価値観に触れることで、新しい気づきを得られるのです。
紹介される多彩な作品
この読書会では、ジャンルやテーマを限定せず、幅広い絵本が紹介されます。たとえば『Love Letter ~私への手紙~』は自分と向き合うきっかけを与え、『やさしいライオン』(やなせたかし)は深い優しさと愛情を思い出させてくれます。さらにかがくいひろしやくすのきしげのりといった人気作家の作品も登場し、参加者それぞれの思い出や体験と結びついて語られます。
温かな場としての存在
絵本は子どものためだけのものではなく、大人にとっても心を整え、人とのつながりを生む大切な存在です。この千代田区の読書会は、まさに絵本が人と人を結ぶ「架け橋」となり、参加者が安心して自分の気持ちを表現できる場として続いています。忙しい日常から少し離れ、ページをめくることで心を通わせるこの時間は、多くの人にとって貴重なひとときとなっています。
体を守る知識を伝える『だいじ だいじ どーこだ?』
絵本は心を癒やすだけでなく、社会的な課題に応える役割も果たしています。その代表的な一冊が、川原瑞丸さんの『だいじ だいじ どーこだ?』です。この作品は、子どもに「体の大切な場所」をわかりやすく伝えるためにつくられたもので、親子で性や体のことを話すきっかけを与えてくれます。難しいテーマをやさしい絵と言葉に置き換えている点が大きな魅力です。
ベストセラーとなった理由
『だいじ だいじ どーこだ?』は、発売から口コミで広がり、すでに46万部を突破しました。多くの保護者や教育関係者から支持を集め、家庭だけでなく保育園や小学校の現場でも読み聞かせに使われています。体の大事な部分をきちんと知ることは、自分を守る第一歩。この本は、子ども自身が理解できるように工夫されているため、幅広い世代から評価されています。
読み聞かせ会で広がる実践
千葉県市川市の助産師黒須さんは、この絵本を使った読み聞かせ会を定期的に開いています。親と子が一緒に本を読み進めながら「どうしてここが大事なのか」「どう守ればいいのか」を自然に考える時間を持てるのです。黒須さんの取り組みは、地域での性教育や防犯教育の一助にもなっており、絵本を通じて親子の対話が深まっています。
絵本だからこその力
性や体の話題は、言葉にするのが難しく、親も戸惑うことが多いテーマです。しかし、絵本という形をとることで、やさしい言葉と絵が橋渡しとなり、子どもも安心して受け止められます。大切なことを自然に、押しつけではなく伝えられる点こそ、絵本ならではの力です。『だいじ だいじ どーこだ?』は、親子の関係を支える実用的な一冊として、多くの家庭に広がり続けています。
又吉直樹が選ぶ一冊『おしいれのぼうけん』
番組のゲストである又吉直樹さんが心に残る一冊として紹介したのは、『おしいれのぼうけん』(古田足日・田畑精一)でした。子どもの頃から繰り返し読んできたというこの物語は、押し入れに閉じ込められた子どもたちが想像の世界で冒険を繰り広げる内容です。特に、大人になってから読み返して印象に残ったのは、子どもを押し入れに入れた先生が反省する場面。子ども目線ではスリルと冒険の物語に映りますが、大人の視点で読み直すと、教育や人との関わり方に深い問いを投げかける作品であることがわかります。
『本でした』に込められた余白の力
また、又吉さんは自身とヨシタケシンスケさんによる共著『本でした』についても言及しました。この本は、あえて説明をしすぎず「余白」を残すことを意識してつくられています。読者自身が考え、物語を補いながら読み進められる構成が特徴です。ヨシタケ作品らしいユーモアと、又吉さんの言葉への感性が融合し、「読む人が参加できる本」として独自の魅力を放っています。
絵本の本質を語ることば
番組の中で又吉さんが語った「言葉では説明できない無言の表現ができるのが絵本」という言葉は非常に印象的でした。絵と文字が融合した絵本は、ただ情報を伝えるだけでなく、読む人に想像力を広げる余白を与えてくれます。大人になってからこそ、絵本に潜む深さを改めて感じ取れる瞬間があるのです。
『おしいれのぼうけん』と『本でした』。この2冊を通じて、又吉直樹さんが大人にも絵本をすすめる理由がはっきりと伝わってきます。絵本は世代を越えて心に残り続ける文化のひとつであることを、改めて教えてくれるエピソードでした。
戦争を描く絵本『いま、日本は戦争をしている』
2025年7月に刊行され、わずか1か月で重版が決まったのが堀川理万子さんの絵本『いま、日本は戦争をしている』です。この作品は、太平洋戦争中に子どもたちが体験した日々をテーマに描かれており、戦後80年という節目の年に大きな話題を呼びました。出版と同時に原画展も開催され、実際のスケッチやラフが展示されたことで、制作の真剣さとリアリティが多くの人に伝わりました。
聞き取りから生まれた物語
堀川さんは作品を制作するにあたり、戦争体験者から直接話を聞き、その場でスケッチを重ねました。中でも印象的なのは、沖縄戦を7歳で経験した比嘉義秀さんの体験をもとに描かれた場面です。幼い目で見た戦争の現実が、絵と物語に反映されています。取材対象となった17人のうち、すでに4人が亡くなっているという事実は、記録を残すことの緊急性を強く訴えています。
多くの地域をカバーする証言
この絵本には、沖縄だけでなく広島や長崎、さらにはサハリンでの体験談も盛り込まれています。異なる地域で子どもたちがどのように戦争を生き抜いたのか、その声を重ね合わせることで、戦争が日本全体に与えた影響を多角的に描き出しています。
出版業界でも注目される存在
戦争を題材にした絵本は決して多くはありません。しかし、子どもの目線を通じて戦争の現実を伝えるこの作品は、次の世代へ記憶を受け継ぐ貴重な役割を担っています。戦後80年という節目に登場したことで、出版業界や教育現場でも関心が高まっています。絵本というシンプルな形式でありながら、読者に重い問いを投げかける力を持つ一冊です。
『いま、日本は戦争をしている』は、ただの絵本ではなく、未来に向けて「忘れないための記録」として存在感を放っています。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・大人向けの絵本が出版業界を支え、新しい文化を生み出している
・『もうじきたべられるぼく』『だいじ だいじ どーこだ?』など社会的テーマを扱う絵本が広がっている
・又吉直樹さんをはじめ、多くの人が絵本を通じて考え、感じる時間を持っている
大人が絵本を手にすることは、情報過多の時代に「立ち止まり、自分で考える時間」を与えてくれます。放送後には、番組で紹介された読書会の様子や視聴者の反響を追記していきます。あなたも一冊、気になる絵本を手に取ってみませんか?
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

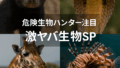

コメント