小泉八雲〜怪談 日本の面影を訪ねて〜
「『耳なし芳一』や『雪女』は聞いたことがあるけれど、どうして今も語り継がれているの?」
「小泉八雲って外国人なのに、なぜ日本の怪談を世界へ広めることができたの?」
こうした疑問を持つ方にとって、2025年9月29日に放送予定の『木村多江の、いまさらですが… 小泉八雲〜怪談 日本の面影を訪ねて〜』は絶好の入口になります。この記事では、放送内容の見どころや小泉八雲が歩いた足跡を整理しました。
【あさイチ】最新ホラーブーム徹底特集!進化するお化け屋敷・VR恐怖体験・実話怪談・リアル系ホラーの人気の秘密とは|2025年7月2日放送
小泉八雲が日本で出会った物語の原点
1890年(明治23年)、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は来日し、松江に赴任しました。そこで彼が出会ったのは、城下町ならではの静かな街並みと、四季折々に姿を変える宍道湖の美しい風景でした。湖面に映る夕陽や、霧に包まれる水辺の光景は、彼の心に深く刻まれました。
松江の町には古い日本庭園や、地域に根づいた寺社が数多く残されており、人々はそこに祈りを捧げ、日々の暮らしと結びつけていました。そうした信仰や風習は、八雲にとって新鮮であり、日本文化を理解する大切な手がかりとなりました。
日常の中で響く寺の鐘の音、石畳を歩く下駄の響き、そして参拝に訪れる人々の素朴な祈りの声。こうした何気ない光景が彼の感性を揺さぶり、のちに『知られぬ日本の面影』や『怪談』といった作品へと結実していきます。
さらに大きな存在となったのが妻の小泉セツでした。セツは地域に伝わる民話や伝承を八雲に語り聞かせ、その言葉は彼の物語づくりの骨格を形づくりました。八雲はセツを通して、日本人の心に息づく物語の力を知り、それを文学として世界に伝えることができたのです。
『耳なし芳一』『雪女』『乳母桜』が語るもの
番組では講談師の神田山緑が三つの怪談を演じます。『耳なし芳一』は平家の怨霊譚を背景に、信仰の力や命をかけた犠牲を描いた物語です。琵琶法師の芳一が、怨霊に取り込まれそうになる姿を通じて、人と死者との境界、そして経文の力が示されています。物語の根底には、信仰によって人を守ろうとする強い思いが流れています。
『雪女』が映す自然と人間
『雪女』は冬の厳しい自然そのものが怪異として姿を現す物語です。吹雪の中に現れる雪女は、人の命を奪う存在であると同時に、愛を与える存在としても描かれています。若者と雪女との出会いと別れは、人間の恐れや愛情、そして自然の前でのはかなさを浮かび上がらせます。雪という自然現象が、人間の感情と深く結びついていることを伝えています。
『乳母桜』が伝える犠牲と愛情
『乳母桜』は、子どもを守るために乳母が自らを犠牲にする物語です。知名度は他の怪談に比べて低いものの、そこには強い愛情と身代わりになるという深い意味が込められています。乳母の思いと桜の木が結びつき、人々に語り継がれてきたこの話は、自己犠牲の尊さや人の心に宿るやさしさを表しています。
怪談が映す日本人の心
これら三つの物語は、ただの恐ろしい話ではありません。そこには日本人の精神や自然に対するまなざしが映し出されています。死者と生者の境界、自然の厳しさと人間の弱さ、そして愛情や犠牲といった感情。そうした普遍的なテーマが重なり合うことで、『怪談』は文学作品としての深みを持ち、今もなお語り継がれているのです。
八雲が歩いた松江と出雲大社への道
徳永えりがリポートするのは、小泉八雲が実際に暮らした松江の旧居や、執筆に使った部屋です。畳敷きの静かな空間や、障子越しに差し込むやわらかな光は、八雲が文章を書くときに大きな影響を与えました。室内には当時の暮らしを感じさせる調度品も残されており、八雲がどのように日常と向き合い、創作に励んでいたのかを具体的に想像することができます。
また、塩見縄手と呼ばれる武家屋敷が並ぶ道は、松江を代表する歴史的な景観で、八雲が好んで散策した場所として知られています。石垣や白壁の続く町並みは、過去と現在が溶け合うような雰囲気を漂わせ、作品に登場する情景の原型となりました。さらに宍道湖の夕景は、八雲にとって忘れられない風景でした。湖面に映る夕陽の赤や紫の色合い、そして水面に広がる静けさが、彼の文章に深い陰影を与えています。
そして、彼が足を運んだ出雲大社は、日本最古級の歴史を持つ神社であり、日本神話の聖地としても名高い場所です。参道を進み、本殿に祈りを捧げる体験は、八雲にとって単なる参拝ではなく、日本人の精神文化に触れる重要な体験でした。出雲地方に根づく「神在月」の信仰や、自然と共に暮らす人々の姿勢を知ることで、八雲は「日本人の心」を理解する鍵を見つけたのです。
地域の信仰や自然に触れたこれらの体験は、八雲が単なる怪談作家にとどまらず、文化や精神の深層を描く文学者として評価される理由につながりました。松江と出雲をめぐる道のりは、彼にとって日本を知るための大切な旅であり、作品世界を豊かにする源泉となったのです。
木村多江・池田鉄洋・速水奨が彩る番組の魅力
番組を導くのは女優木村多江と俳優池田鉄洋。親しみやすい進行に加え、語りを担当するのは速水奨。重厚な声で紡がれるナレーションは、怪談の世界をより一層引き立ててくれるでしょう。
この記事のポイント
・小泉八雲の文学の原点は松江での生活と妻セツの語りにあった
・『耳なし芳一』『雪女』『乳母桜』はそれぞれ信仰・自然・愛情を描く怪談である
・松江の旧居や出雲大社の参拝は八雲の創作と日本理解を深める旅だった
まとめと次のステップ
小泉八雲が描いた怪談は、ただの恐怖譚ではなく、日本人が大切にしてきた信仰や自然観を記録した文化遺産です。今回の番組をきっかけに、忘れかけていた「日本の面影」に改めて触れてみてはいかがでしょうか。放送後には、神田山緑の講談の表現や、徳永えりが訪れた松江・出雲の映像美を追加でまとめる予定です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

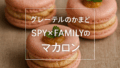
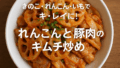
コメント