トレカ騒動に見る“転売ビジネス”のリアルと限界
2025年10月、まだ薄暗い早朝の東京・新宿。午前5時過ぎ、眠らない街の一角に長蛇の列ができていた。行列の先にあったのは、なんとハンバーガーショップ。お目当ては、期間限定で販売された人気ゲームキャラクターとのコラボトレーディングカード付きのセットだった。
このカード、実は中古市場で驚くほどの価値を持つ。数年前には1枚が7億円以上で落札されたこともあり、今や“投資商品”としての顔を持っている。そのため、食事ではなくカードを狙う人々が殺到。複数店舗で混乱が発生し、警察が出動する事態にまで発展した。
現場では、カードだけ抜き取ってハンバーガーを放置する人、数人のグループで大量購入する転売ヤーの姿も確認された。さらに現金のやり取りをしている人物もおり、その裏に転売目的の取引があることが見えてきた。
“中国転売ルート”というもう一つの市場
取材を進めると、転売されたトレカの多くが中国の大手フリマサイトで高額取引されていることが判明。日本で数千円の商品が、数万円で出品されていた。中国では日本のキャラクターグッズや限定商品への人気が非常に高く、なかでもトレカは“プレミア投資商品”として確固たる地位を築いている。
番組スタッフは、実際に中国向けの転売に携わる女性にも取材。彼女は「中国のお客さんに頼まれているだけ」と話し、20万円分の送料をかけて大量のキャラクターグッズを送っていたという。
転売ネットワークの実態を探るため、番組は物流会社にも取材を依頼したが、すべて拒否された。専門家によると、一部の企業は正規ルートではなく「コンテナの隅を間借りする通関方式」などの抜け道を使い、膨大な量の商品を輸出している。こうした構造が、国内での“買い占め”と“転売”を支えているという。
京都・宇治の老舗抹茶店が抱える“転売被害”
番組はさらに、人気商品が海外で転売される現場として、京都・宇治の老舗抹茶店を取材。開店前から行列ができ、開店と同時に外国人観光客が一目散に抹茶を手に取っていく。購入制限は「1人5個まで」だが、20分で完売。
調査すると、同じ抹茶が海外の通販サイトで定価の3〜4倍の価格で販売されていた。中には賞味期限切れの商品まで出回っているという。
代表取締役の中村省悟さんは「せっかく丁寧に作った抹茶を、どこで買ったかわからないルートで手にした人が“まずい”と感じてしまうのが悲しい」と語った。転売によってブランド価値が損なわれるリスクに、老舗の誇りが傷つけられている。
“せどり”は悪なのか?生活を変えた人たちの現実
番組では、“転売=悪”という構図とは異なる、もう一つの側面も描かれた。
運送会社に勤める33歳の男性、ゆきんこさん。副業として中古品の“せどり”を始め、3年で4800万円を稼いだ。扱うのはワイヤレスイヤホンの「右耳だけ」「ケースだけ」など、壊れた部品を修理して再販するスタイル。古物商許可を取得し、正規ルートでビジネスを行っている。
また、フィルムカメラ人気の再燃により、修理や分解を学んで転売する人も増加。1000円で仕入れたジャンク品が、手を加えることで1万円前後で売れる。月に80万円の利益を上げる人もいるという。
さらに、中国から安価に仕入れた商品を国内で販売することで生活を立て直したシングルマザーも登場。彼女は車用USBプラグを輸入し、月に40万円の売上を記録。「子どもの学費を払うために始めた。せどりがなかったら今の生活はなかった」と話す姿は印象的だった。
“転売コンサル詐欺”という新たな罠
一方で、転売ブームの裏には“詐欺”も横行している。番組で紹介されたのは、20代女性の被害例。
彼女は「在宅で月50万円稼げる」という求人広告を見て応募したところ、転売ノウハウを教えるという名目でコンサル料110万円を請求された。さらに「仕入れパック90万円」を勧められ、カードで分割払い。届いた商品は、ほとんどが価値のない粗悪品だった。
国民生活センターによると、こうした“転売コンサル詐欺”の相談が急増しており、なかには総額200万円以上の被害もあるという。被害を防ぐには、支払い履歴ややり取りの保存が重要。弁護士の助言を受けながら、返金交渉を行うことが勧められている。
所ジョージと重盛さと美のコメントが示す“転売の本質”
番組終盤、所ジョージは「食べるものよりカードを優先するなんて、生き物としてどうなんだ」と語り、転売騒動の異常さをユーモアを交えて指摘した。
一方、重盛さと美は、自身の写真集が転売されていた経験を語った上で、転売に対する複雑な心情を吐露。「数分前まで転売ヤーを憎んでいたのに、今のVTRを見て少し考えが変わった。転売されたことで、自分の作品が誰かの希望や自信になっているのかもしれない」と話し、スタジオの空気が一瞬静まった。
最後に彼女は、印象的な言葉を残した。
「転売は人生を懸けてやるものじゃない。『もうける』は欲、『もうかる』は道。人のために道を歩んでいけば、自然と利益はついてくる。」
この一言には、番組全体のテーマである“お金と倫理”の関係が凝縮されていた。
“儲ける時代”から“信頼を積み上げる時代”へ
転売ビジネスは、SNSとフリマアプリの普及によって爆発的に拡大した。しかし、買い占めや詐欺まがいの行為が増える一方で、「誰かの笑顔を奪う商売」への反発も強まっている。
企業側も、購入制限や抽選販売、転売禁止条項などを強化しているが、抜け道は依然として多い。大切なのは“禁止”より“選択”。消費者一人ひとりが、正しい購入行動を選ぶことが、健全な市場を守る鍵になる。
まとめ
・トレカや抹茶など、人気商品の転売が社会問題化している
・転売は違法ではないが、買い占めや詐欺まがいの行為は罪に問われる可能性あり
・“せどり”は技術と工夫次第で正しい副業になりうる
・安易なもうけ話よりも、「信頼で成り立つ経済」を選ぶ意識が重要
“儲け”を追うだけの時代は終わった。これからの時代は、“信頼を積み重ねる人”が報われる時代だ。私たちの一つの買い物、一つの判断が、その未来をつくっていく。
出典:NHK総合「所さん!事件ですよ」2025年10月18日放送
https://www.nhk.jp/p/jiken/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

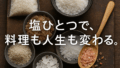
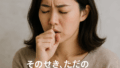
コメント