- 台風の未来は変えられるのか?“進路を変える夢”に迫った最新研究のすべて
- 台風と日本の歴史―“予測”が生まれた背景にある深刻な被害
- 未来予測の主・荒川秀俊が残した大胆すぎるビジョン
- 台風はなぜ暴風雨になるのか?“17m/秒”が境界線
- アメリカの“ドライアイス散布実験”は夢を追った挑戦
- 国家プロジェクト“ストームフューリー”の栄光と挫折
- 日本は当時“台風制御”に反対していた
- 2021年、日本が本気で動き出した「タイフーンショット構想」
- 台風を弱める“打ち水作戦”の可能性
- 世界随一の技術“台風の目に突入する観測”
- 台風制御には社会的議論が不可欠
- 結論:進路変更は難しいが“弱めること”は可能
- エンディングの言葉に込められた未来への希望
- この記事のまとめと未来へのメッセージ
- 気になるNHKをもっと見る
台風の未来は変えられるのか?“進路を変える夢”に迫った最新研究のすべて
2025年の日本にとって、台風は毎年のように向き合わなければならない自然の脅威です。この記事では『台風の進路を変えられる』という大胆な未来予測をテーマにしたNHK『未来予測反省会』(2025年11月11日放送)をもとに、歴史・技術・社会的影響までを整理しながら、読者が知りたい“台風制御のリアル”をわかりやすく紹介します。
NHK【チコちゃんに叱られる!】なぜ日本は台風を番号で呼ぶの?戦後の歴史とアジア名の違いを解説(2025年8月29日放送)
台風と日本の歴史―“予測”が生まれた背景にある深刻な被害
まず押さえておきたいのが、日本がこれまで経験してきた台風被害の大きさです。
番組では、過去の代表的な台風被害が丁寧に紹介されていました。
2018年の『台風21号』では、死者14人、公共建物1,248棟が被害を受け、経済損失は1兆678億円にのぼりました。
さらに、明治以降で最も大きな被害となった1959年『伊勢湾台風』では、死者・行方不明者が5,098人という未曽有の規模。
この甚大な被害から、「何とか台風の進路を変えられないか」、そんな未来への願いが生まれたのは自然な流れでした。
当時の新聞記事にも、科学技術の進歩とともに未来の台風対策として“進路変更”という希望が語られていたことが紹介されます。しかし、2025年の現在でも進路変更は実現していません。「なぜ夢のままなのか?」──番組はその答えに迫っていきます。
未来予測の主・荒川秀俊が残した大胆すぎるビジョン
今回“天国からの登場”という演出で紹介されたのが、台風制御の未来予測を語った気象学者 荒川秀俊。
彼が予測を寄せた書籍『21世紀への階段(第1部)復刻版 40年後の日本の科学技術』には、次のような記述があります。
「台風の災害をくいとめる方法は進路のコントロールである」
「台風を管理し奪いあって調節するというようなこともユメではない」
今読むと驚くほど先鋭的で、SFのような内容です。しかし当時は科学技術への期待が高まり、未来への明るい予測がたくさん語られた時代でもありました。
この荒川秀俊の予測を現代の視点から“反省する”ため、3人の専門家が登場しました。
・台風シミュレーション研究の第一人者 佐藤正樹
・スーパー台風を直接観測した 坪木和久
・台風制御の社会的影響を研究する 笹岡愛美
いずれも台風研究の最前線を支える存在で、番組の内容に圧倒的な説得力を与えていました。
台風はなぜ暴風雨になるのか?“17m/秒”が境界線
番組では 坪木和久 が、台風が強力な暴風雨になる仕組みをわかりやすく説明していました。
台風とは、熱帯地域で発生する熱帯低気圧のうち、風速17m/秒を超えたものを指します。
大量の水蒸気が上昇し、凝結しながら熱を放つことでさらに上昇気流を強める──という“熱”を使った自然システムが、やがて巨大な渦を生み出し、日本へ接近するころには非常に強い力を持つことがあります。
この基礎を押さえると、後半で紹介される「台風を弱める」技術の意味がよくわかります。
アメリカの“ドライアイス散布実験”は夢を追った挑戦
1947年、アメリカは雲にドライアイスを撒いて雨を降らせる“シーディング実験”を成功させました。
中心人物は『アーヴィング・ラングミュア』と『ヴィンセント・J・シェーファー』。
微小水滴が0℃以下でも凍らず存在している雲にドライアイスを加えると、氷の結晶が成長して落下しやすくなる──この科学的原理を利用したものです。
そこから“台風にも応用できるのでは?”という大胆な発想が生まれ、1961年のハリケーン『エスター』で実験。
結果は「最大風速10%低減」と発表されました。
国家プロジェクト“ストームフューリー”の栄光と挫折
アメリカは夢を諦めず、『ストームフューリー計画』を1962年にスタートさせました。
台風へ薬剤を撒き、構造を変えることで弱めようという壮大な計画です。
・1963年『ボーラー』最大風速20%減少
・1969年『デビー』最大風速31%減少
など、成功とされた例もありましたが、
1971年の『ジンジャー』では“効果なし”。
しかも被害はそのまま襲来し、ノースカロライナ州では約1,000万ドルの損害を受けています。
ここで大きな問題として残ったのが、
「成功なのか失敗なのか、基準がはっきりしない」
という点。
台風という複雑で巨大な自然現象を操作する難しさが浮き彫りになりました。
日本は当時“台風制御”に反対していた
番組では、日本の姿勢も明確に紹介されていました。
1971年・74年の『台風委員会』で、アメリカが
「太平洋でも実験をしたい」
と提案したものの、日本は強く反対します。
・フィリピン
・韓国
・香港
・タイ
などは賛成だったのに対し、日本は読売新聞にも反対の論調が載るなど慎重姿勢を崩しませんでした。
その背景には、自然操作による“予期せぬ影響”への不安が強くあったと考えられます。
2021年、日本が本気で動き出した「タイフーンショット構想」
時代は変わり、日本は2021年にかつてない規模で台風制御研究に着手します。
それが『タイフーンショット』構想。
中心にあるのが『台風科学技術センター』で、
・台風予測研究ラボ(ラボ長 佐藤正樹)
・台風観測研究ラボ(ラボ長 坪木和久)
・社会実装推進ラボ(笹岡愛美)
など複数の専門分野が集結した組織が立ち上がりました。
これは、台風研究としては日本史上最大級の取り組みともいえる内容です。
台風を弱める“打ち水作戦”の可能性
番組で興味深いと感じたのが、佐藤正樹 が語った“打ち水作戦”。
海面に海水を散布し、海面温度を下げることで台風のエネルギーを奪うという方法です。
台風は温かい海をエネルギー源にしているため、たとえ数℃下げるだけでも大きな効果が期待できる可能性があります。
進路を変えるのは困難でも、“弱める”ことなら現実的かもしれない──そんな希望につながる話でした。
世界随一の技術“台風の目に突入する観測”
坪木和久 が率いる観測研究ラボでは、ジェット機で台風の目に入り、無線機付き測定器『ドロップゾンデ』を落とす研究を行っています。
台風内部の温度、湿度、風速などリアルなデータは非常に貴重で、これにより予測精度が劇的に向上します。
世界でも限られた国しかできない観測技術で、日本の科学力の高さが伝わる場面でした。
台風制御には社会的議論が不可欠
科学が進めば進むほど重要になるのが、倫理や法の問題です。
笹岡愛美 は、ELSI(倫理的・法的・社会的影響)を丁寧に整理する研究を進めています。
台風制御は“恩恵を受ける地域”と“影響を受ける地域”が異なる可能性があり、意図せぬリスクも想定されます。
技術だけでなく、社会全体の理解とルール作りが不可欠だという視点は非常に重みがありました。
結論:進路変更は難しいが“弱めること”は可能
番組の議論をまとめると、台風制御の未来は次のように整理できます。
・進路を変えるレベルの制御は極めて困難
・しかし“弱める”方向の制御なら可能性が見えている
・地球全体の気候への悪影響は現時点では少ないとされる
そして、実用化の大きな目標は『2050年』。
これは長い道のりですが、2050年の日本は今とは違う“台風との向き合い方”を手にしているかもしれません。
エンディングの言葉に込められた未来への希望
番組の最後、影山優佳 は
「自然と向き合い、関わる選択肢が増えているのはありがたい」
と語っていました。
台風に挑む科学者と、社会全体が協力しながら“自然と共存する未来”を作っていこうというメッセージが温かく響いたシーンでした。
この記事のまとめと未来へのメッセージ
この記事のポイントは以下の3つです。
・台風制御は長年の夢で、多くの失敗と挑戦を経て研究が進んでいる
・日本は2021年から『タイフーンショット』という大規模プロジェクトを開始
・2050年に向けて“台風を弱める”技術が徐々に現実味を帯びている
もし台風を弱める技術が確立すれば、日本の防災は大きく変わります。
未来の安全をつくる研究は、今この瞬間も続いています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

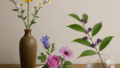

コメント