「日本人男性の平均身長は175cmになる」は実現した?未来予測の“反省会”をのぞいてみよう
私たちの体格は、どこまで進化してきたのでしょうか。昭和の時代、「21世紀には日本人男性の平均身長は175cmになる」との予測がありました。けれども、実際の平均身長は171cm前後で止まっています。なぜ予測は外れたのでしょうか?この記事では、長谷川忍(シソンヌ)と影山優佳が語り合ったNHK『未来予測反省会』(2025年10月14日放送)の内容をもとに、身長の伸びが止まった理由をわかりやすく紹介します。
NHK【未来予測反省会】“動物言語学”がついに現実に?シジュウカラの会話とAIがつなぐ「人と動物の新時代」|2025年10月7日
高度成長期の奇跡!20年で6cm伸びた日本人
番組で紹介されたのは、1971年に未来予測を立てた長嶺晋吉という研究者の存在。当時、彼は「21世紀に入る頃には日本人の20歳男性の平均身長は175cmに達し、アメリカ人(178cm)に近づくだろう」と予想しました。根拠は、戦後20年余りで6cmも伸びた驚異的な成長スピードにありました。
背景にあったのは、食の“革命”。戦後、国民の食生活は一変し、白米中心から動物性たんぱく質中心の食事へとシフト。さらに学校給食制度が整備され、子どもの栄養状態が大幅に改善しました。1960年代初頭には、給食を実施している学校とそうでない学校で、11歳男子の平均身長に明確な差が出ていたといいます。
1962年には学校給食の基準が定められ、摂取エネルギーの13〜20%をたんぱく質でまかなうよう指導されました。まさに“牛乳とパン”が、戦後の子どもたちを伸ばしたのです。
失速の始まり…1990年代からのたんぱく質離れ
ところが、その勢いは90年代半ばを境に止まります。日本人1人あたりのたんぱく質摂取量を追うと、1995年をピークに下降線を描き、今では1950年代とほぼ同水準。原因のひとつは、牛乳の消費量の減少です。1990年を頂点に右肩下がりが続き、特に若い世代では「牛乳離れ」が顕著になりました。
もしこの牛乳消費が伸び続けていたら、日本人男性の平均身長は予測通り175cmに達していたかもしれません。
長嶺晋吉の未来予測の条件には「1日80gのたんぱく質(うち40gは動物性)」「カルシウムとビタミン類の十分な摂取」が挙げられていましたが、その条件は満たされなかったのです。番組ではこれを「反省ポイント1:予想外のたんぱく質摂取量の減少」として総括しました。
“やせ志向”という新たな社会現象
1970年代後半以降、日本社会に大きな変化が訪れます。それが「やせ志向」。女性の間で「細い方が美しい」という価値観が広まり、妊娠中であっても体重増加を抑える傾向が強まりました。その結果、低出生体重児(2500g未満)の割合は約2倍に。
生まれた時に体重が少ない子どもは、その後の身長にも影響が出やすいと言われています。専門家の森崎菜穂は「母体の栄養状態が、子どもの将来の体格に直結する」と指摘。こうした社会的価値観の変化を1970年代の科学者が予測できなかったことが、次の“誤算”でした。
さらに、若い世代の運動不足も問題視されています。特に20〜30代女性の運動習慣率は60代女性よりも低いというデータも。食事を制限する一方で体を動かさない——そんな生活習慣が、日本人の成長曲線を下げたのです。
番組では「反省ポイント2:日本社会の価値観の変化まで予測できなかった」と整理されました。
江戸時代からの“身長史”が示す日本人の宿命
身長の歴史をさかのぼると、縄文時代の人々はそもそも小柄でした。狩猟採集の時代で栄養が不安定だったため、遺伝的なポテンシャルも低かったのです。
ところが、弥生時代〜古墳時代にかけて朝鮮半島から渡来人が流入し、身長が急上昇しました。逆に、江戸時代には飢饉や栄養不足により再び低下し、平均身長は155〜160cm程度にまで落ち込みました。
当時、欧米人の平均身長は170cm前後。日本人との10cm以上の差に、多くの知識人がショックを受けます。夏目漱石も『倫敦消息』で「皆厭に背が高い……ちっと人間の背に税をかけたら少しは倹約した小さな動物が出来るだろう」と記し、西洋人への劣等感を率直に綴っていました。
遺伝と環境のバランスが決める“限界点”
明治以降、日本はこの“身長コンプレックス”を克服しようと国家を挙げて栄養改善に取り組みます。富国強兵政策のもと、軍隊食には肉が導入され、戦後には母子保健政策が整備され、衛生状態も飛躍的に向上しました。こうして1950〜80年代にかけて、身長は再び上昇します。
しかし、現代の専門家たちは「日本人の身長はすでに遺伝的限界に達している」と見ています。世界114位という順位が示す通り、今の日本人男性の身長は世界的に見ると中の下。東アジア諸国と比べても低めです。
これは「ベルクマンの法則」と「島国効果」で説明されます。寒い地域の動物は体が大きくなる傾向があり、温暖な地域ほど小型化する。日本はその中間の気候帯に位置し、さらに島国として資源が限られていたため、体格の大型化には自然の制約があるのです。番組ではエゾシカやケラマジカの例を挙げ、日本人の身体的特徴を生物学的に解説していました。
新しい時代の“健康美”という価値観
最後に登場したのが国立健康・栄養研究所署長の瀧本秀美。彼女は2021年に改定された「妊産婦のための食生活指針」を紹介しました。従来は妊娠中の栄養管理に重点が置かれていましたが、今は「妊娠前からの準備」へと考え方が変わっています。
主菜(魚・肉・豆など)をしっかり取り、必要なたんぱく質を確保すること。そして、妊娠中の体重増加の基準も“制限”ではなく“健康的な増加”へと改められました。
また、世界では「ヘルシービューティー(健康美)」という価値観が主流に。パリ・コレクションでは「やせすぎモデル」の出演を禁止するなど、健康を重視したボディポジティブの潮流が広がっています。身長や体重ではなく、自分らしい体をどう育てるか——それがこれからのテーマです。
まとめ
この記事のポイントは次の3つです。
・日本人の身長は戦後の栄養改善と学校給食により急上昇したが、1990年代以降は停滞。
・たんぱく質摂取量の減少や“やせ志向”が成長を妨げた。
・遺伝的・地理的な制約もあり、今後は“健康美”の時代へ。
かつて「175cm」が理想の指標だった時代から半世紀。今、私たちに問われているのは“どれだけ背が高いか”ではなく、“どれだけ健康的で、自分らしく生きられるか”。
科学が描いた未来予測を振り返ることで、現代の「体と心の豊かさ」について考えさせられる回でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

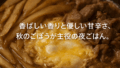
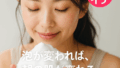
コメント