日本が台風を番号で呼ぶのはなぜ?
毎年のように日本を直撃する台風。ニュースで「台風1号」「台風15号」と番号で呼ばれるのを耳にしますが、「なぜ日本は台風に名前ではなく番号をつけるの?」と疑問に思った人も多いのではないでしょうか。実は台風には名前がついているのですが、日本ではあえて番号で呼んでいるのです。この記事では2025年8月29日放送のNHK「チコちゃんに叱られる!」で紹介された解説をもとに、台風の呼び名の歴史と理由を詳しく紹介します。読み終えれば、ニュースの台風報道がもっと理解しやすくなります。
台風に名前があるのに日本では番号?
多くの人にとって台風は「台風〇号」として記憶されます。しかし国際的には台風にも名前がつけられています。ではなぜ日本では番号を使うのか。番組ではこの疑問をテーマに取り上げました。ゲストのあのさんは「ロンドンブーツ1号2号が発祥」とユーモラスな答えをして笑いを誘いましたが、もちろん不正解。正解は「日本の台風にも名前はある!でも番号のほうが都合がよかったから」です。ここから、日本の台風呼称の歴史が解説されました。
戦後はアメリカが台風に名前をつけていた
台風とは、熱帯の海上で発生する熱帯低気圧のうち最大風速が17メートル毎秒以上に発達したものを指します。戦前の日本では台風に特別な名前をつける習慣はなく、単に「台風」と呼んでいました。状況が変わったのは戦後です。日本がアメリカの占領下にあった時代、台風に英語の名前をつけることが定められました。当時は女性の名前をつける習慣があり、「台風ジェーン」「台風キャサリン」などと呼ばれています。
しかし、ここで問題が発生しました。台風かどうかの判断は各国が独自に行っていたため、日本が「台風」と判断しても、アメリカが認めない場合には名前がつかないという事態が起こったのです。例えば日本列島に大きな被害をもたらしても、アメリカが「これは台風ではない」と扱えば、名前はつかないまま。情報の整理や共有に大きな混乱を招きました。
1953年から番号制に切り替え
こうした混乱を解消するため、日本は1953年から「台風を番号で呼ぶ方式」を導入しました。独立国として主権を回復した翌年の決断です。番号なら、発生順に整理でき、誰が見ても理解できます。「台風5号」と聞けば、その年の5番目の台風だと直感的にわかるのです。これにより、国内での情報伝達が飛躍的にスムーズになりました。
この「台風番号制」は70年以上たった今も続いています。災害時に混乱を避けるための合理的な工夫として定着し、台風の報道では欠かせないものになりました。
2000年以降はアジア名も導入
2000年からは国際的な取り組みとして、台風委員会(世界気象機関と国連の枠組みで設立)が発足し、アジア各国が台風に名前をつける仕組みが始まりました。日本、中国、韓国、フィリピン、ベトナムなど14か国・地域が参加し、それぞれの国が提案した名前を順番に使っています。日本からは「ヤギ(星座のやぎ座)」「カジキ(魚の名前)」などが登録されています。
つまり、台風には国際的な「アジア名」が公式に存在します。例えば「台風カジキ」という名前が国際機関では使われているのです。しかし日本国内では依然として番号で呼ぶのが主流。理由は単純で、外国語の名前は日本人にはなじみにくく、覚えにくいからです。ニュースや天気予報で伝える際、番号のほうがわかりやすく、情報の誤解も少なくて済むのです。
番号で呼ぶことのメリット
日本が番号を使い続けているのには明確な利点があります。
-
シンプルで分かりやすい:発生順なので誰でも理解できる
-
過去との比較が容易:「昭和28年の台風13号」といった形で記録を整理できる
-
災害情報で混乱を防げる:外国語の名前より報道に適している
-
短く伝えやすい:「台風15号接近中」といえば即座に伝わる
災害時に大切なのは、迅速で正確な情報伝達です。番号はその点で非常に実用的な方法といえます。
番組での専門家解説
「チコちゃんに叱られる!」では気象庁の福田さんが登場し、戦後から現在までの台風呼称の歴史を解説しました。日本が台風を番号で呼ぶ背景には、戦後の占領政策、国際的なルール、そして日本人の生活文化に合った情報伝達方法という複数の要素が絡んでいることが分かります。
番組では、あのさんのユーモアあふれる回答や、チコちゃんの叱りによってスタジオは笑いに包まれましたが、最終的には専門的な解説で視聴者も納得できる内容でした。
よくある疑問Q&A
Q:台風に名前は本当にあるの?
A:はい。2000年以降、アジア各国がつける名前(アジア名)が存在します。ただし日本ではあまり使われていません。
Q:アメリカ式の名前はもう使われていないの?
A:はい。戦後しばらくは使われましたが、1953年以降は日本独自の番号制になりました。
Q:アジア名はどんな名前があるの?
A:動植物や自然現象、神話由来のものが多いです。例:「テンビン」「バビンカ」「コップ」など。
Q:日本でも名前を使うことはある?
A:国際的な情報では名前が併記されることもありますが、国内のニュースではほとんど番号が使われます。
まとめ
日本が台風を番号で呼ぶのは、戦後の混乱を避け、情報を正しく共有するために選ばれた方法でした。1953年に番号制が導入されて以来、70年以上にわたり使われ続けています。2000年からはアジア名もつけられていますが、日本では覚えやすさと分かりやすさを重視し、依然として「台風〇号」と呼ぶのが主流です。
-
台風には名前があるが、日本では番号が中心
-
戦後のアメリカ式命名の混乱を避けるために番号制が導入された
-
番号はシンプルで災害情報の伝達に最適
-
今もニュースや天気予報で番号が使われている
次に「台風○号」のニュースを耳にしたときには、その呼び名の背景にある歴史や国際ルールを思い出してみてください。何気ない「番号」の裏には、災害と向き合ってきた日本人の知恵が隠されているのです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


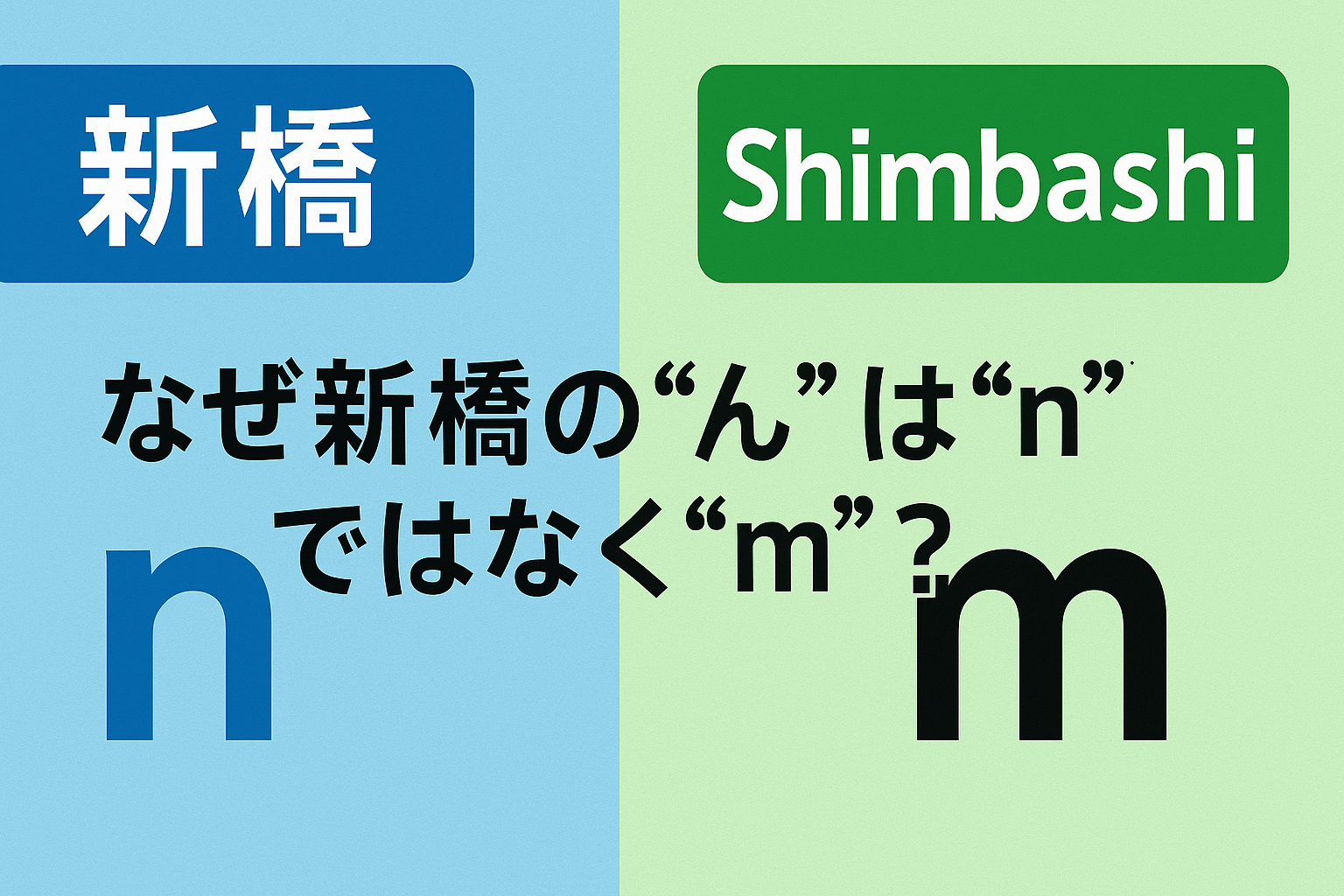
コメント