走れ 挑戦の魂〜F1 30年ぶりの世界一〜|2025年4月5日放送回まとめ
2021年、世界最速のレースF1でホンダが30年ぶりに世界一に返り咲きました。かつてアイルトン・セナを乗せて最強を誇ったホンダF1が、再び世界の頂点へと登り詰めた裏側には、ある“伝説の男”と若き技術者たちの熱い物語がありました。NHK総合で放送された『新プロジェクトX〜挑戦者たち〜』では、ホンダの技術者たちが挑んだ夢と試練の軌跡が描かれました。
本田宗一郎の夢から始まった挑戦
ホンダがF1に挑戦したのは、まだ会社としての実績も乏しかった1960年代のことです。創業者・本田宗一郎が「世界一の技術者になるには、世界最速の舞台で戦うべきだ」と語り、F1参戦を宣言しました。当時、ホンダは四輪車の販売実績すらなかったにもかかわらず、この挑戦に踏み切ったのです。
-
1964年にF1世界選手権へ初参戦
-
わずか3年後の1965年、メキシコGPで日本初となるF1優勝を達成
-
日本の技術が世界で通用することを証明する大きな一歩となりました
そこからホンダは自動車メーカーとしての存在感を一気に高め、世界の舞台へと歩みを進めていきます。そして1980年代後半、F1第2期ではエンジンサプライヤーとして復帰し、マクラーレンとのコンビで黄金期を築きます。
-
1988年、マクラーレン・ホンダは16戦15勝という驚異的な成績を残す
-
アイルトン・セナ、アラン・プロストという2人の天才ドライバーがホンダエンジンで戦った
-
世界のF1関係者から「ホンダのエンジンは最強」と絶賛されました
しかし1990年代、バブル経済の崩壊により日本全体が苦境に陥ります。ホンダも例外ではなく、1992年をもってF1からの撤退を決定します。ここから会社は大きな方向転換を迫られます。
浅木泰昭はこのタイミングでF1開発から離れ、軽自動車部門へと異動となりました。周囲からは「F1にいた人間が軽なんて…」という声もあったとされますが、浅木は全く気にせず、「他社のまねは決してするな」という信念で開発を進めました。
-
軽自動車の「狭くて妥協の産物」というイメージを打ち破る新設計を導入
-
天井を高くし、室内空間を広くとった設計
-
ファミリー層や高齢者にも使いやすいことを意識した乗降性や視界の良さも追求
こうして誕生したのが「N-BOX」です。「こんなに広い軽は見たことがない」と評され、たちまち大ヒット。販売台数は全国でトップを記録し、軽自動車市場の常識を変える存在となりました。
浅木はF1という世界最高峰の舞台で培った「設計の考え方」「こだわり」「責任の重さ」を、軽自動車開発にも生かしていたのです。この経験が、のちにF1に戻ったときに再び力を発揮する原点となりました。ホンダのF1挑戦は、夢から始まり、撤退と再起、そして市販車の改革へと続く大きな流れを形づくっていきます。
ハイブリッド化で技術の壁に直面
2013年、F1は新たな時代に突入しました。エンジンはガソリンだけではなく、電動モーターを組み込んだハイブリッド仕様のパワーユニットが義務づけられ、エンジニアにはまったく新しい開発が求められました。ホンダは「この技術で世界と戦うことで、次世代のものづくりに生かせる」と考え、F1への再参戦を決めます。
しかし、ホンダの復帰は2年遅れでした。すでに他チームはハイブリッド技術を完成させており、ホンダは最初から大きなハンデを背負う形になりました。
-
初年度のエンジンは馬力不足で、直線では他車に追い抜かれることが多発
-
冷却システムやモーターの連携にも課題があり、完走すら難しいレースもあった
-
世界のトップドライバーからも「このマシンでは戦えない」と言われるほどの惨状
この事態を打開するために、ホンダは社内から実力派の技術者を次々とF1チームに招集します。
-
エンジン設計のスペシャリスト・角田哲史は、全体の設計思想を根本から見直す役割を担う
-
若手ながら実力を買われた田岸龍太郎は、馬力を上げる方法を徹底的に探る役目を任された
2人は何度も試作と検証を繰り返し、データを積み上げながら少しずつ性能を改善していきます。それでも思うように結果は出ず、レースでは連続して失敗が続きます。チーム内の士気も下がり、外部からの批判は一段と厳しくなっていきました。
そんな中、ホンダ上層部はある決断を下します。長年、社内で“技術の柱”として活躍してきた浅木泰昭をF1チームの現場に呼び戻すというものでした。彼はすでに定年まで半年と迫っており、一度はこの要請を断ります。
しかし、今の若手が失敗の責任を背負って終わってしまうのではと感じ、「今こそ自分が動くべきだ」と決意。浅木は現場に復帰し、技術だけでなく組織としての再起にも向き合うことになります。
現場にはすでにハイブリッド開発で疲弊した技術者たちがいました。浅木はまず、彼らの声に耳を傾け、「何ができて、何ができていないのか」を一つずつ整理し直すところから始めます。
設計図の見直し、開発フローの短縮、テストデータの分析方法まで、彼の手は細部にまで及びました。浅木が口にしたのは「技術は必ず壁を越える。そのためには一体感が必要だ」という信念でした。こうして、苦しんでいたF1チームは少しずつ光を見いだし始めたのです。
世代を超えた技術者の衝突と成長
浅木泰昭がF1の開発現場に復帰したとき、チームには複雑な空気が流れていました。彼の着任を歓迎する声ばかりではなく、「軽自動車の人にF1の最前線がわかるはずがない」という否定的な意見も少なくありませんでした。
しかし浅木はその反応を真正面から受け止めました。むしろ「反発こそが成長のきっかけになる」と考え、現場に毎日足を運ぶようになります。設計室や実験施設をまわり、若手技術者に声をかけ、一人ひとりの目線で話をし、疑問点や不満を共有していきました。
-
設計ミスや課題が出たときでも、怒鳴ることはせず、まず意見を出し合う環境を作る
-
技術的なアイデアにはすぐに手を動かして試すことを大切にした
-
データでは見えない「現場の感覚」を、浅木自身が一緒に確認しながら進めた
こうした日々の積み重ねで、次第に若手たちの表情にも変化が出てきます。「この人は、ただ命令する上司ではない」と気づいた技術者たちは、意見を率直にぶつけるようになりました。設計の細部をめぐっては激しい議論になることもありましたが、そこには上下関係は存在せず、「良いモノをつくる」という目的で全員がぶつかり合っていました。
浅木の着任から3か月ほど経った頃、若手技術者の高橋真嘉から「高速燃焼に関するすごいデータが出た」という報告が届きます。これは燃焼効率を飛躍的に高める技術で、理論上はエンジンの出力を大きく引き上げる可能性を秘めていました。
-
高速燃焼の技術は、パワーを引き上げる一方で、制御が難しく、暴走すればパワーユニットを壊すリスクもある
-
安定性が不安視される中で、浅木は「すぐにレースで使え。責任は自分が取る」と背中を押す
若手たちは浅木の決断に応えるため、何百枚もの設計図を書きました。それぞれの部品が高速燃焼に耐えられるか、振動や熱による影響をどこまで抑えられるか、すべてを見直して調整していきます。
-
設計責任者の角田哲史は、全設計に目を通し、細かな部分にまで目を配りながら改善点を次々に指示
-
チーム全体が、「この新技術で勝ちたい」という気持ちで一つにまとまりました
この時期、浅木の存在は単なるリーダーではなく、技術者たちにとって「背中を見て学ぶべき人」として大きな信頼を集めていました。そして現場には、かつてなかった一体感と集中力が生まれていたのです。こうして、ホンダのパワーユニットは少しずつ世界を狙える水準へと進化していきました。
F1撤退通告と最後の挑戦
2019年、ホンダはついにF1の表彰台の常連となり、年間3勝を挙げました。パワーユニットの進化は明らかで、誰もが「次こそ世界一」と感じていたタイミングでした。しかし、世界を襲った新型コロナウイルスの影響で状況は一変します。ホンダは800億円という巨額の赤字を抱え、F1からの撤退を本社が決定します。
この知らせに現場の技術者たちは大きな衝撃を受けました。数年かけて積み重ねてきた努力が水の泡になってしまうような思いでしたが、浅木泰昭はその空気を一変させます。「最後のシーズン、絶対に勝とう」と言い切り、技術者たちを前へと導きました。
-
勝つためには、2年先の投入予定だった新骨格パワーユニットを半年で仕上げる必要がある
-
5000を超える部品をゼロから設計し直し、信頼性と高出力の両立を求めた
-
浅木の「いま持てる力すべてを注げ」という言葉で、開発チームは総力をあげて挑む体制に入りました
開幕前のわずか数週間で新型パワーユニットが完成。2021年3月、バーレーングランプリで初戦を迎えたホンダは、絶対王者メルセデスと互角に戦い、2位入賞を果たします。この一戦で「今年のホンダは本気だ」と世界が認めました。
その後のシーズンもレッドブル・ホンダは快進撃を続け、一時はポイントでメルセデスを上回ることに成功。しかし中盤以降、メルセデスがパワーアップしたことで再び逆転されてしまいます。技術者たちは焦りと悔しさに包まれましたが、そこで立ち上がったのが、かつて浅木とぶつかり合っていた若手たちでした。
-
新しいバッテリーの構造と、オーバーテイクボタンという“最終兵器”の開発に成功
-
オーバーテイクボタンは、バッテリーに蓄えた電力を一気に放出し、数秒間だけ加速力を極限まで高める仕組み
-
かつて意見が合わなかった若手が、自ら開発を担い、最後の決戦に希望を持ち込んだことはチームの絆を象徴する出来事でした
そして迎えた最終戦、アブダビGP。ホンダとメルセデスは同点。勝ったほうがそのまま世界王者という緊張感あふれる展開となりました。
レース終盤、メルセデスがリードするなか、レッドブル・ホンダはわずかにその背後に迫っていました。そして最終ラップ、オーバーテイクボタンを使用するタイミングで、ドライバーに指示が出されます。ボタンを押し、バッテリーの全エネルギーを解き放ち、ホンダは最後の1周で逆転勝利をおさめたのです。
この瞬間、F1界におけるホンダの30年ぶりの世界一が決定しました。栄光の瞬間の裏には、撤退という逆風を力に変えた技術者たちの執念と、新旧がぶつかりながらも認め合った“技術の魂”のバトンリレーがあったのです。
未来へ続く挑戦のバトン
2021年12月、ホンダはF1を再び撤退。しかし浅木は社内に技術を蓄積し、電気自動車や空飛ぶクルマへの応用に備えていました。そして2023年5月、ホンダは2026年からのF1復帰を発表。新たなリーダーは角田哲史、馬力向上の責任者は田岸龍太郎。創業者・本田宗一郎の「最も困難なものに挑戦せよ」という言葉が、今も脈々と息づいています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


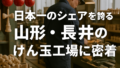
コメント