江戸吉原で生まれた甘露梅とは?遊女の思いが詰まった伝統菓子に注目
2025年6月9日(月)放送予定のNHK Eテレ『グレーテルのかまど』では、江戸吉原で生まれた伝統菓子「甘露梅(かんろばい)」が取り上げられます。この小さな和菓子には、江戸時代の遊女たちがこめた思いと、華やかな遊郭文化の歴史が詰まっています。
江戸の華やかさと裏側を映す甘露梅のはじまり
甘露梅は、江戸時代の新吉原で生まれた小さな砂糖漬けの和菓子です。材料はシンプルで、青梅の種を取り除き、紫蘇の葉で包んで砂糖にじっくり漬け込んだもの。味はやさしい甘さと紫蘇の香りが重なり、さっぱりとした上品な風味が楽しめます。この菓子は、一粒一粒手作業で仕込まれ、およそ半年から一年半もかけて完成させるという手間のかかったものでした。
作られるきっかけは、吉原の遊女たちが年の瀬に上客に贈る“お年始の贈り物”として始まったとされています。梅の実が実る5月ごろから仕込みを始め、翌年の正月をさらに越えて、2年後のお正月にようやく渡すという、時間と手間のかかるおもてなしでした。
また、当時のガイドブック『吉原細見』にもこの菓子の名が登場しており、吉原の名物として親しまれていたことがわかります。製造元としては「松屋庄兵衛」という名も伝わっており、商家による商品としても流通していたようです。
甘露梅に込められた遊女たちの思いと工夫
吉原の遊女たちは、客との関係を築くうえで「贈り物」を大切にしていました。中でも甘露梅は、特別な上客にのみ配られるもので、贔屓をつなぎとめるための心づかいの象徴でもありました。
仕込み作業には遊女だけでなく女中たちも総出で取り組み、種取り、しその葉包み、瓶詰め、砂糖の調合といった工程が丁寧に行われていたとされています。当時は砂糖が非常に高価だったため、甘露梅はたいへん贅沢な一品でした。
こうした背景を考えると、単なる和菓子ではなく、吉原という閉ざされた世界の中で、女性たちができる限りの工夫と誠意を込めて贈った、人と人とのつながりを結ぶ手作りの証とも言えます。
この菓子は、江戸の町でも話題となり、吉原からの土産としても人気を集めました。当時の庶民は直接吉原に出入りする機会は少なかったものの、甘露梅の名は広く知られていたようで、川柳などにも詠まれています。
-
「寺からと 女房を騙す 甘露梅」
-
「甘露梅 内儀の口に 唾がたまり」
これらの句は、吉原帰りの男が甘露梅を妻に持ち帰って誤魔化す様子や、その香りや美味しさに妻がつい期待してしまう情景を描いており、当時の人々の暮らしと甘露梅の存在感を感じさせます。
現代に残る甘露梅の姿と味わいの変化
時代が進み、吉原という場所が消えた後も、甘露梅の名前と文化は形を変えて残っています。現在では、山形や小田原などの梅の名産地で、餡入りの求肥を紫蘇の葉で包んだ和菓子が「甘露梅」として販売されています。
この現代の甘露梅は、かつての製法とは異なるものの、「紫蘇の香り」「贈り物にふさわしい上品な味わい」「梅の季節の和菓子」という特徴を継承しており、昔ながらの伝統がいまも息づいていることを感じさせます。
特に小田原では、吉原にルーツをもつ甘露梅を再現した銘菓が人気を集めており、贈答用や茶席のお菓子として親しまれています。パッケージや販売時の説明にも、江戸の歴史や遊郭文化とのつながりが紹介されており、文化的背景を伝える一助となっています。
甘露梅の作り方と保存方法
江戸時代中期、吉原の女性たちが心を込めて作っていた伝統の和菓子「甘露梅(かんろばい)」。白あんに梅の甘露煮を混ぜて香り豊かに仕上げたあんを、もちもちの求肥で包み、さらに梅の香りを含んだ赤紫蘇の葉でくるんだ一品です。食べると五感にやさしく広がる風味と食感が楽しめます。
材料(12個分)
【梅あん】
-
白こしあん:300g
-
水:100ml
-
梅の甘露煮:50g(種を除いて刻む)
【求肥】
-
もち粉:100g
-
水:90ml
-
上白糖:200g
-
片栗粉(手粉用):適量
【仕上げ】
-
水:160ml
-
グラニュー糖:80g
-
赤紫蘇の梅酢漬け:12枚
梅あんをつくる手順
-
梅の甘露煮は種を取って細かく刻み、風味が出やすくなるようにしておきます。
-
鍋に白こしあんと水を入れて中火にかけ、木べらですくってゆっくり落ちるくらいの固さになるまで炊きます。
-
刻んだ甘露煮を加え、さらに火にかけて梅の香りが立つまで混ぜながら炊き上げます。
-
梅の香りがふわっと立ってきたら火を止め、バットやトレイに広げて冷まします。粗熱が取れたら1個25gずつに丸めておきます。
求肥を準備する
-
もち粉に水を加え、耳たぶくらいのやわらかさになるまでしっかりこねます。
-
生地は4等分に分け、それぞれを平たくのばして真ん中に穴を開けておきます(熱が通りやすくするため)。
-
お湯を沸かしておくことも忘れずに。
求肥をつくる
-
沸騰したお湯に先ほどの生地を入れて約5分間ゆでます。
-
浮かび上がってふくらんできたら火を止めて取り出し、別の鍋に移します。
-
弱火にして手早く練りながらひとつにまとめます。
-
上白糖を3回に分けて加え、そのたびに鍋肌から少しゆで汁を加えながら、なめらかになるまで練り続けます。
-
手にくっつかなくなってつやが出てきたら完成です。
あんを包む
-
できあがった求肥を手粉(片栗粉)を広げた台にのせ、25gずつに分けて丸めます。
-
それぞれを平たくのばし、梅あんをのせて、外側から少しずつ引っ張るようにしてしっかり包み込みます。
仕上げの準備
-
水とグラニュー糖を鍋に入れて火にかけ、完全に溶けたら火を止めて冷まし、シロップを作ります。
-
赤紫蘇の梅酢漬けは、このシロップに3時間以上しっかり浸けておきます。
-
使う直前に取り出し、キッチンペーパーなどで余分なシロップをやさしく拭き取ります。
仕上げ
-
赤紫蘇の葉の上に、梅あんを包んだ求肥を閉じ目を上にして置きます。
-
そのまま葉をやさしく包み、下に向けて置いて軽く手のひらで押して整えます。
-
閉じ目を上にすることで、紫蘇で包んだときに表面がなめらかで美しく仕上がります。
食べごろと保存方法
甘露梅は常温で保存するのが基本です。冷蔵庫に入れると、求肥が固くなってしまい、香りも飛んでしまうためおすすめできません。風通しのよい涼しい場所で保管してください。
-
保存期間は作った翌日までが目安です。
-
翌日を過ぎると、求肥が乾燥して弾力が失われたり、赤紫蘇の色合いや香りも弱まります。
-
保存時はひとつずつラップで包むか、乾燥しないように密閉容器に並べて入れると良いです。
-
赤紫蘇は色移りしやすいため、布巾や紙で包むときは清潔で使い捨てできるものを選びましょう。
-
湿気が多い日は、乾燥剤や通気性のある容器も併用すると安心です。
甘露梅は、作ってから半日~翌日が一番おいしいタイミングです。時間をおくことで、赤紫蘇の香りが求肥と梅あんになじみ、味がまろやかになります。食べる直前に軽く手のひらで整えると、形もふっくらして美しく見えます。
口に入れると、ふんわりやわらかい求肥と、ほんのり甘酸っぱい梅の香り、紫蘇のさわやかな風味が重なり、しっとりとやさしい味わいが広がります。まさに江戸の女性たちが大切にしてきた「五感で楽しむ和菓子」といえる逸品です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

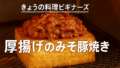
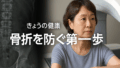
コメント