高齢者とペット 共に暮らし続けるために
2025年6月30日放送のNHK「午後LIVE ニュースーン」では、高齢者とペットの共生について特集が放送されました。ペットは大切な家族の一員ですが、高齢になると最後まで世話ができるか不安を感じたり、実際に飼うことを諦める人も多くいます。番組では、高齢者がペットと安心して暮らし続けるための新しい取り組みや、具体的なサポート事例が紹介されました。
ペットと暮らしたいけれど諦める人が増えている現実
犬の登録頭数は、2000年を過ぎた頃から600万頭以上を維持しています。また、猫の飼育数は去年、過去最高の約916万頭となりました。しかし、ペットの数が増える一方で、飼い主の高齢化も進んでいます。京都市が65歳以上の人を対象に行った調査では、38.3%の人が「ペットを飼いたいが諦めている」と答えました。その理由には次のようなものがあります。
・急な入院などのとき世話ができない
・体力的に散歩やトイレの世話が難しい
・留守にできなくなる不安
・最後まで責任を持てるか自信がない
このように、ペットと暮らしたい気持ちがあっても、年齢による不安から踏み切れない人が多いのです。
高齢者と保護犬をつなぐシニアドッグ・サポーター制度
77歳の船橋志津枝さんは、これまで40年以上、犬と一緒に暮らしてきました。夫に先立たれた後も、愛犬と支え合いながら生活してきましたが、4年前に愛犬が亡くなり、大きな悲しみに包まれました。その後、再び犬を飼おうとしましたが、年齢を理由にペットショップや里親から断られてしまいました。
そんな中、船橋さんが知ったのが、保護団体「ドッグデュッカ」のシニアドッグ・サポーター制度です。この制度は、以下のような仕組みです。
・引き取り手が少ない高齢の犬と、飼いたくても飼えない高齢者をマッチング
・飼育は高齢者の自宅で行い、団体が必要な支援を提供
・面談や飼育環境の確認をしたうえで犬を紹介
・1週間のお試し飼育ができる
船橋さんの元には、心臓に疾患がある2匹の犬、モモとダイがやってきました。薬は団体から無料で提供され、体調が悪い時には病院へ連れて行ってもらえます。これらの費用は、しつけ教室の収益やクラウドファンディングでまかなわれています。また、船橋さんがどうしても飼えなくなった場合は、団体が犬を引き取ってくれます。この制度は2019年に始まり、これまでに90頭の犬が高齢者のもとで新しい生活をスタートさせています。
高齢者が今いるペットと安心して暮らせるサポート
すでにペットと暮らしている高齢者にとっても、将来の不安は大きいものです。京都市では、民間企業と協力し、高齢者がペットと安心して暮らし続けられる仕組みを作っています。82歳の黒井久代さんもその一人です。
黒井さんは12年前から2匹の猫と暮らしていますが、高齢になるにつれ「ずっと一緒にいられるのか」という不安を感じていました。そんな時に出会ったのが、京都市と連携している民間企業のサービスです。このサービスでは次のようなサポートが受けられます。
・飼えなくなった場合、里親が見つかるまで猫を保護
・人見知りの多い猫でもスムーズに保護できるよう定期訪問
・訪問は月に1回、1時間程度
・必要に応じて爪切りやトイレ掃除、買い物の手伝い、健康チェックも実施
・料金は月額6000円から
黒井さんはこのサービスのおかげで、安心して猫と暮らし続けられるようになりました。
ペットと暮らすことで健康面のメリットも
高齢者がペットと暮らすことで、健康にも良い影響があることが分かっています。例えば、犬を飼っている人は、飼っていない人に比べて認知症の発症リスクが40%低いという研究結果があります。また、ペットを飼っている人は、飼ったことがない人に比べて「フレイル(心身の衰え)」のリスクも0.87倍に下がるといわれています。ペットとの暮らしが、体だけでなく心の健康にもつながっているのです。
ペットと一緒に入居できるグループホームの取り組み
奈良県のグループホーム「さくら生駒」では、8年前からペットと一緒に入居できるようになりました。この施設では、80歳から100歳までの18人が10頭の犬とともに暮らしています。
82歳の荒井セイさんは、15年前に夫を亡くし、その後犬のケンタと暮らしてきました。しかし認知症の症状が出たため、施設に入居を考えましたが、2つの施設でペット同伴を断られました。ようやく見つけた「さくら生駒」では、入居前に入居者と家族の同意を得て、犬と一緒に暮らすことができました。
この施設では以下のような工夫をしています。
・犬と暮らせる人は1階、犬が苦手な人は2階とゾーニングを実施
・施設長の竹田幸代さんが動物管理士の資格を取得
・ペットが施設に慣れるようにしつけを行う
・感染症対策や掃除は職員全員が協力
犬だけでなく、過去にはハトと一緒に入居した人もいました。入居者が亡くなった場合、ペットは施設が責任を持って世話を続けます。ペットと暮らせる環境を整えたことで、入居希望者が増え、今も入居待ちが続いています。
高齢者とペットが安心して暮らせる社会へ
日本獣医生命科学大学の濱野佐代子教授は、高齢者にとってペットロスの影響は大きく、特に孤独感が深刻化しやすいと指摘しています。そのため、これからはもっと高齢者がペットと一緒に安心して暮らせる支援や受け入れ施設が増えていくことが求められています。大切な家族であるペットと、これからも安心して暮らしていける社会づくりが必要です。
【関連情報】
https://human-animal.jp/actions/pet-kouken
https://cat-operation.net/project
https://j-pettrust.com/trust
https://helpmanjapan.com/article/5839
https://env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/project/practice.html
https://nikkairen.com/news-article/news-article-1008
ペットと暮らす高齢者向け健康アドバイスコーナー

ここからは、私からの提案です。ペットと安心して暮らすためには、無理せず楽しめる工夫が大事です。特に年齢を重ねると、体力や健康面が気になる人も増えますが、ちょっとした工夫で毎日の暮らしを楽しく続けられます。
まず、犬の散歩は健康維持にとても良いですが、体への負担を考えて短時間の散歩を何回かに分けるのがおすすめです。
・15分から20分程度を目安に、1日2回くらいが無理なく続けやすいです
・リードは滑りにくくて太めのものを選ぶと、手を痛めにくいです
・転倒が心配な場合は、杖や歩行補助具を使いながら散歩すると安全です
外だけでなく、室内でもペットとふれあう時間を作ることで、心も体も元気になります。たとえば、猫の場合はおもちゃや匂いのするグッズを使って、軽い遊びを取り入れると良いです。
・パズルトイやトンネルを置いて、運動と頭の刺激を同時にできます
・おやつを中に入れられるボールで遊ぶと、楽しみながら食事ができます
犬の場合は、しつけを兼ねたふれあいがおすすめです。
・「お手」「待て」などの簡単なトレーニングを毎日少しずつ行うと、頭の運動になります
・おもちゃを使った引っ張りっこも、飼い主とペットの絆が深まります
ペットの高齢化が進んでいるため、介護グッズの利用も役立ちます。
・ベッドやソファに上がるためのスロープや階段を設置すると、足腰への負担が減ります
・フローリングには滑り止めマットやカーペットを敷いて、滑って転ぶのを防げます
・寝たきりのペットには厚みのある低反発ベッドがおすすめです。寝返りがしやすく、床ずれの予防にもなります
また、健康を保つためには定期的なケアも必要です。
・動物病院で半年に1回は健康チェックを受けると、病気の早期発見につながります
・歯磨きや歯石除去も大切です。口のトラブルは体全体の健康に関わります
・食事は高齢ペット用のフードを選び、消化が良く、体重管理しやすいものにすると安心です
年齢とともに視力や聴力が落ちることもあるので、家の中をペットが安心して移動できるように環境を整えましょう。
・家具の配置をなるべく変えないことで、ペットが迷わず動けます
・段差をなくしたり、階段にゲートを付けたりして、事故を防ぎます
このように、簡単な工夫や道具を取り入れることで、高齢者もペットも安心して楽しく暮らせます。小さなことの積み重ねが、毎日の安心と元気につながるのです。
【ソース】
https://www.akc.org/expert-advice/health/making-home-accessible-for-senior-dog/
https://wofainc.com/blog/senior-pet-care/
https://www.smalldoorvet.com/learning-center/wellness/keeping-your-dog-entertained-indoors/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

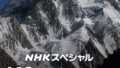

コメント