中高年の心の危機をどう乗り越える?モヤモヤから抜け出す方法とは
2025年7月9日放送のNHK総合「クローズアップ現代」では、「中高年が陥る心の危機 モヤモヤから抜け出すには?」をテーマに、人生の折り返し地点で感じる不安や喪失感、モヤモヤと向き合うヒントが紹介されました。IT業界で長年働いてきた男性、親の介護をしてきた女性、そして芸能人たちのリアルな体験を通して、同じ悩みを抱える人たちに向けた、優しくて前向きなヒントが詰まった放送でした。
セカンドライフ研修がきっかけで人生の土台が揺らいだ男性の体験
千葉県に住む西村秀久さんは、IT業界で30年以上キャリアを築き、2人の息子を育てあげた真面目な父親です。そんな西村さんが心のあり方に大きな変化を感じたのは、会社で受けたセカンドライフ研修がきっかけでした。「これからの人生をどう生きるか」と問われた瞬間、今まで順調だったはずの人生がぐらついたのです。焦りから本を読みあさっても、求めている答えは見つかりませんでした。西村さんは、仕事も子育ても一段落した40代後半から50代にかけて、自分の存在意義がわからなくなるような不安感と向き合うことになったと語ります。
こうした心の揺らぎは、ミッドライフクライシス(中年の危機)と呼ばれるもので、特別な人にだけ起きることではなく、誰でも直面しうるものです。家庭でも職場でも「求められること」が減ってくる時期、心にぽっかり穴が開いたような感覚に悩まされる人は少なくありません。
介護と喪失、そして更年期が重なった女性の深い孤独
荒井美雪さんは、40歳を過ぎてから仕事を辞めて両親の介護に専念しました。親の看取りという大きな節目を経て、自分のこれからをゆっくり考えようとしていた矢先に、妹をがんで亡くしてしまいます。大切な家族との別れという深い喪失感に襲われた荒井さんは、同時に更年期特有の体調不良にも悩まされ、ついには外に出ることもままならなくなってしまいました。
そんな中でも、彼女が唯一できたのは、ノートに辛い気持ちを綴ること。感情を吐き出すように、ただひたすら言葉にしていくことで、少しずつ気持ちが整理されていきました。「言葉にすることは、自分を認めることにつながる」。そんな実感を得ながら、少しずつ立ち上がっていったのです。
年齢による脳の変化と心の不安のつながり
心のモヤモヤには脳の変化も関係しています。東北大学の研究では、40代後半から脳の前頭前野と海馬が萎縮し始める傾向があるとされ、これが不安やストレスの制御を難しくする原因のひとつになっています。実際に約400人の脳画像を分析したところ、「知的好奇心」が強い人ほど、脳の萎縮が抑えられていたことが明らかになりました。
つまり、新しいことに興味を持ち続けることが、心の安定にもつながるということです。年齢を理由に好奇心を閉じてしまうのではなく、「やってみたい」と思えることに出会う機会を大切にすることが、メンタルヘルスにとっても非常に効果的です。
自分史をつくることで“好き”を再発見した母の実践
神奈川県川崎市の佐藤さんは、2人の子どもを育てる母親です。仕事と家庭に追われる中、自分の気持ちを見失いかけていた彼女は、「自分史」という手法を使って過去を振り返ることにしました。出来事と気持ちの変化をグラフ化してみると、もっとも気分が落ち込んでいたのは25歳のころ。孤独な子育てに悩んでいた時期でした。
けれど、その後のグラフはしっかりと上向きに。「落ちた時期にも必ず上がるタイミングがある」ということに気づけたことで、自分の人生に対して前向きな見方が持てるようになりました。過去の経験を知ることは、未来へのヒントにもなるのです。
モヤモヤを仕分けて“願い”に変えるコツ
スタジオには、タレントの大久保佳代子さんが出演し、「50代になってから急にモヤモヤすることが増えた」と語りました。そんな彼女に対し、公認心理師の中島美鈴さんは「モヤモヤの仕分け」という方法を紹介しました。これは、悩み事を細かく書き出すのではなく、「こうなりたい」「こうしたい」という願望の形で書くことで、本当に求めているものが見えてくるという考え方です。
番組では、自分の“好き”を見つけるヒントとして、以下のような視点も紹介されました。
-
過去を振り返って心が動いた出来事を見る
-
今の気持ちや願いを書き出す
-
書店でつい立ち止まるジャンルを意識する
-
スマホの写真フォルダに多く残っているテーマを確認
-
嫌いな人の共通点を探って逆に自分の価値観を知る
このように、自分の内面と向き合う方法はたくさんあります。やみくもに前向きになるのではなく、「自分は何が好きなのか」を丁寧に見つけていくことが、再出発の第一歩になります。
家事と夫婦関係の見直しから得た「自分の時間」
渡辺満里奈さんは、エッセイで「自分ばかりが家事をしていることに違和感を感じていた」と綴っています。転機は、夫の名倉潤さんがうつ病で2か月間休養したとき。その期間に夫婦でじっくり話し合い、家庭内での役割や思いを共有し合いました。現在は、家族にも家事を任せるようになり、自分の時間を持つことで気持ちが楽になったと語っています。
人が集う新しい居場所「タノバ食堂」の誕生
51歳で早期退職を決めた宮本義隆さんは、退職後に仕事仲間との関係が一気に減り、社会的な孤独を感じるようになりました。そんな中、かつての同僚と話し合って生まれたのが「タノバ食堂」です。この食堂は、料金も自由、誰でも参加でき、職業や年齢に関係なく人が集まれる場所です。「家でも会社でもない、自分の居場所がほしかった」。その思いがかたちになった新しい場は、今多くの人にとっての“よりどころ”になっています。
ありのままの自分を認めるという新しい自信
中島美鈴さんは、「人は生まれながらに“愛されたい”“認められたい”という欲求を持っている」と語ります。けれど、年齢を重ねると、その欲求を満たす機会が減り、自尊心が揺らぎやすくなります。そんなときこそ、「できる自分」ではなく、「そのままの自分を受け入れる力」が必要です。
大久保佳代子さんも、「トークがうまくできなかった日でも、自分を責めすぎないようにしている」と語りました。理想を少し下げることで、自分をほめてあげられるようになるのです。
言葉にすることが心をほどく
番組の最後には、荒井美雪さんが詩の仲間たちの前で、自作の詩を朗読する様子が紹介されました。苦しいときに書いた詩を声に出して人に伝える。その行為は、感情の整理であり、他者とのつながりを感じる小さな一歩でもあります。思いを言葉にすることで、心の中に風が通り、前に進む力が少しずつ湧いてくるのです。
まとめ
今回の「クローズアップ現代」では、人生の後半を迎える中高年が抱えるリアルな不安や揺れ、そしてその先にある「自分らしい生き方」への道すじが、さまざまな形で描かれていました。モヤモヤを否定するのではなく、その感情を受け止めて丁寧に見つめることが、心の再生の第一歩となるのです。
関連情報
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

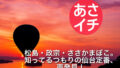
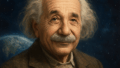
コメント