選挙ってどう選べばいいの?
2025年7月14日(月)放送のNHK「あさイチ」では、間近に迫る参議院選挙をテーマに、選挙の仕組みや投票先の決め方、SNSでの注意点など、視聴者の疑問にやさしく答える内容が特集されました。番組では初心者にもわかりやすい選挙の基本情報から、今注目されている「ボートマッチ」などのツール、投票の実践方法まで幅広く紹介され、政治が少し苦手という人でも「これなら分かるかも」と思える工夫がたくさんありました。
次回の【あさイチ】朝ドラ出演中!倉悠貴が“冷やし麺”料理に挑戦!
投票先ってどうやって決めたらいい?
街の人たちの声を聞くと、投票先の決め方は本当にいろいろです。「その人の政策をちゃんと調べてから決める」と答えた人もいれば、「なんとなくの雰囲気で選んでしまう」「正直よくわからないし、自分から積極的に調べる気にならない」という人もいました。関心の度合いや生活スタイルによって、選び方がバラバラであることがわかりました。
ボートマッチを活用する方法
そんな中、番組で紹介されたのが「ボートマッチ」という便利なウェブサイトです。これはNHKが各候補者に行ったアンケートの結果をもとに、自分の考えと近い候補者を見つけるためのツールです。最初に自分の住んでいる選挙区を選び、次に気になる政治テーマ(たとえば、子育てや経済、環境など)を選びます。その後、そのテーマに関するいくつかの質問に「賛成」「反対」などで答えていくと、候補者や政党との一致度がパーセンテージで表示されます。
この結果を参考にすることで、自分と考えが近い人を具体的に把握できるようになります。たとえば、「子育て支援が大事だと思っていたけど、それを重視している候補がこの人だったんだ」と気づくことができます。また、政党ごとの一致度もわかるので、候補者名だけでなく、政党の方向性も比較しやすくなります。
実際にこのツールを体験した出演者は、ボートマッチを複数のサイトで試してみると結果が違うこともあるという事実を挙げていました。つまり、1つのサイトの結果に頼るのではなく、いくつかのツールを活用して幅広く情報を見たうえで、自分の意見を固めていくのが大事だとされています。
実際に候補者に会って話を聞く
また、投票の判断材料として「候補者の演説を直接聞きに行く」という体験も紹介されました。街頭演説を見に行くことで、テレビやネットでは分からなかった候補者の人柄や話し方、姿勢などを直接感じることができます。演説の場に足を運ぶと、その人の思いが伝わりやすく、印象が大きく変わることもあるそうです。とくに、もともとあまり印象がよくなかった候補でも、実際に話を聞くと「意外といいこと言っている」と思えたり、逆に「やっぱり少し違うかも」と冷静に判断できたりします。
このように、インターネットでの情報と、実際に会って感じた印象の両方を参考にしながら、自分で納得のいく選び方をしていくことが大切であると番組では伝えていました。選挙は難しそうに見えても、身近なテーマから一歩ずつ考えることで、自分に合った投票先が見えてくるかもしれません。
投票所に何を持っていってもいいの?
投票所に行くとき、何を持ち込めるのか不安に思う人も多いですが、基本的には筆記用具・メモ帳・飲み物などを持ち込んでも問題ありません。特にメモ帳は、自分で候補者の名前を確認するためのものとして使う場合は持ち込みが認められています。ただし、他人に見せたり、不正な使い方をすると注意される可能性もあります。
筆記用具についての注意点
筆記用具は、自分で持参したものを使うこともできますが、投票所には公式に用意された鉛筆が置かれており、これを使うことがすすめられています。ボールペンや水性ペンは、インクがにじんでしまい、文字が読みにくくなったり、無効票と判断されるリスクがあるため、あまりおすすめされていません。持ち込む場合は、油性ペンを選ぶ方が安全ですが、そもそも筆記用具の持ち込みを推奨していない自治体もあります。
最近では「鉛筆だと書き換えられるのでは?」という心配がSNSなどで広がっていますが、これは誤った情報です。日本では選挙管理のルールがしっかりしていて、投票用紙の内容を第三者が書き換えるようなことは、ほぼ起こり得ません。票の保管や集計も厳格に管理されており、不正が起きにくい仕組みが整っています。
家族と一緒に投票できる?
投票所には、家族や介助者、補助犬を同伴することができます。とくに注目すべき点は、以前は幼児だけに限られていた子どもの同伴が、現在では18歳未満であれば認められているという点です。子どもにとっては、親と一緒に投票所に行くことが貴重な体験になり、将来の投票意識にもつながります。
また、身体が不自由な人など、介助が必要な場合には、投票管理者の許可を得れば介助者が一緒に中まで入って手助けすることも可能です。こうしたルールは、誰もが平等に投票できる環境を守るために用意されています。
このように、投票所ではある程度自由に持ち物が認められており、不安なく投票を行うための工夫がなされています。ルールを正しく理解して、安心して投票に行くことが大切です。
SNSで気をつけたいこと
選挙期間中になると、SNSには多くの情報が飛び交い、どれを信じてよいのか迷ってしまうことがあります。番組には「フェイク情報を見分けるにはどうしたらいいの?」という視聴者からの疑問が寄せられました。それに対して、番組では発信している人がどんな意図で投稿しているのかを考えること、自分自身で情報を確かめることの大切さが強調されていました。
SNSは便利な反面、間違った情報や意図的に操作された内容が広まりやすい場所でもあります。そうした環境の中で、どの情報が信頼できるのか、どれが怪しいのかを見極める力が求められます。
「た・し・か・め・て」で情報を見直す
番組では、選挙情報と向き合うときのポイントとして「た・し・か・め・て」という覚えやすい言葉が紹介されました。この言葉は、SNSで見た情報をそのまま信じるのではなく、一度立ち止まって確認するためのヒントです。
| 文字 | 意味 |
|---|---|
| た | たどってみよう(情報の発信元を確認) |
| し | 調べて比べて(他のニュースも見る) |
| か | 感情的な言葉に注意して深呼吸 |
| め | 目を引く動画はその場で即決しない |
| て | 手がかり(根拠や出典)を確認 |
これらを意識することで、印象だけで判断するのを防ぎ、冷静に事実を見極める手助けになります。例えば、ある候補者についての極端に良いまたは悪い情報を見たときは、その情報の出どころがどこなのか、似た内容が他のニュースでも報じられているかを確認するのが基本です。
さらに、選挙の話題に感情が動かされてしまうと判断が偏ることがあります。そんなときには一度深呼吸をして、目の前の情報が信頼できるものかどうかを「て=手がかり」でしっかり見直してから、自分の意見をまとめることが大切です。
このように、SNSでは情報を受け取る側の姿勢がとても重要であると、番組では繰り返し伝えられていました。自分の一票を考えるためにも、落ち着いて情報を見つめ直すことが大切です。
参議院の役割と仕組み
参議院は国会議事堂の本会議場のうち、正面から見て右側に位置しています。定員は合計248人で、このうち選挙区選出148人、比例代表選出100人という内訳です。任期は6年と長く設定されており、3年ごとに半数が改選される仕組みなので、一度に全員が入れ替わることはありません。立候補できるのは30歳以上で、衆議院のような解散がないため、選ばれた議員は腰を据えて中長期の課題に向き合うことが期待されています。
二つの投票で意思を示す
参議院選挙では有権者が**「選挙区」と「比例代表」の2票**を投じます。選挙区の投票では、自分が住んでいる地域の候補者名を書いて一人を選びます。一方の比例代表では、候補者名か政党名のどちらかを書いて投票します。比例票は全国で集計され、得票数に応じて政党ごとに議席が配分されるため、個人を選ぶだけでなく政党の考え方を支持するという意思も示せます。選挙区と比例代表を合わせることで、地域の声と全国的な政策への評価の両方を国会に届ける仕組みになっています。
白票の意味や当確の仕組みにも注目
番組には、「白票を入れることに意味はあるのか?」という視聴者からの問いが寄せられました。選挙で投票用紙に何も書かずに投票する白票は、形式上は無効票として扱われますが、それでも「支持する候補者がいない」という意思を示す手段として見ることができます。実際に過去の地方選挙では、白票を含む無効票が20万票を超えた例もあり、一定の存在感を持つ行動とされています。
このように白票は、投票に行かないという選択ではなく、「選択肢がない」という立場からの積極的な意思表示とも受け取られることがあります。誰にも投票したくないと思ったときに、あえて白票を投じるという行動が、その地域の政治に対する不満や課題意識を反映する場合もあるのです。
「当確」はどうしてあんなに早く出るの?
また、「まだ開票が少ししか進んでいないのに、どうして当確が出るの?」という疑問も取り上げられました。この「当確」は、NHKなどが独自の基準と情報に基づいて発表するもので、選挙管理委員会が公式に出す結果とは異なります。
NHKでは、投票日当日に実施される出口調査や、事前の情勢取材のデータを総合的に分析して、当確の判断をしています。また、開票が始まった後は、記者が現場で集計状況を取材し、票の動きを把握します。こうした情報をもとに、どの候補が優勢かを判断し、確度が高いと判断された時点で「当選確実(当確)」を出しているのです。
ただし、票が拮抗している接戦の場合には、選挙管理委員会の公式発表をある程度待ってから判断することもあるとのこと。つまり、当確が早く出るのは、裏でしっかりとした調査と分析がされている結果であり、感覚的な予想ではないということです。
話題のコーナー「鈴木の代行!趣味ハジメ」も放送
今回は、茶道の体験にチャレンジ。都内には初心者向けの無料体験ができる教室も多く、服装は普段着でも大丈夫。ただし、白い靴下の持参とアクセサリー類の着脱など、最低限のマナーは必要です。
体験では、もてなされる側の作法を中心に学び、お茶とお菓子のいただき方も体験。お菓子を食べるときは懐紙を使い、茶を飲む前には「お点前頂戴いたします」とあいさつ。所作が身につくことで、日常の振る舞いも変わるというメリットが紹介されていました。
月謝は月6000~1万円ほどで、必要な道具はネットや店頭で揃えることができ、動画での復習も可能です。
おわりに
選挙が近づくと「どうやって決めればいいの?」「何を信じていいの?」と悩む人も多いですが、今回の放送では、手軽に始められる情報収集の方法や、選挙との関わり方が紹介されていて、とても参考になる内容でした。政治のことは難しく考えがちですが、自分の暮らしとつながっている大切なテーマ。番組で紹介された方法を活用しながら、自分なりの視点で選挙と向き合っていけると良さそうです。
次回の【あさイチ】朝ドラ出演中!倉悠貴が“冷やし麺”料理に挑戦!
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


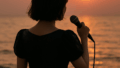
コメント