アイデアで勝負!ローカル水族館の魅力を徹底紹介
水族館といえば大きな水槽やイルカショーを思い浮かべる人が多いですが、近年は地域に根ざしたローカル水族館が個性的な展示や工夫で注目を集めています。今回のNHK「午後LIVEニュースーン」では、三重県伊勢市の伊勢シーパラダイスと愛知県蒲郡市の竹島水族館を中心に、ユニークな取り組みを紹介していました。この記事ではその内容をすべてまとめ、読者の疑問に答えていきます。
ゼロ距離で生き物とふれあえる伊勢シーパラダイス(三重県伊勢市)
まず紹介されたのは、三重県伊勢市にある伊勢シーパラダイスです。ここは「ゼロ距離水族館」というユニークなコンセプトを掲げており、来館者が生き物と本当に近い距離でふれあえるのが最大の魅力です。例えば、普段は遠くからしか見られないゴマフアザラシやセイウチといった大きな動物に、すぐそばで触れることができます。さらに、展示されている水槽では、タツノオトシゴやトビハゼなどの小さな生き物にも直接手を伸ばして触れることが可能です。この「ゼロ距離体験」は、子どもから大人までわくわくする特別な体験になっています。
一見すると「お客さんが楽しめるための工夫」と思われがちですが、実際には飼育スタッフが何よりも大切にしているのは動物たちの健康と快適さです。ゼロ距離展示は単なるサービスではなく、もともとセイウチの運動不足を解消する工夫として始まったものです。大きな体のセイウチが柵の外に出てのびのびと動き回る姿を見てもらうことで、動物にとっても良い刺激になり、結果的に来館者が間近で触れ合えるというスタイルが生まれました。
また、ふれあいの時間は動物のストレスを減らすためにきちんと制限されています。無理に全ての個体を参加させるのではなく、人に慣れていて接触が得意な動物だけが触れ合い体験に登場します。これにより、動物が安心して過ごせる環境を守りながら、来館者に特別な体験を提供できるのです。つまり、この展示は単なる「楽しい仕掛け」ではなく、人と動物の両方にやさしいスタイルとして評価されています。
【伊勢シーパラダイスの特徴まとめ】
- ゴマフアザラシやセイウチと本当にゼロ距離でふれ合える
- タツノオトシゴやトビハゼなど、小さな生き物にも直接触れられる
- 動物の健康と安全を第一に考えた運営方針
- ストレスを避けるため、触れ合いの時間は限定的で無理のない範囲
このように伊勢シーパラダイスは、動物を大切にしながらお客さんに忘れられない体験を提供しており、「ゼロ距離」という言葉にふさわしい水族館となっています。
深海生物で人気を回復した竹島水族館(愛知県蒲郡市)
続いて紹介されたのは、愛知県蒲郡市にある竹島水族館です。かつては来館者数の減少に悩み、存続の危機に立たされた時期もありました。しかし、思い切って深海生物に特化した展示に力を入れたことで、大きな人気を取り戻すことに成功しました。
館内にはなんと140種類以上の深海生物が展示されており、その数は日本一の規模を誇ります。近隣にある形原漁港や西浦漁港は底引き網漁が盛んで、市場には出回らない深海魚が多く水揚げされます。これらを安価に譲ってもらうことで、他の水族館ではなかなか見られない珍しい生き物を次々と集めることができています。まさに地域とのつながりを活かした水族館といえるでしょう。
特に2010年から始まった「深海生物に触れるプール」は、竹島水族館を代表する大人気の体験型展示です。子どもから大人まで、実際に深海生物に触れることができる貴重な機会として話題を集め、来館者の心をつかみました。その効果は数字にも表れており、10年前には年間約24万人だった来館者数が、現在ではおよそ倍の48万人にまで増加しています。
さらに忘れてはならないのが、スタッフの工夫による手書きの解説パネルです。生き物の特徴や裏話をユーモアを交えて紹介しており、ただ見るだけでなく「学ぶ楽しさ」や「親しみやすさ」を感じられる仕掛けになっています。この温かみのあるパネルは、深海生物の不思議さをより身近に感じさせ、訪れる人々を惹きつけています。
【竹島水族館の特徴まとめ】
- 深海生物140種類以上を展示(日本一の規模)
- 形原漁港・西浦漁港から市場に出ない深海魚を仕入れ可能
- 2010年開始の「触れる深海生物プール」が大人気
- スタッフ手作りの解説パネルで温かく楽しい学び体験
- 年間来館者数は10年前の約24万人から約48万人へ倍増
このように竹島水族館は、地域の特性を活かした深海生物展示と、スタッフの熱意が伝わる工夫で再び注目を集める存在となりました。大規模ではなくても、強い個性を打ち出すことで多くの人に愛される水族館へと生まれ変わったのです。
他にもある!特化型のローカル水族館
番組では、竹島水族館のように独自の工夫で人気を集める施設だけでなく、全国各地にある「何かに特化した水族館」も紹介されました。その一つが、山形県鶴岡市にある加茂水族館です。ここはクラゲ展示の充実度で世界的にも知られており、常時50種類以上のクラゲを公開。幻想的なクラゲドームは国内外から観光客を集める大きな魅力になっています。
さらに、和歌山県すさみ町にあるエビとカニの水族館は、甲殻類に特化した全国でも珍しい水族館です。世界最大級のカニであるタカアシガニをはじめ、さまざまな種類の甲殻類を間近で観察することができ、研究面からも注目されています。
長崎県長崎市にある長崎ペンギン水族館も外せません。ここではペンギンの飼育種類数が世界一とされており、世界中のペンギンを一度に見られる貴重なスポットになっています。実際に海で泳ぐペンギンを観察できる「自然体験場」など、他にはない展示方法が工夫されており、訪れる人に特別な体験を提供しています。
このように、「特化型水族館」は大規模な施設でなくても、強い個性や専門性を打ち出すことで全国から人々を呼び寄せています。地域ならではの特色を活かすことで、観光の目玉にもなり、地元経済を支える存在にもなっているのです。
まとめ:ローカル水族館の未来
今回紹介された伊勢シーパラダイスと竹島水族館は、どちらもアイデアと動物への愛情で来館者を魅了しています。大規模な施設に比べると規模は小さいですが、むしろその距離感が「温かみ」や「親しみやすさ」につながっています。
旅行やおでかけの際、近くのローカル水族館を訪れてみると、大型水族館では味わえない特別な体験ができるかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


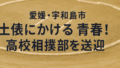
コメント