江戸から旅人ジューデンが現代へ!海野宿で見つけた“時をこえる町並み”の秘密
旅をしていて「この町、なぜこんなに昔の風景が残っているんだろう」と感じたことはありませんか?古い家並みや石畳、木の香りが漂う通りを歩くと、まるで時間がゆっくり流れているように感じます。そんな“時の継承”をテーマにした番組『ジューデンのまちなみタイムスリップ 時をこえ〜長野・海野宿』が、2025年10月16日(木)に放送されます。
番組では、江戸時代からやって来た俳人ジューデン(濱尾ノリタカ)が、長野県東御市の海野宿(うんのじゅく)を訪ねます。ここはかつて北国街道の宿場町として栄え、旅人や商人が行き交った町。江戸の雰囲気を今に残すこの町で、ジューデンは人々の暮らしと文化の“つながり”を目にします。
NHK【あさイチ】奈良で味わう幻の和菓子と大和まな料理、1300年前の文様雑貨まで“大人かわいい”をめぐる旅|2025年10月16日
“重伝建地区”とは?町そのものが文化財

海野宿(うんのじゅく)は、国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)に指定されています。これは、江戸から明治にかけての町並みや建築物がまとまって残り、文化的価値が高い地域として国が正式に認めているものです。日本全国でこの重伝建地区は129か所あり、その一つひとつが「生きた博物館」とも呼ばれています。古い建物を単に残すのではなく、今もそこに人々が暮らし、歴史とともに生活が続いている点が特徴です。
長野県東御市にある海野宿は、その中でも特に保存状態のよい宿場町として知られています。江戸時代には北国街道の宿場町として栄え、多くの旅人が行き交いました。通りには旅籠(はたご)や商家が軒を連ね、行商人や旅人を迎え入れていた面影が今も残ります。建物の特徴は、木格子のある落ち着いた外観、白壁、そして瓦屋根が整然と並ぶ美しい町並み。通りを歩けば、まるで江戸時代の絵巻物の中に入り込んだような感覚になります。
通りの中央には、今も澄んだ水路が静かに流れています。この水路は、かつて旅人の喉を潤すための生活用水として使われていましたが、もう一つの役割がありました。それは火事の延焼を防ぐための防火用水です。木造の建物が密集していた時代、町を守る知恵として欠かせない存在でした。現在もこの水路はきれいに整備され、地域の象徴として大切に守られています。
海野宿の家並みには、屋根の上に張り出したうだつと呼ばれる壁がいくつも見られます。もともとは火事の延焼を防ぐための防火壁でしたが、やがて裕福な商人たちが競うように装飾を凝らすようになり、「うだつが上がる」という言葉の語源にもなりました。通りの両側に立ち並ぶうだつは、海野宿の象徴ともいえる存在です。
この町並みを今日まで保ち続けているのは、地域の人々の不断の努力です。住民たちは古い家屋を修復しながら暮らし、外観を損なわずに現代の生活に合わせる工夫をしています。行政と住民が協力して「保存と生活の両立」を進めており、観光客に対しても静けさと温かさを感じてもらえる町づくりを続けています。
季節ごとに違った表情を見せるのも海野宿の魅力です。春には桜が通りを彩り、夏には清らかな水路の音が心地よく響きます。秋は紅葉が瓦屋根を包み、冬は雪化粧の家並みが幻想的な風景をつくり出します。まさに“日本の四季”と“江戸の時間”が共に息づく場所として、訪れる人々を静かに迎えてくれる町です。
海野宿を象徴する“うだつ”の意味

海野宿(うんのじゅく)の町並みを歩くと、まず目を引くのが屋根の上に少し張り出した「うだつ」です。うだつとは、もともと火事の延焼を防ぐための防火壁として設けられた建築の一部で、隣家との境に設けられる土壁のことを指します。木造家屋が密集していた江戸時代、火事は町にとって最大の脅威でした。そのため、うだつは町を守るための実用的な構造として生まれたのです。
しかし時代が進むにつれて、このうだつは商人たちの「誇りの象徴」へと変化していきました。裕福な商家の主人たちは、より立派で装飾性の高いうだつを競い合うように建て、家の格式や繁栄を示すものとしました。その結果、「うだつが上がる」という言葉が生まれ、社会的に成功することや、地位が向上することの比喩として今も使われています。
長野県東御市の海野宿には、このうだつが美しく連なる家並みが今も残っています。通りを歩けば、白壁と木格子の家々が整然と並び、その屋根の上に控えめながらも存在感のあるうだつが続いています。夕暮れ時には瓦屋根の陰影が浮かび上がり、町全体が柔らかな光に包まれる光景はまるで絵画のようです。こうした風景は、写真家や観光客にとって絶好の撮影スポットとなっており、四季折々の表情を求めて全国から人々が訪れています。
番組『ジューデンのまちなみタイムスリップ』では、これらのうだつを修復し続ける地元の大工職人や、古民家を守りながら暮らす住民の姿が紹介される予定です。長年にわたって伝統的な工法を受け継ぎ、木と土、漆喰を使って細部まで丁寧に仕上げる職人たちの手仕事。その姿からは、「文化財をただ残すのではなく、生かして次の世代につなぐ」という強い思いが感じられます。
海野宿では、町並み全体が一つの作品のように大切に扱われています。建物の修復や補修は個人任せではなく、住民と行政が協力しながら保存活動を進めており、うだつを含む家並みの修景もその一環です。古い建物をカフェや宿泊施設に活用する取り組みも進み、観光客が町の文化を体験できる形へと少しずつ姿を変えています。
瓦の重み、木の香り、漆喰の白さ。どれもがこの町の記憶を語り、静かに息づいています。海野宿のうだつは、単なる建築物ではなく、時代を超えて人々の心と暮らしをつなぐ“生きた文化”なのです。
江戸から現代へ 俳人ジューデンのまなざし
物語の中心にいるのは、江戸時代の俳人ジューデン。彼は小林一茶の弟子として、師とともに庶民の暮らしや自然の移ろいを句に詠んでいた人物です。そんな彼が、ある日突然、令和の時代へとタイムスリップします。舞台は長野県東御市・海野宿。江戸から令和へ──まるで夢のような時の旅が始まります。
ジューデンが現代の町を歩くと、まず目に飛び込むのは、江戸にはなかった電柱や車の往来。頭上を張り巡らせる電線、ガラス越しに光るコンビニの看板、カメラを構える観光客たち。そのどれもが、彼の知る“日本”とは違う世界の光景です。けれど、よく見れば、町の奥には江戸の頃から続く瓦屋根や格子戸が静かに残り、人々の暮らしの中に“変わらない温もり”が息づいていることに気づきます。
町を歩く中で、ジューデンは地元の職人や住民たちに出会います。彼らは古い建物を守りながら、今の時代に合った形で使い続けています。スマートフォンで観光案内をする若者、SNSで町の魅力を発信するカフェの店主。彼らの姿に、ジューデンは戸惑いながらも次第に興味を持ち、江戸の言葉で現代の日本をどう表現できるかを探し始めます。
番組では、そんなジューデンが見た「令和の日本の風景」を、俳句という形で表す瞬間が描かれます。スマートフォンの画面越しに笑う若者や、写真を撮る観光客、うだつの上を飛ぶ鳥──それらの一つひとつに、彼は江戸時代と変わらない“人の心”を見いだします。過去と現在が交わるその瞬間、ジューデンは思わず一句を詠みます。
言葉は短くても、そこに込められた思いは深く、見る者の胸に静かに響きます。ジューデンが感じた「時を超えて生きる日本のこころ」──それは、過去を懐かしむのではなく、“今を生きる”ことの尊さを映す鏡のようです。
物語の最後、彼が見つめる海野宿の夕暮れは、まるで江戸と令和が溶け合うような柔らかな光に包まれています。長い時間を超えて、変わらない風景と人の思い。ジューデンが詠むその一句には、“時代を超えて生き続ける日本人の心”が込められています。
暮らしと文化が共存する“生きた町”
海野宿(うんのじゅく)の魅力の本質は、単なる観光地ではなく「今も人が暮らす町」であることです。多くの古い町並みが観光用に保存されている中で、海野宿は“生活と文化が共存する場所”として特別な存在です。
古民家の軒先には四季の花が飾られ、玄関には子どもたちのランドセルが掛けられています。朝になると通りには登校する子どもたちの声が響き、夕方には障子越しにあたたかな灯りがともります。瓦屋根の上を風が抜け、川のせせらぎが静かに響く。そんな日常がこの町の景観の一部になっています。
住民たちは、古い建物をただ保存するだけでなく、「暮らしながら守る」という形で文化を受け継いでいます。たとえば、建物の修繕では伝統的な木組みや漆喰塗りの技法を用い、外観を損なわずに内部を現代的に整える工夫をしています。冬の雪対策や防火設備なども、景観に配慮しながら慎重に設置されています。こうした努力が、江戸から続く町並みを今に伝える力になっています。
さらに、海野宿では年間を通して地域の祭りや行事が行われています。春の「宿場まつり」では住民総出で通りを清め、家々にのれんがかかります。夏には町の中央を流れる水路を利用した灯籠流し、秋にはうだつの家並みをライトアップする夜祭が開かれます。どの行事も、世代を超えて住民が参加し、“自分たちの町を誇りに思う心”を次の世代へとつないでいます。
番組の中で、江戸から来た俳人ジューデンがこの町を歩き、「この町は生きておる」とつぶやいたのは、まさにその理由です。ここでは建物も人も、過去の遺産としてではなく、現在進行形の“暮らし”として息づいているのです。江戸の香りを残しながら、令和の生活が溶け込む海野宿。その姿は、古いものを守りながらも未来へ進む、日本の町の理想形ともいえます。
未来への橋渡し 海野宿が伝えるもの
文化財というと、静かに佇む古い建物や展示物を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、本当の文化財は“静止している”のではなく、そこに関わる人々の手によって“動き続けている”存在です。海野宿の町並みもその一つ。見た目は変わらないように見えても、毎日の手入れや季節ごとの行事、住民の暮らしによって常に息づいています。
長野県東御市・海野宿(うんのじゅく)では、古い建物の修復だけでなく、次の時代へ文化を引き継ぐための工夫が随所に見られます。古民家の外観はそのままに、内部を現代的にリノベーションしてカフェや宿泊施設として再生させる取り組みが進んでいます。古い梁や土壁を活かしながら、照明や家具にモダンなデザインを取り入れることで、昔と今が自然に溶け合う空間が生まれています。
町の中には、かつての旅籠(はたご)を改装した古民家カフェや、職人が手作りする工芸雑貨店もあり、観光客だけでなく地元の若者たちの憩いの場にもなっています。こうした施設では、地元産の食材や手仕事を活かしたメニュー・商品を提供し、訪れる人に「この町の文化」を体験してもらう工夫がされています。若い世代がSNSで発信することで、海野宿の魅力は全国に広がり、地域の活性化にもつながっています。
また、海野宿を舞台にした写真展やワークショップなども定期的に開かれています。古い家屋の土間をギャラリーに活用したり、旅人が自由に句を詠める俳句ノートを設置したりと、訪れる人が町の文化に関わる仕組みが増えています。地元の中学生や高校生がボランティアとしてイベントに参加することもあり、文化財の保存が「学び」として根づき始めています。
こうして海野宿は、“守る町”から“育てる町”へと変化しています。建物はそのままに、人の関わりが未来を動かしているのです。文化を受け継ぐということは、単に過去を守ることではなく、今の時代に合う形で息を吹き込むこと。番組『ジューデンのまちなみタイムスリップ』では、そんな「変わりながら守る町の姿」に光を当て、人々が文化財に込める想いを丁寧に描き出していきます。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・海野宿は“江戸の風景”が今も残る重要伝統的建造物群保存地区
・俳人ジューデン(濱尾ノリタカ)が時をこえて現代の町並みを見つめる
・町並み保存は「建物を守ること」ではなく「暮らしと記憶を未来へつなぐこと」
町の記憶を守るのは、そこに生きる人々の心です。放送を通じて、海野宿の静かな時間の流れ、そして日本の“まちの原点”を感じてみてください。
ソース:
NHK公式番組表『ジューデンのまちなみタイムスリップ 時をこえ〜長野・海野宿』(https://www.nhk.jp/)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

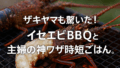

コメント