怖い昔話にはちゃんと理由があった!記憶に残る“怖さ”の正体とは
今回取り上げるのは『チコちゃんに叱られる!』で放送された「なんで童話や昔話は怖い話が多いの?」という疑問です。私たちが子どもの頃に読んだあのドキドキする場面には、ただの演出ではなく、人間が生き延びていくための“記憶の仕組み”がしっかり組み込まれているという深い背景があります。
この記事では、放送内容のすべてを整理しながら、昔話がなぜ怖いのかを心理・進化・文化の側面からまとめます。『舌切り雀』や『赤ずきん』に込められたメッセージ、街の人が語った“忘れられない怖い体験”、そしてあばれる君のリアルな思い出まで紹介します。
【チコちゃんに叱られる!】“外郎売”が生んだ早口ことば!のど薬が生んだ江戸の声文化と市川團十郎の物語|2025年10月10日
怖い昔話が生まれた理由は『子孫繁栄』と深い関係があった
冒頭、チコちゃんが問いかけたのは「なんで童話や昔話は怖い話が多いの?」。
井上芳雄さんは「教訓のため」と答えましたが、チコちゃんに叱られてしまいます。正解は『怖くないと子孫繁栄に役立たないから』。
この謎を解説したのが鵜野祐介さん。ここで示されたのが、物語と人間の“記憶のしくみ”の関係でした。
昔話は、教訓を伝えるためにつくられたものですが、優しく穏やかな話だけでは記憶に残りにくいという特徴があります。
そこで“怖い”“驚いた”という感情が重要な役割を果たします。強い刺激は脳に深く刻まれ、長いあいだ忘れにくくなります。
この仕組みは、子どもたちが危険を避け、生き延びて子孫を残すために必要な能力です。
まさに“怖さは生きる力”という考え方で、番組の答えである『子孫繁栄に役立つ』につながっていきます。
鵜野さんは、物語の具体例としていくつかの昔話を紹介しました。
・『舌切り雀』……思いやりと、欲張らない心
・『赤ずきん』……警戒心と慎重さ
・『三びきの子ぶた』……選択の結果と責任
・『みにくいアヒルの子』……自己肯定と成長
・『かちかち山』……悪意への報い
・『うさぎとかめ』……努力と油断
どれも、子どもにとって学んでほしい“生き方のヒント”が含まれています。
そして、そのメッセージを強く覚えさせるために「怖さ」という要素が自然と使われてきたわけです。
さらに街頭インタビューでは、昔話の記憶がいかに強く残るかを示す例が登場しました。
1週間前の夕食は思い出せないのに、幼い頃に感じた“怖い思い出”だけはスラスラ語れる人が多く、怖さが記憶を強固にしていることがよく分かりました。
あばれる君の体験が“怖さの記憶”を象徴していた
番組で印象的だったのが、あばれる君の実体験です。
彼の父はとても厳しく、ミニ四駆の大会に来てくれた際、マシンが動かなくなって困った彼に対して「いじりすぎなんだよ」と怒ったそうです。
その時の怒られた記憶が、いまでも忘れられないとのこと。
この例がまさに「強い感情は長期記憶になる」仕組みを示しており、怖さは人に強く刻まれるという番組の説明とぴったり合っていました。
人間が“怖さの記憶”を大切に保つのは、生き延びるために危険を避ける本能が関わっています。
昔話が長く語り継がれてきた背景には、こうした記憶の性質が大きく影響していたのです。
世界の名作にも共通する“恐怖の教訓構造”
放送では、日本の昔話だけでなく、世界各地の物語にも「怖さを通して学ぶ」構造が共通していることが紹介されました。
『三びきの子ぶた』では、オオカミの存在が強い恐怖として描かれています。
『赤ずきん』でも、狼という危険の象徴が登場し、警戒心を身につけるための物語として伝わっています。
『みにくいアヒルの子』にも、仲間外れにされる恐怖があり、感情の揺れが強い記憶として残る仕組みが使われています。
番組では、物語に関する展示を行う東京おもちゃ美術館や、『世界名作シリーズ』を刊行する永岡書店も紹介され、昔話と文化の結びつきが丁寧に語られました。
怖さは“忘れにくい記憶”をつくり、文化として残り続ける
物語は、感情を動かすほど記憶に残るという人間の性質を巧みに活かしています。
特に「恐怖」は強烈な体験として刻まれるため、親から子へ、子からさらに次の世代へと伝わる物語には欠かせない要素になりました。
怖い昔話は、単なる演出や娯楽のためではなく、
「危険を避けるための知識を、忘れないように伝える仕組み」
として機能し、人類の生存戦略の一部になっていたのです。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・童話の“怖さ”は、人間が危険を忘れずに生き延びるための『記憶の仕組み』が関係していた
・あばれる君のエピソードを含め、怖い体験ほど脳に深く刻まれやすい
・日本も世界も、昔話の多くには“恐怖を利用した教訓”があり、子どもに大切な知恵を伝えるための工夫が込められていた
物語に登場する“怖い場面”は、実は生きるための知恵を伝える力強い装置でした。
その背景を知ると、昔話を読み返したときに新しい発見がたくさん見えてきます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


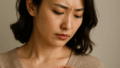
コメント