緊急派遣5千人 日本メーカーの総力戦〜タイ大洪水との闘い
2011年に発生したタイの大洪水は、日本の製造業にも大きな影響を与えました。今回の『新プロジェクトX』では、被災地に生産設備を置いていた日系企業の奮闘と、5千人のタイ人従業員を緊急派遣して日本で再生産に挑んだ前代未聞のプロジェクトが描かれます。国境を越えた人々の連携と信頼の物語です。
工業団地を飲み込んだ100年に一度の大洪水

2011年、タイのチャオプラヤ川流域にかつてない規模の大雨が降り注ぎました。3つの台風が立て続けに襲来し、ダムの放水も追いつかないほどの豪雨が続いた結果、100年に一度といわれる大洪水が発生。被災者数はおよそ230万人にのぼりました。中でも、タイ中部アユタヤ県に位置するロジャナ工業団地は、広大な敷地を持つ大規模な産業エリアであり、日系企業を中心に150以上の工場が立地する重要拠点でした。
・ニコンは主力であるカメラの9割をこの工場で生産しており、浸水によって生産ラインは壊滅的な被害を受けました
・沖電気工業の工場は、タイでの再始動を果たした直後のラピスセミコンダクタに移行しており、最新の設備が導入されたばかりでした
・パイオニアも年800万台を出荷する重要拠点を持っており、家電製品の供給が完全に止まりました
水はわずか1日で工業団地を覆い尽くし、建物の1階部分が完全に水没。生産機器はもちろん、出荷待ちの製品、重要なデータを記録した装置までもが泥水の中に埋もれてしまいました。電力も止まり、通信も遮断された中、工場で働いていた現地のタイ人従業員たちは、次々に家を失いながらも職場に駆けつけ、事態の収拾に奔走しました。
・ロジャナ工業団地には、ニコン、沖電気、パイオニアをはじめ、電子部品、家電、医療機器、自動車部品などの製造工場が密集
・従業員数はおよそ5万人以上にのぼり、そのうち多くが地元のタイ人スタッフで構成されていました
・水害は週単位で続き、工場の再稼働は見通しが立たず、生産と生活の両面で危機が訪れました
そうした中で動いたのが、日系企業の日本人リーダーたちでした。現地スタッフを“家族”と捉え、“第2の家”を失わせてはならないという思いで立ち上がったのです。泥水が引くのを待つのではなく、「今できる最善の方法を探して行動する」ことを選びました。
・ニコンの現地責任者である村石信之氏は、被害状況を確認しながらも次なる生産手段の確保に動き出しました
・ラピスセミコンダクタの山田隆基氏は、かつて現地スタッフと築いた関係を信じ、社内外に連携を呼びかける行動を始めました
・パイオニアの現地トップ青柳篤氏もまた、自身が東日本大震災を経験した記憶を重ねながら、即座に復旧策を模索しました
このように、単なる災害対応ではなく、企業と地域社会が一体となった「復旧への総力戦」がここから始まったのです。被害を受けた工場は数百にのぼり、設備の損傷だけでなく、従業員の暮らし、サプライチェーンの断絶など、複数の課題が一気に押し寄せていました。それでも、指揮を執るリーダーたちはあきらめず、状況を乗り越えるためのあらゆる手段を考え続けました。その最初の一歩が、この未曾有の洪水被害を受けたロジャナ工業団地で踏み出されたのです。
「ぶどうの理論」で企業の壁を超えた連携

ロジャナ工業団地が水没した直後、現地の混乱は極限まで高まりました。工場の設備だけでなく、従業員の暮らしも一気に奪われる中、企業単体では対応しきれない局面が広がっていきます。そんな中で動いたのが、沖電気時代から現地で信頼を集めていた山田隆基でした。
彼が実行したのは、「ぶどうの理論」と呼ばれる考え方に基づいた行動です。これは、「ぶどうの棚から取った実は誰かに渡す。自分の両手はいつでも空けておき、有事の時に率先して前に出ろ」という、リーダーとしての心構えを表した言葉でした。
・山田は、ニコンの村石信之、パイオニアの青柳篤と即座に連携
・自社の復旧だけではなく、ロジャナ工業団地全体の問題として対応しようと決断
・数多くの企業が混乱する中で、日系企業の代表としての立場を自ら引き受ける
3人は、水に覆われた工業団地から南へ80km、首都バンコクを目指して行動を開始しました。タイ政府に対して直接支援を求めるためです。その道のりは困難でしたが、目的は明確でした。「現地の従業員の暮らしを守ること」。それは生産再開よりも優先すべき命題でした。
向かったのは、日本の対外支援機関であるジェトロ(日本貿易振興機構)。ここで対応にあたったのが、助川成也です。山田たちの訴えを聞いた助川は、即座に支援の意思を示しました。
・最優先事項は、仕事を失った従業員たちの給与をどう補償するか
・水没により住まいを失った従業員たちも多く、生活の安定が再建の第一歩と考えられていました
・助川は、タイ政府と交渉して補助金の提供を引き出すことに成功
・また、被災した150社以上の日系企業の現状把握と支援の優先順位整理も同時に進行
こうして、企業の枠を超えた行動が始まります。従業員の未来を第一に考えるという共通の信念が、ニコン・ラピス・パイオニアという異なる業種の企業のリーダーをひとつに結びつけたのです。リーダーたちの判断と、国際機関の支援が重なったことで、後の「タイ人5千人派遣」につながる一大プロジェクトの土台が築かれました。
この時点で、まだ工場は泥水に浸かり、生産設備も使えない状態でしたが、すでに再建への流れが静かに動き出していたのです。リーダーたちの連携と現地従業員への強い信頼が、困難の中にある希望の灯をともした瞬間でした。
泥水の中で始まった決死の生産設備回収

水没した工場で、日本への生産移管という非常手段を実行するには、現地に残された精密な生産設備を回収することが必要不可欠でした。金型や基板、組み立て装置など、どれも再調達が難しく、タイの工場にしかない機器も多く含まれていました。泥水に浸かった機材の回収は、命の危険と隣り合わせの作業でした。
ラピスセミコンダクタの現場で指揮をとったのは工場長の大岡文彦。彼は水位が下がらないままの工場に部下とともに飛び込み、懸命な捜索を開始します。視界ゼロの泥水の中では、重機も使えず、手探りで設備を探すしかありませんでした。
・金型や基板は、ひとつ数十キロから数百キロに及ぶ重量物
・泥と油が混じった水に沈んだ設備は、どこにあるのか目視できず、感覚だけが頼り
・それでもタイ人従業員たちは笑顔で作業に加わり、冗談を言い合いながら励まし合っていた
タイには「笑って闘う」という文化があります。どんなにつらくても笑顔を忘れず、前向きに困難を乗り越える。その精神が、極限の状況にあっても、彼らを支えていたのです。
一方、ニコンの村石信之のもとには思わぬ援軍が現れました。パタヤでダイビングインストラクターを束ねるソンマイという男性とその仲間20人が、「水中作業なら任せてくれ」と駆けつけたのです。
・ダイバーたちは毎日泥水に潜り、合計100個以上の金型(1個200キロ超)をわずか2週間で回収
・作業中にはなんとワニに遭遇する場面もありましたが、誰一人として怯むことはなかった
・回収を終えたあと、ソンマイたちは報酬を相場の3分の1しか受け取らず、「残りは被災者支援に使ってほしい」と申し出た
こうした協力があったことで、数億円規模の生産資産が無事日本に送られることになりました。タイ人の協力なしには到底成し得なかった決死の任務です。機材の確保は、日本での緊急ライン設置と再生産に直結しており、まさに再建の“命綱”となる作業でした。
機械を取り出しただけでは終わりません。水に浸かった装置は再調整や部品交換が必要で、精密な復旧作業が日本側で待っていました。しかし、回収に成功したことで、企業は次のステージへと進む足がかりを得たのです。
この決死の作業は、人と人との信頼、そして誠意によって成り立った奇跡のような現場でした。命がけで支え合った日と笑顔の記憶は、今も語り継がれるタイとの絆として残っています。
難関だった日本への派遣計画とその突破

水没した工場の復旧には長い時間がかかると判断された中で、生産の継続を日本国内で行うという決断が下されました。しかし、日本で同じ品質の製品をつくるには、熟練したタイ人従業員の技術が欠かせませんでした。そこで企業側は、タイ人スタッフを日本へ一時的に派遣して生産ラインを立ち上げるという計画を進めます。
しかしこの計画は、日本政府の大きな壁に直面します。当時の法務省は、外国人労働者の派遣について慎重な姿勢を崩さず、「不法滞在のリスクがある」として就労ビザの発給に難色を示しました。とくにタイのように一般的な出稼ぎ目的での渡航と誤解される懸念があり、前例のない規模の派遣は容易に認められませんでした。
・日系企業からの派遣申請に対して“50年かかっても通らないだろう”という厳しい反応
・助川成也が日本政府、特に外務省と法務省に対して再三の要請
・企業側も、タイ人スタッフの信頼性を示すため、企業単位での管理体制や帰国保証を徹底
この時、ラピスセミコンダクタの山田隆基は「彼らは家族だ。絶対に裏切らない」と、強い覚悟を持って明言しました。この言葉が交渉を動かす一つのきっかけとなります。助川は彼の言葉を信じ、官庁と何度も協議を重ねました。
・受け入れ先企業は住居・生活支援を全て用意
・タイ側でもスタッフに対し厳格な規律と帰国時期の確認を徹底
・“技能継続のための臨時派遣”という新たな解釈が導入され、突破口が開かれます
そして、ついに2011年10月末、第一陣として66人が宮崎県の半導体工場へ派遣されることが決定。リーダーを務めたのは、山田の会社で2期生として働いていたシリヌッチ。彼女は同僚をまとめ、日本での新しい任務に挑みました。
・全国の工場へ5,409人のタイ人スタッフが順次派遣
・派遣先は大手企業から中堅企業まで約100社に及び、家電・半導体・医療機器など多様な製品の生産を再開
・言葉や文化の壁を超えて、日本のスタッフと共に緊急ラインを立ち上げた
タイ人たちは、慣れない環境でもすぐに能力を発揮し、短期間で生産を安定化させます。そのおかげで、止まっていた「メードインジャパン」の製品供給が動き始めました。
この派遣計画の成功は、国籍や企業の枠を越えて結ばれた“信頼”が制度や常識を動かした実例として、多くの関係者に深い印象を残しました。山田や助川をはじめとする人々の信念と努力、そして現地のスタッフの誠実な姿勢があったからこそ、前代未聞のプロジェクトは実現したのです。
再建と別れ、そして希望へ

タイの大洪水から数か月。被災した企業の多くが、生産ラインや設備の修理・再構築に向けて動き始めました。ニコンでは、生産拠点の分散化や建物の高層化など、新たな洪水対策を施しながら復旧作業が進められました。現地スタッフも戻り、再び工場に灯りがともる日が訪れます。
一方、ラピスセミコンダクタの工場は平屋建てで、今後も洪水対策が困難であることから閉鎖の決断が下されます。この工場は、数多くの従業員が「第2の家」として働いてきた場所でした。長年共に汗を流してきた仲間たちに、その決定を伝えるのは容易なことではありません。
・山田隆基は、全社員を前に深く頭を下げ、閉鎖の理由と想いを丁寧に伝えました
・会場は一瞬静まり返ったものの、間もなく起こったのは温かい拍手でした
・社員たちは、山田の真摯な姿勢とこれまでの尽力を理解し、誰一人として彼を責めませんでした
この拍手は、単なる労いではなく、信頼と感謝の証でした。山田は、工場を閉じることになっても、最後まで「第2の家」の父親であり続けようと、社員全員の再就職先を一人ひとり手配しました。技術職から事務職まで、それぞれの経験や希望に応じて企業を探し、本人が納得するまで対応したといいます。
・派遣されていた5,409人のタイ人スタッフは、全員が無事に任務を終えて帰国
・彼らの誰ひとりとして行方をくらますことなく、日本政府との約束は完全に守られました
・帰国後、被災した工場に再び戻り、新たな体制での再建に参加したスタッフも多くいました
ニコンでは、村石信之のもとで新たな防災体制が構築されました。生産拠点を分散させ、浸水しにくい構造にするなどの改善策が実施され、同じような被害を繰り返さないための取り組みが続けられました。
・再建された工場では防水壁の設置や高床構造の導入などが施され、以前よりも安全性が向上
・従業員も再び現場に戻り、以前と変わらぬ活気を取り戻していきました
山田が送り出した従業員のうち、リーダーだったシリヌッチは紹介された企業で幹部となり、現在もタイ国内で重要な役職を担っています。さらに、1期生だったコンサックは、新たな工業団地で再出発した会社にいち早く戻り、再建の柱として働いています。
この一連の出来事は、ただの企業復旧の話ではありません。人と人との信頼、苦境を乗り越えるための行動、そして未来を切り開く力が集まって実現した「希望の物語」だったのです。別れがあっても、その先に新たなつながりと未来が待っていました。それは“再建”という言葉を超えた、“再生”の物語だったのです。
タイで今も続く絆
山田はその後も日本には戻らず、工場を失った元従業員と同じようにタイで再就職。紹介したアルミ缶メーカーでシリヌッチは幹部に、コンサックは新工場の初期メンバーとして活躍。彼らとの絆は今も変わらず、毎年の誕生日にはかつての部下たちが山田のもとに集まります。
この番組は、“仲間を信じて行動し、困難を乗り越えた人々の記録”です。自然災害と向き合ったときに、本当の「強さ」と「優しさ」が問われる。その答えが、ここにあります。
※この記事は、2025年4月18日放送予定の『新プロジェクトX』の事前情報に基づいて作成しています。放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

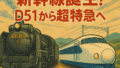
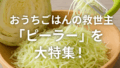
コメント