伊勢神宮への旅・第五夜
2025年5月10日に放送されたNHK「ブラタモリ」では、シリーズで続いてきた「伊勢神宮への旅」がついに最終回を迎えました。第五夜のテーマは、いよいよ伊勢神宮の到達とその周辺に広がる歴史的・文化的な背景です。タモリさんと佐藤茉那アナウンサーが歩んできた道のりは、ただの観光ルートではなく、江戸時代の庶民が命がけで目指した“憧れのお伊勢参り”の実体験を追体験する旅でした。
斎宮と祓川 神に仕える女性たちと神聖な儀式

旅の中盤、タモリさんたちが訪れたのは祓川(はらいがわ)と呼ばれる清流です。この川はかつて、特別な身分をもった女性が禊(みそぎ)を行った場所として知られており、その女性とは「斎王(さいおう)」と呼ばれる存在でした。斎王とは、天皇の代理として伊勢神宮に仕える未婚の皇族女性であり、飛鳥時代から南北朝時代にかけて約660年にわたり制度が続いたといわれています。
斎王が暮らしたのが「斎宮(さいぐう)」と呼ばれる施設で、現在の三重県明和町に位置しています。その広さは137ヘクタール以上もあり、そこには斎王を支える役人や技術者など約500人が常駐していたとされています。斎王制度は、古代における神と天皇をつなぐ神聖な役割を果たすもので、時代を通じて非常に重要視されてきました。
現在も明和町ではその歴史を継承する行事として「斎王まつり」が毎年開催されており、放送では第39代斎王役を務める三田空来さんの様子が紹介されました。発掘調査も進んでおり、江戸時代の伊勢路とは異なる古代の巡礼路の存在も明らかになってきています。こうした歴史は、ただの神話や伝承ではなく、発掘された土器や建物の痕跡から実在が裏付けられており、私たちの目に見える形で古代の息吹を伝えてくれています。
江戸時代の旅人に愛された二見浦の絶景

伊勢神宮へ向かう途中、タモリさんたちは「二見浦(ふたみがうら)」に立ち寄りました。ここは古くから旅人の心を癒す景勝地として知られており、特に「夫婦岩(めおといわ)」の存在はあまりにも有名です。二つの岩が仲睦まじく並ぶ姿は、夫婦円満の象徴とされ、江戸時代にはすでに多くの人々が訪れる名所となっていました。
晴れた日にはこの夫婦岩の間から富士山が見えることもあるとされ、実際に当時のガイドブック『伊勢参宮名所図会』にもその情景が描かれています。江戸時代の人々は、この地で敷物を敷き、波の音を聞きながら富士山と海の美しさに心を預けていたのでしょう。
さらに地形的にもこの地域は特別です。二見浦を通るのは、日本最大の断層の一つである「中央構造線」です。この断層上には、豊川稲荷・伊勢神宮・高野山といった信仰の拠点が並んでおり、日本人の精神文化を支える地理的な“神の道”としても注目されています。信仰と地形が結びついたこの事実は、現代人にとっても神秘的に映ることでしょう。
外宮から内宮へ 伊勢神宮の本質を知る

旅の最後、タモリさんたちはついに伊勢神宮 外宮に到着します。ここで案内役を務めたのは、伊勢神宮に詳しい音羽悟さんです。伊勢神宮には「外宮(げくう)」と「内宮(ないくう)」という二つの正宮があり、古来より外宮を先に参拝することが習わしとなっています。
外宮では「豊受大御神(とようけのおおみかみ)」という、食事や農業を司る神が祀られています。これは内宮の主祭神「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」が祀られた約500年後に迎えられたとされており、食の重要性がいかに高く考えられていたかが分かります。
特に注目されたのは、外宮の中にある「土宮(つちのみや)」です。このお宮は唯一東を向いているという特異な存在で、その理由には深い意味があります。一般的に神社は南向きに建てられることが多いのですが、土宮は西に流れる「宮川」に向かって祈るために東向きになっていると考えられています。宮川は豊穣をもたらす源とされ、古代の人々は川の恵みに感謝し、祈りを捧げていたのです。
このように、社殿の向きひとつとっても、そこに込められた自然と共に生きる信仰心が垣間見えます。旅の最後には、いよいよ伊勢神宮 内宮へと足を運び、すべての旅路がつながっていきます。
お伊勢参りの道は、人々の想いをつなぐ道
今回の「ブラタモリ」では、伊勢神宮そのものだけでなく、そこに至るまでの道のりがどれほど重要だったのかを教えてくれました。斎王や斎宮の歴史、庶民の願い、地形と信仰の結びつき——すべてが複雑に絡み合いながら、一つの“お伊勢参り”を形作っていたのです。
江戸時代、庶民にとって伊勢参りは人生一度の大きな夢でした。旅は決して楽なものではなく、何日もかけて歩き続け、雨風にも耐えながら伊勢を目指しました。そんな中でも人々は、道中の景色や名所を楽しみ、地元の人々と触れ合いながら、神に会うという目的に心を向けて歩みを進めていったのです。
それは現代の私たちが忘れかけている「祈り」や「感謝」の気持ちを思い出させてくれる旅でもあります。今回の放送は、歴史と地理、そして人々の暮らしが織りなす「日本の精神文化」の奥深さを再認識させてくれました。未来へつなげるべき大切な知恵や信仰の形が、伊勢の道には静かに息づいています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

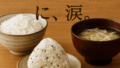

コメント