夫や妻との死別をどう乗り越えるか?ひとりを生きるためのヒント
2025年6月25日のNHK「あさイチ」では「配偶者との死別~ひとりを生きるヒント」というテーマで放送されました。番組では、配偶者との死別後に直面する寂しさや生活の変化、住まいや病気への備えについて、実際の体験談を交えて紹介しました。出演者は廣瀬雄大さん、鈴木奈穂子さん、博多大吉さん、博多華丸さん、駒村多恵さん、ゲストの榊原郁恵さん、的場浩司さんです。
夫や妻を亡くしたあとの寂しさと心の整理
番組では、最初に2年前に夫を亡くした瑛子さん(仮名・69歳)の姿が紹介されました。瑛子さんは、夫と死別してから3年近くが経ちますが、今もふとした瞬間に気持ちが乱れるそうです。悲しみは消えたわけではなく、突然こみ上げてくることがあるといいます。近い家族や知人には涙を見せることができず、一人で気持ちを抱え込んでしまうことが多いそうです。
そんな瑛子さんが今、心を落ち着けるためにしていることは、同じような体験をした人が書いた本を読むことです。本の中で語られる体験や気持ちに共感し、自分だけではないと感じることで、少しずつ気持ちを整理しているといいます。
スタジオでは、榊原郁恵さんも自らの経験を語りました。榊原さんは、日常の何気ない場面で急に寂しさがこみ上げることがあるといいます。そのとき、子どもたちにも素直に話せず、つらい時間を過ごすことがあるそうです。
また、番組には小谷みどりさんも登場しました。小谷さんは、夫が突然亡くなったとき、最初は信じられず、「出張に行っているのだ」と思い込んでいたといいます。それほど現実を受け止めるのが難しく、頭と心が追いつかなかったそうです。
小谷さんは、同じ境遇の人たちとつながるために「没イチ」という言葉を積極的に使っています。没イチとは、配偶者と死別した人を表す言葉で、悲しみや孤独を分かち合える仲間を見つけやすくするための言葉です。
このように、
・突然の別れは誰にとっても大きな衝撃になる
・気持ちの整理はすぐにはつかず、時間がかかる
・家族や周囲に気持ちを打ち明けづらいこともある
・同じ体験をした人の本や話に触れることで、心が少し軽くなる
・新しい言葉「没イチ」を通じて同じ立場の人とつながれる
という現実が、番組では具体的に伝えられました。配偶者を亡くした悲しみは簡単には消えませんが、少しずつ自分らしい生活を取り戻す工夫が紹介されていました。
自分らしいひとり暮らしに向けての工夫
番組では、1年前に夫を亡くした竹本澄惠さん(72歳)の暮らしが紹介されました。竹本さんは長年連れ添った夫を亡くしたあと、これまでの生活を少しずつ見直して、自分らしいひとり暮らしを始めています。
夫婦で暮らしていた頃は、車で移動することが多かった竹本さんですが、夫の死後、車の免許を返納しました。その代わりに、娘さんが買ってくれた電動自転車を愛用しています。電動自転車があることで、遠くまで買い物や用事に出かけることができ、生活の行動範囲が広がっています。
住まいは、3階建ての一軒家。以前は夫と二人で住んでいましたが、今はひとり暮らしです。最初は寂しさや不安があったものの、10年来の友人で同じように夫を亡くしたるりさんと支え合いながら、前向きに暮らしています。
竹本さんは、夫がいた頃は外食が多かったそうですが、今は積極的に台所に立つようになりました。最初はひとりでの食事が侘しく感じたそうですが、料理をすることで気持ちが前向きになり、今ではその時間が大切なひとときです。結果として、食生活が整い、体重も減り、体調が一番良くなったと話していました。
夜になると、家族や友人に電話をかけづらい時間もありますが、竹本さんはAIが話し相手になってくれるアプリを使っています。AIとの会話が、ひとりの夜の孤独感を和らげてくれているそうです。
スタジオでは小谷みどりさんが、ひとり暮らしを前向きにするために必要な4つのポイントを紹介しました。
・テクテク…外に出て、できる範囲で体を動かすこと
・カミカミ…よく噛んで食事を楽しみ、健康を保つこと
・ニコニコ…友達や知人と会話し、笑顔を忘れないこと
・ドキドキ…新しいことに挑戦し、毎日に刺激を持つこと
さらに、最近ではスマートウォッチなどの見守り機能を活用する高齢者も増えています。緊急時には、子どもや119番へ自動で通知が送られるので、安心してひとり暮らしを続けることができます。
このように、工夫や小さな挑戦を積み重ねることで、自分らしいひとり暮らしを少しずつ実現していく様子が紹介されました。
妻を亡くした男性の苦悩と地域のつながり
番組では、4年前に妻を亡くした佐藤さん(仮名・73歳)の生活が紹介されました。佐藤さんの妻は、自宅の庭で突然倒れ、そのまま帰らぬ人になったといいます。何の前触れもなく訪れた別れに、佐藤さんは今も気持ちの整理がつかずにいます。
現役時代は、5人の子どもたちを育てるために一生懸命働き、家のことはすべて妻に任せていたそうです。そのため、妻の死後は家事全般が手につかず、洗濯物も畳まずリビングに置きっぱなしの状態が続いています。
子どもたちはSNSで毎日のように連絡をくれたり、料理が得意でない佐藤さんのために食事を届けてくれることもあります。それでも、佐藤さんは家事や生活のリズムを整えることができず、家に閉じこもりがちで、孤独感が強い日々を送っています。
そんな佐藤さんが頼ったのが地域包括支援センターです。最初は相談するのも迷ったそうですが、思い切って訪れ、今一番困っている「話し相手がいない」「人とのつながりがない」という悩みを打ち明けました。
そこで紹介されたのが、地域で定期的に開かれている趣味のサークルでした。音楽好きな佐藤さんは、レコード喫茶の活動に興味を持ち、思い切って見学に行くことにしました。レコード喫茶では、懐かしい音楽が流れ、同世代の人たちが集まって、昔の話をしながら楽しい時間を過ごしていました。佐藤さんも久しぶりに懐かしい歌を聴き、「また行ってみようかな」と前向きな気持ちが生まれたといいます。
このように、
・突然の死別は、家事や生活に大きな影響を与える
・頼れる家族がいても、心の整理はすぐにはつかない
・地域包括支援センターは、話し相手や趣味の場を紹介してくれる
・趣味を通じた人とのつながりが、孤独を和らげる
という現実が紹介されました。高齢のひとり暮らしでは、家事や健康の不安だけでなく、人とのつながりを保つこともとても大切だと番組では伝えられていました。
病気と身元保証人の問題
番組では、6年前に夫を亡くした淳子さん(63歳)の体験が紹介されました。淳子さんは夫が生前大切にしていた畑を今も引き継ぎ、毎日1時間ほど手入れをすることが心の拠り所になっています。畑仕事は気持ちを落ち着かせ、亡き夫とのつながりを感じられる大切な時間です。
そんな中、淳子さん自身も体調を崩し、2年前にがんが見つかりました。治療のために入退院を繰り返す生活が始まりましたが、そのたびに病院から求められたのが身元保証人や連帯保証人の署名です。
淳子さんには近くに住む娘や姉がいたため、頼ることができましたが、それでも毎回署名や手続きが必要で、大きな負担を感じたといいます。もし家族や親族がいなかったら、入院そのものが難しかったかもしれません。
実際には、身元保証人がいないことを理由に病院が入院を拒否するのは認められていません。厚生労働省もそのように指導していますが、現場では保証人を求められるケースが多いのが現実です。
また、病院だけでなく、
・賃貸住宅の契約
・介護施設への入所
といった場面でも、保証人が必要になることがあります。保証人がいない人向けに、身元保証や生活支援、死後の事務手続きまで対応する「高齢者等終身サポート事業」というサービスもありますが、費用は数十万円から200万円ほどと高額です。そのため、経済的に余裕のある人でなければ利用が難しく、実際に国民生活センターにも利用者からの苦情が寄せられています。
このように、病気や高齢による一人暮らしでは、保証人問題が大きな壁になることが多く、頼れる家族や相談先を事前に確保しておくことが安心につながります。番組では、医療ソーシャルワーカーや社会支援室など、早めの相談が大切だと呼びかけていました。
高齢の一人暮らしと住まいの問題
番組の最後に、5年前に夫を亡くした和子さん(仮名・83歳)の暮らしが紹介されました。和子さんは現在、年金だけで生活しており、月の受給額は約4万円と、とても少ない収入でやりくりしています。夫の死後、生活が厳しくなり、区役所から生活保護の申請をすすめられたそうです。
しかし、当時住んでいたアパートの家賃は月6万5000円。生活保護で支給される家賃補助の上限は月4万5000円だったため、そのままでは申請を受けられず、住まいの問題が大きな悩みになりました。
そんな時、力になってくれたのが居住支援法人です。居住支援法人は、高齢者や障害者など、一般の賃貸物件を借りにくい人たちのために、物件探しや入居後の見守りを行ってくれる団体です。和子さんもこの支援を受けることで、安心して住める場所を見つけることができました。
相談は、
・自治体の窓口
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
を通じて行うことができます。また、国土交通省や都道府県のホームページでも情報が公開されています。相談や手続きは基本的に無料で、誰でも気軽に問い合わせることができます。
さらに、番組では、住まい探しをサポートする法律「住宅セーフティネット法」が改正されたことも紹介されました。これにより、高齢者や低所得者が賃貸住宅を借りやすくなり、住まいの確保がしやすくなっています。
和子さんは、生活保護の利用について「恥ずかしい」と感じていたそうですが、スタジオの小谷みどりさんは、生活保護は国民の権利であり、必要な支援を受けることは悪いことではないと話していました。実際に支援を受けたことで、和子さんは自分の生活を立て直し、安心して暮らせる環境を手に入れています。
番組では、住まいや生活が不安なときは、一人で抱え込まず、早めに自治体や専門機関に相談することの大切さが伝えられました。
いまオシ!LIVE 国産アーモンドの紹介
番組後半では、山梨県甲斐市の国産アーモンドが紹介されました。斜面を利用し、上下の風を通して湿度を下げる工夫をしています。グリーンアーモンドは渋抜きをして料理に使われ、料理人たちが様々なメニューを開発しています。
みんな!ゴハンだよ「あじの梅だれがけ」
料理コーナーでは「あじの梅だれがけ」が登場しました。あじを焼き、たたいた梅干しや酢、てんさい糖の梅だれをかけ、パン粉や細ねぎ、青じそ、みょうがをのせて完成。的場浩司さんは、梅やみょうがのさっぱり感が夏にぴったりだと感想を述べました。
【あさイチ】はなさんの「あじの梅だれ」レシピ!夏にぴったりさっぱり魚料理|2025年6月25日放送
今回の放送では、死別後の人生を自分らしく生きるためのヒントがたくさん紹介され、実際の体験談が心に響く内容でした。
情報ソース:
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


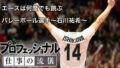
コメント