昭和百年(3)高度成長 やがて悲しき奇跡かな
戦後、日本は焦土からの復興を目指して必死に歩みを進めていました。しかし、国内だけの努力では立ち直りに時間がかかるはずでした。その流れを大きく変えたのが朝鮮戦争です。1950年に勃発したこの戦争は、日本にとって経済的な追い風となりました。日本製鋼所や神戸製鋼所などの工場がアメリカ軍からの大量の発注を受け、鉄鋼や機械の需要が爆発的に伸びました。これがいわゆる朝鮮特需で、日本経済の再生を一気に後押ししたのです。
昭和30年代に入ると、日本の経済成長率は年8%を超えるようになり、世界でも例を見ないスピードで成長を遂げます。農村からは多くの若者が都会へ移り住み、工場や建設現場で働くようになりました。一方で都市の人口急増に伴い、交通事故が多発する「交通戦争」や、大量のごみ処理、住宅不足といった新たな社会問題が浮上しました。。
【あさイチ】昭和・平成を生きた女性たちの本音と生活の変化を徹底解説|2025年3月24日放送
東京オリンピックと都市の大改造
1959年、東京オリンピックの開催が決定します。これは日本にとって、戦後復興を世界に示す大きなチャンスでした。池田勇人内閣はこの時期に所得倍増計画を掲げ、国民の生活水準を大きく引き上げる政策を進めました。減税や金利引き下げを行い、設備投資と消費を刺激したことで経済はさらに加速していきます。
東京では首都高速道路や国立代々木競技場第二体育館など、インフラや競技施設の建設が急ピッチで進められました。当時の建材としてアスベストが多用され、後に深刻な健康被害の要因となることが知られるようになります。
1964年に開かれた東京オリンピックでは、日本の女子バレーボール代表が圧倒的な強さで金メダルを獲得しました。厳しい指導で知られる大松博文監督の姿は、ドキュメンタリー映画「挑戦」に記録され、日本国民に大きな感動を与えました。
ベトナム戦争と世界第2位の経済大国へ
しかし、オリンピック後の日本経済は一時的に冷え込み、昭和40年には不況に陥ります。そんな中、アメリカがベトナム戦争に参戦したことにより再び特需が発生しました。軍需関連の需要が高まり、日本の輸出は急増。これをきっかけに日本経済は息を吹き返します。
1968年、日本はついに世界第2位の経済大国にまで成長しました。国内ではテレビや洗濯機、冷蔵庫といった「三種の神器」が広がり、生活は豊かになっていきます。家庭内では「専業主婦」という言葉が一般化し、都市生活を支える新しいライフスタイルが定着していきました。
大阪万博と公害問題の噴出
1970年、大阪で開かれた日本万国博覧会(大阪万博)は、戦後日本の象徴的なイベントとなりました。シンボルとしてそびえ立った岡本太郎の太陽の塔は今なお強烈な印象を残しています。日本の技術力と未来志向を世界に示す場となった一方で、社会の裏側では深刻な問題が顕在化していました。
高度成長の影で放置されてきたのが公害問題です。水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそくといった病気が各地で発生し、多くの人々が苦しみました。経済成長が必ずしも国民の幸福につながらない現実を突きつけられ、日本社会は大きな疑問に直面します。また、仕事に追われる日々を拒否する若者が現れ、「蒸発」や「失踪」という社会現象も増加しました。地方から都会に出る若者の数も減り、労働力不足が深刻化していきます。やがて1973年のオイルショックをきっかけに、日本の高度成長時代は終わりを迎えました。
安定成長と昭和の終焉
高度成長の終わりのあと、日本は安定成長期に移行します。そして1986年にはバブル景気が始まり、土地や株価が急騰しました。しかしその裏では、成長を最優先にしてきた社会のひずみが改めて注目されるようになります。アスベスト被害、過労死、セクシャルハラスメントといった問題が社会で広く語られ始めました。経済的豊かさと引き換えに、労働や生活に潜む大きな課題を日本は抱えていたのです。こうして激動の昭和は幕を閉じ、平成の時代へと移っていきました。
まとめ
今回の「映像の世紀バタフライエフェクト」では、日本の高度経済成長がどのように始まり、どんな希望と矛盾を抱えていたのかが映像で丁寧に描かれました。朝鮮戦争やベトナム戦争という外的要因が成長を後押しした一方、公害や社会問題という負の側面も忘れてはなりません。「奇跡」と呼ばれた成長の裏には、必ず「悲しき現実」があった――そのことを現代の私たちにも問いかける内容でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

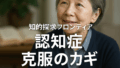
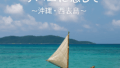
コメント