はやぶさが残した“挑戦の記憶”をたどる旅 執念の快挙はどう実現したのか
今回の『時をかけるテレビ』では、2010年に放送された『追跡!A to Z “はやぶさ”快挙はなぜ実現したか』が特集として紹介されました。スタジオには池上彰、そしてゲストの中川翔子が参加し、“サンプルリターン”という前例のない挑戦の裏側を改めて深掘りしていきました。
この記事では、番組で語られたすべてのエピソードを整理しながら、当時の緊張感・技術者たちの創意工夫・そして挑戦が未来へつながっていく姿まで、読みやすく丁寧にまとめています。
読むことで、はやぶさの壮大な冒険を“技術”だけでなく“人の情熱”を軸に理解できるようになります。
NHK【クローズアップ現代】宇宙ビジネス最前線!日本企業の月面挑戦と勝ち筋は?2025年7月2日放送
オープニングで示された“はやぶさ再評価”の意義
番組の冒頭では、オープニング映像に続き池上彰が今回のねらいを説明しました。
取り上げたのは、世界で初めて小惑星の砂を地球へ持ち帰った探査機『はやぶさ』。成功だけが語られがちですが、実際にはプロジェクト崩壊の危機や、通信断絶、エンジントラブルなど、想像以上に過酷な旅路がありました。
ゲストの中川翔子も、2010年当時に感じた感動を振り返りながら、「華やかに見える偉業の裏にこんなドラマがあったなんて」と驚きの表情を浮かべていました。
番組の雰囲気としては、「再放送」ではなく「当時を新しい視点で読み直す」意図がはっきり感じられる構成でした。
はやぶさプロジェクトの全体像と80名の挑戦
本編では、まず探査機『はやぶさ』のミッションがどれほど難易度の高い挑戦だったのかが説明されました。
『サンプルリターン』という目標を掲げ、総責任者の川口淳一郎さんのもと、技術者・研究者ら約80名がチームを組んだ『はやぶさプロジェクト』。ここには、宇宙航空研究開発機構・相模原市の宇宙科学研究所や、丸の内の広報拠点など、さまざまな現場での努力が積み重なっていました。
ただの“探査機を飛ばす”計画ではなく、“小惑星に降りて砂を取って地球に持ち帰る”という人類初の挑戦。番組でも、これが「技術力の限界を押し上げる試行錯誤の連続」だったことが丁寧に描かれていました。
2005年11月20日 初の着陸と離脱の指令
最初の大きな山場が2005年11月20日のイトカワ着陸です。
探査機がイトカワに接近し、着陸を試みたものの、安全性の確証が得られず、“途中離脱”の指令が発せられました。
この場面は当時ニュースでも報じられましたが、番組では「なぜ離脱が必要だったのか」「どう判断されたのか」まで詳しく紹介され、視聴者が当時の緊迫感を改めて感じられる構成になっていました。
着陸に失敗したのでは、という不安がプロジェクト全体に広がり、先行きが見えなくなる瞬間でした。
2005年11月25日 2回目の採取試行と“まさかの沈黙”
5日後の11月25日、2回目の砂採取の試行が行われます。
機体がイトカワから離れたように見えたため「うまくいった」と思われましたが、実際には採取装置は作動しておらず、さらにははやぶさとの通信が突然途絶えてしまいます。
ここで番組は一気に緊張感を増し、「行方不明」という最悪の事態に触れました。
この時期には、内部でも「プロジェクトは中止すべきでは」との空気が漂ったと紹介され、チームがどれほど深刻な状況に追い込まれていたかがよく分かりました。
はやぶさ“消息不明47日”の裏にあった執念の捜索
はやぶさの電波が途絶えてから47日間、チームは探査機の捜索に全力を注ぎました。
このときの姿を番組では「諦めるという選択肢がなかった」と表現していましたが、実際には技術的にも精神的にも限界に近い挑戦だったはずです。
捜索の拠点となったのは、佐久市にある臼田宇宙空間観測所。巨大なパラボラアンテナで、遠く離れたはやぶさの微弱な電波を探し続けました。
そして47日目、ついに通信が復旧。
番組映像からも、当時の現場の安堵が伝わってくるような構成で、この瞬間がチームにとってどれほど大きかったかが”間”で表現されていました。
姿勢制御の危機と技術者のひらめき
通信が戻ったものの、はやぶさは深刻な姿勢制御の問題を抱えていました。
ここで登場するのが電機メーカーの技術者白川健一さん。彼が提案したアイデアにより、姿勢制御の問題をなんとか回避し、はやぶさは再び地球へ向けて動き始めます。
さらに、最も絶望的だったのが“エンジン全停止”という異常。
絶体絶命の中で、宇宙航空研究開発機構の國中均さんが「2つのエンジンをつなぎ合わせる」という前例のない発想を提示し、はやぶさは再び軌道を修正する力を取り戻しました。
番組では、ここを非常に丁寧に描写し、「技術者のひらめきと執念」がどれほど偉業を支えたかを視聴者に強く印象付けていました。
2010年6月13日 帰還の日が描いた光
そしてついに、2010年6月13日。
はやぶさは大気圏に突入し、その前にサンプル入りのカプセルを分離。地球の姿を最後に撮影し、流れ星のように燃え尽きてミッションを終えました。
映像としての美しさ、そして背景にある7年越しの努力。そのすべてが胸を打つクライマックスです。
スタジオでは、中川翔子が「可能性を諦めなかったみんなの気持ちが伝わった」と感想を述べ、番組は一つの区切りを迎えました。
はやぶさ2、そして未来へ続く挑戦
後半では、後継機『はやぶさ2』についても紹介されました。
2014年に打ち上げられ、2020年にサンプルを地球に届け、その後も旅を続けています。現在は火星の衛星を観測し、将来的に帰還する計画も進行中。技術と挑戦は確実に次の世代へ受け継がれています。
一人の少年が“夢”を仕事に変えた物語
番組の最後に紹介された六尾圭悟さん(25)のエピソードも印象的でした。
はやぶさの旅を見た小学生だった彼は、その後の進路を“宇宙一筋”で選び続け、宇宙学が学べる学校を探して進学。大学では航空宇宙工学を学び、現在はIHIエアロスペースで働いています。
一つのミッションが、未来の技術者を育てる力を持つ——その象徴的な例として番組はこの話を丁寧に紹介していました。
まとめ
今回の特集を通して見えてきたのは、はやぶさの旅が“失敗と成功の積み重ね”で成り立っていたという事実です。
・前例のない挑戦
・何度も訪れた危機
・技術者たちのひらめきと執念
・諦めない姿勢が生んだ帰還の光
そのすべてが、今の宇宙探査の基盤をつくっています。
そして、はやぶさを見て育った世代が、今まさに次のプロジェクトを支える立場になりつつあります。
挑戦が“未来へ続くバトン”であることを強く感じさせる放送でした。
読んでくださった方にも、この壮大な物語が少しでも鮮やかに伝わっていればうれしいです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


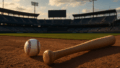
コメント