博多大吉が見た“いま”の能登半島|2025年5月19日放送
2025年5月19日放送のNHK「あさイチ」では、地震から約1年半が経った能登半島の現在の様子が特集されました。多くの視聴者から「能登を応援してほしい」との声が届いたことを受けて、博多大吉さんが現地を訪れ、復興に向けて奮闘する人々の姿を取材しました。番組では、かつての観光名所・輪島の朝市通り、絶景の千枚田、幻のブランド牛・能登牛の生産地、そして新たに生まれた居酒屋やラーメン店まで、“今”の能登の現状と人々の努力が描かれました。
朝市通りの再生を目指して

大吉さんが最初に足を運んだのは、かつて「日本三大朝市」の一つとして多くの観光客でにぎわっていた石川県・輪島市の朝市通りです。現在は建物がすべて撤去され、見渡す限りの更地となっており、地震とその後の大規模火災によって受けた被害の深刻さを物語っていました。以前は所狭しと並んでいた店々もなく、街の静けさと空白が、復興までの長い道のりを感じさせます。
しかしその一方で、出張朝市という形で再出発した店主たちの力強さと工夫が印象的でした。火災で店舗を失った30軒の商店が、市内の商業施設に集まり、それぞれの店が営業を再開しています。
-
会場には、手作りの竹細工や木製のお箸など、地元らしさにあふれた品々が並ぶ
-
能登名物の発酵調味料「いしる」も販売され、人気を集めている
-
一店一店に立ち寄る来場者の姿が多く、人と人とのやり取りが活発に交わされていた
出張朝市の運営を手がけたのは、地元の冨水長毅さん。「とにかく戻ることが我々の目標」という言葉の通り、商店主たちは復興への一歩を自らの手で踏み出していることが伝わります。まだ本来の朝市通りに戻るには区画整理や土地の権利問題など、越えなければならない課題も多くありますが、それでも日々の営業の中で活気を取り戻しつつある姿は、見る人の心を動かします。
この日、大吉さんも実際に店舗をめぐり、地元の特産品を購入。どの店もエネルギーに満ちており、自然と足が止まり、会話が生まれる空間となっていました。その様子に触れて、大吉さんは「ウィンドウショッピングは無理。どこも素通りできない」と話しており、店主たちの熱意が空間全体に溢れていたことが伺えます。
この朝市の光景は、ただの買い物の場ではなく、地域が再び前に進もうとする希望の象徴でもありました。建物は失っても、人と人のつながりと商いの力はしっかりと残されている――それを実感できる現場となっています。
絶景・千枚田も被災、それでも復興へ

次に大吉さんが訪れたのは、石川県輪島市にある「白米千枚田」です。ここは、山と海の間に広がる美しい棚田が連なる、日本の原風景とも言える絶景スポットです。しかし、地震の揺れによって田んぼの約8割に亀裂が入り、さらにその後の豪雨によって土砂が流れ込み、大きな被害を受けてしまいました。
今年の春、田植えができたのは全体のわずか4分の1の面積にとどまりました。それでも、地元の方々の努力によって復旧作業は一歩ずつ進められています。
-
先月、道の駅「千枚田ポケットパーク」が1年4か月ぶりに営業を再開
-
店頭には千枚田で育てた新米を使ったおにぎりや特産品が並び、観光客を迎える体制が整いつつある
-
一部の田には水が張られ、棚田らしい風景が少しずつ戻ってきている
こうした動きのなか、常盤貴子さんもロケで千枚田を訪れ、田植えを体験しました。ここでは今も手作業による田植えが行われており、日本では失われつつある伝統的な農法が守られています。機械が入らない斜面での作業は大変ですが、それでも地域の人々とボランティアの力で守られています。
今年は、全国から約100人のボランティアが集まり、ひとつひとつ手で苗を植える田植え作業が実施されました。泥に足を取られながらの作業でも、参加者は一体感を感じながら棚田の再生に力を注ぎました。
自然の猛威によって一時は姿を失いかけた千枚田ですが、地元の方々と支援の手によって、また一歩、風景が戻りつつあります。田に映る空の色、海とのコントラスト、そして手作業で植えられた苗たちが、また新たな季節の営みを始めています。
幻のブランド牛・能登牛と畜産農家の苦闘
次に博多大吉さんが訪れたのは、石川県能登町で能登牛を育てる畜産農家です。能登牛は年間に約1000頭しか市場に出回らない希少なブランド牛として知られています。やわらかな肉質と甘みのある脂が特長で、多くの料理人からも高く評価されています。しかし、地震によってこの貴重な生産地にも深刻な影響が及びました。
地震発生後、被害は生活インフラだけでなく、家畜にも及びました。
-
電気と水道が1か月にわたり停止し、牛に必要な1日20リットルの飲み水を確保するのが困難に
-
ストレスが原因で牛が死亡するケースも相次ぎ、90頭いた牛は60頭まで減少
-
牛舎には地割れが入り、安全な飼育環境が損なわれたため、新しい牛舎の建設を計画しているが、自己負担は2000万円にものぼる
このような状況の中、18軒ある能登牛の農家のうち、すでに3軒が廃業を決断。残った農家も厳しい経営環境のなかでなんとか持ちこたえています。
大吉さんは現地で実際に子牛にミルクを与える作業を体験しながら、農家の現状に触れ、日々の苦労や再建に向けた努力に強く胸を打たれていました。牛舎には静かな空気が流れ、まだ完全には戻らない日常のなかで、牛たちの穏やかな姿が少しだけ希望を感じさせてくれます。
自然災害による直接的なダメージだけでなく、復旧のための資金や人手の確保など、課題は山積しています。それでも地元の方々は、能登牛という地域の誇りを守り抜こうと奮闘を続けていました。
能登牛は、単なる「高級食材」ではなく、人と土地が育んできた文化と誇りの象徴でもあります。ふるさと納税やお取り寄せなど、外からできる支援が、これからの畜産の未来につながっていきます。
新たに始まる店と、奮闘する人々
輪島市では、地震で店舗を失った料理人たちが新たな形で立ち上がろうと、力を合わせて居酒屋を開店しました。店をまとめるのは、かつてフランス料理店を営んでいた池端隼也さん。地震で店舗が全壊し、営業を続けることができなくなった中、炊き出しの現場で出会った料理人たちと手を組み、それぞれが得意な料理ジャンルを持ち寄って、新たなスタイルの居酒屋を誕生させました。
この居酒屋では、能登の地元食材をふんだんに使った創作料理が次々と生み出され、観光客だけでなく地元の人たちにも喜ばれています。被災によって分断された人と人が、食の場で再びつながり直す場所として、静かに力強く営業を続けています。
-
メニューには地元で獲れた魚介類や旬の野菜など、能登ならではの食材が活かされている
-
各料理人が腕を振るい、フレンチ・和食・郷土料理の垣根を越えた料理を提供
-
店舗は、もともと使われていなかった建物を再活用し、地域の再生にも一役買っている
この店では、別の角度からも復興の歩みが始まっています。海岸の隆起によって漁ができなくなった素潜り漁の海女さんたちが、働く場所としてこの店を選びました。橋本真理子さんもそのひとりで、もともとは輪島の海で漁をして生計を立てていたものの、地震による活断層の影響で海が陸になり、漁場が失われてしまったのです。
-
海底が隆起したことで磯が遠くなり、海産物の採取が困難に
-
水揚げ施設も被害を受け、受け入れ体制の不備が続く
-
モズク漁は一度再開されたが、その後の豪雨で海の環境が大きく変わってしまった
それでも、橋本さんは漁の再開を信じて、7月からの復帰を目指して毎日3時間の筋トレを続けています。居酒屋で働きながらも、海に戻る日を夢見て準備を続ける姿には、地元の自然と共に生きてきた人の強さが感じられます。
港には今も多くの漁船が並んでいますが、水揚げ体制が整わないため、本格的な漁はまだ再開できていません。それでも人々は諦めることなく、それぞれの形で生活を立て直し、未来へ向かって動き始めています。
食と仕事の場が新たに生まれ、人と人がつながり直すことで、地域の力は確実に再生へ向かっています。この居酒屋は、そんな希望の象徴のひとつとなっていました。
新たな希望、地元のラーメン店も再出発

輪島市では、震災を乗り越えて新たな挑戦に踏み出した若き料理人・河上隼人さんのラーメン店が今年1月に開店しました。この店は、地元で獲れる新鮮な魚を使って丁寧に取った出汁をスープに仕立てているのが特徴で、素材の旨みを最大限に生かした一杯が評判となっています。
このラーメン店の背景には、被災後に炊き出しで知り合った仲間たちとの強い絆があります。前述の居酒屋で共に働いた料理人たちから、出汁の取り方や味づくりのコツを学び、それをベースに独自の味を作り上げました。
-
使用する魚は地元産にこだわり、鮮度と風味を重視
-
スープはあっさりながらもコクがあり、誰にでも親しみやすい味
-
店の雰囲気は明るく清潔で、復興の中で生まれた新しい希望を感じさせる
震災からの復興には長い時間がかかりますが、こうした新しい店舗の誕生は、地域に元気と誇りを取り戻すきっかけとなっています。河上さんのように、困難な状況の中でも一歩を踏み出した若い力が、次の世代の輪島をつくっていく大きな原動力になっているのです。
被災地でも、新たな挑戦は確かに芽生えています。店を開く勇気、地域の素材を活かす工夫、仲間と助け合う心――そのすべてが、輪島のこれからを明るく照らす光となっていました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

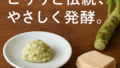
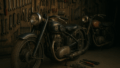
コメント