日本初のパンダ来日!ランラン・カンカンの物語とその舞台裏
1972年、日本に初めてやってきたジャイアントパンダ「ランラン」と「カンカン」は、当時の人々を夢中にさせました。中国からの贈り物として上野動物園にやってきた2頭は、国交正常化の象徴であり、同時に空前のパンダブームを巻き起こしました。公開初日には長蛇の列ができ、上野駅から動物園まで続くほどの人出となり、「2時間並んで見るのはわずか50秒」という状況もあったといいます。見た目のかわいらしさだけでなく、外交的な意味も持った2頭は、日本と中国の友好の証として特別な存在となりました。
飼育員たちの奮闘と初めての挑戦
ランランとカンカンは、日本にとってまったく未知の動物でした。それまで国内にジャイアントパンダの飼育経験はなく、現場には参考になる事例がほとんどありません。到着直後から、用意した竹を食べてくれない、慣れない環境でストレスがたまり呼吸数が異常に上がるといった問題が続出しました。飼育員たちはまず食事面の対策に追われ、竹の産地や種類を変えて試し、時には笹や果物、特製のクッキーのような補助食を与えるなど工夫を重ねました。
情報収集と環境づくりの工夫
当時の動物園スタッフは、限られた情報を補うために外国語の論文や飼育マニュアルを翻訳し、少しでも役立つ知識を得ようと奔走しました。中国からのアドバイスも貴重でしたが、気候や環境が異なる日本で同じ方法が通用するとは限らず、温度や湿度、日陰の作り方まで一つひとつ調整を行いました。パンダ舎の中には涼しい空気を送り込む設備や、直射日光を避けられる構造が導入され、健康維持に努められました。
繁殖への挑戦と新たな試み
やがて、2頭の繁殖への挑戦が始まりました。自然交配を試みましたが、発情期のタイミングや相性、行動の違いからなかなか結果は得られませんでした。そこで導入されたのが人工授精という新しい方法です。国内では前例がほとんどなく、獣医師や研究者と連携しながら、麻酔や採精、受精の技術を少しずつ確立していきました。この過程では、パンダの体調管理とストレス軽減を最優先に考え、一度の試みのたびに記録を詳細に残して次に活かす工夫が重ねられました。こうした地道な積み重ねが、後の日本でのパンダ繁殖成功へとつながっていきます。
命をつなぐ長い道のり
1979年、ランランは妊娠中毒症を発症し、懸命な治療もむなしく命を落としました。このときお腹の中に赤ちゃんは確認されず、日本初のパンダの赤ちゃん誕生は実現しませんでした。そのわずか翌年、1980年にはカンカンも心不全で急逝します。数年の間にペアの2頭を失ったことで、上野動物園は深い悲しみに包まれましたが、飼育員たちは前を向き、パンダの命をつなぐ取り組みを続ける決意を固めます。
新たなペアとの再出発
1982年、中国から新たにメスのホァンホァンとオスのフェイフェイが来園します。2頭は穏やかな性格で、環境にも少しずつ適応していきました。動物園ではこのペアでの繁殖を目指し、健康管理や食事の工夫に加え、発情期の観察や交配の準備が進められました。
人工授精の挑戦と成功、そして試練
1985年、日本で初めて人工授精による赤ちゃん「チュチュ」が誕生します。この瞬間は日本のパンダ飼育史において大きな快挙でしたが、生まれて数日後に命を落としてしまいます。それでもこの経験で得られたデータや技術は貴重な財産となり、次への道を開きました。
待望の自然交配成功
翌1986年、自然交配によって「トントン」が誕生します。トントンは順調に成長し、多くの来園者に愛される存在となりました。そして1988年には2頭目の赤ちゃん「ユウユウ」が生まれ、日本のパンダ飼育はようやく命をつなぐ成功の時代を迎えました。これらの成果は、失敗を乗り越えて努力を重ね続けた飼育員や研究者たちのたゆまぬ情熱の結晶でした。
番組で描かれる感動の実話
今回のNHK「熱談プレイバック」では、講談師・神田阿久鯉さんが、当時の貴重な映像とともにこの感動の物語を語ります。政治と文化、そして人々の情熱が交差した昭和の一幕が、当時の空気そのままによみがえります。放送後には、番組内で紹介されたエピソードや新たに明らかになった事実を追記し、より詳しい記事として更新する予定です。
放送情報
放送日 :2025年8月11日(月)
放送時間:18:05〜18:32
放送局 :NHK総合(東京)
出演者 :神田阿久鯉
番組を見て感じたこと
番組を見ながら、昭和47年のランラン・カンカン来日の映像に釘付けになりました。上野駅から動物園まで続く人の列、わずか50秒のために何時間も並ぶ姿から、当時のパンダブームの熱気と期待感が伝わってきます。同時に、あの2頭が単なる人気動物ではなく、日本と中国の国交正常化の象徴だったことも、改めて深く印象に残りました。
飼育員たちが、初めて接するジャイアントパンダのために試行錯誤を重ねる様子も心を打ちました。竹を食べない、環境に慣れない――そんな壁を一つずつ乗り越えるために、全国から竹を取り寄せたり、外国文献を翻訳したり、パンダ舎の温度や湿度まで調整したり。映像からは、動物を前にしたときの真剣なまなざしと、失敗を次につなげる粘り強さが伝わってきました。
繁殖への挑戦も、決して順風満帆ではありませんでした。人工授精への試みは国内ではほぼ前例がなく、体調管理やストレス軽減を第一にしながらの手探り。ランランとカンカンの死はあまりに早く、当時のスタッフの落胆は計り知れません。それでも歩みを止めず、次に迎えたホァンホァンとフェイフェイで人工授精と自然交配の両方に挑み、トントンやユウユウが誕生するまでの道のりは、まさに積み重ねの成果でした。
神田阿久鯉さんの語りは、事実を伝えるだけでなく、その背景にある人々の喜びや悔しさまで浮かび上がらせてくれます。昭和の街並みや動物園のにぎわいとともに、パンダと人が一緒に歩んだ年月が鮮やかによみがえり、最後まで胸が熱くなる放送でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


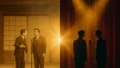
コメント